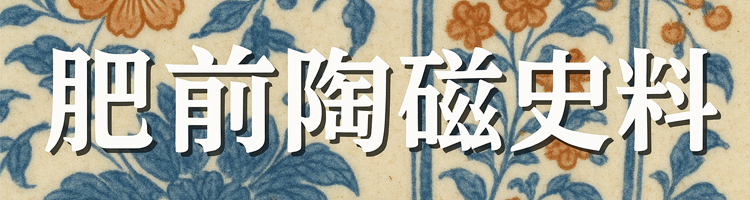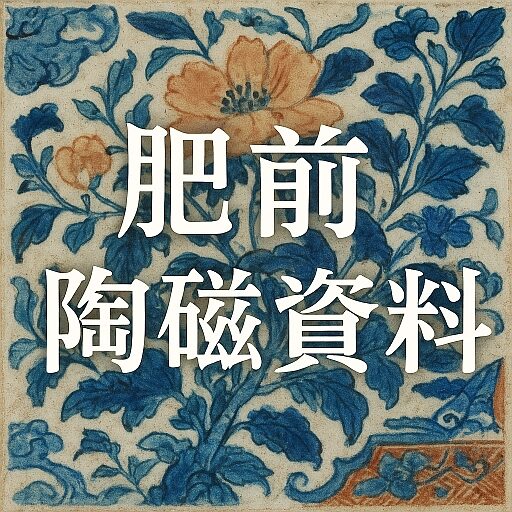【原文】[Original text]
縄文時代から江戸時代にかけて、日本の陶磁器はどのような変遷を辿ったのか?
「肥前陶磁史考」によると、縄文時代から江戸時代にかけて、日本の陶磁器は以下のような変遷を辿りました。
縄文時代(新石器時代)
日本の製陶の歴史は、新石器時代にコロボックル人が製作した「縄紋土器」に始まるとされています。当時は穀物栽培の技術が知られていなかったため、縄や藁ではなく、天然の葛や撚蔓などを生乾きの器に巻きつけて文様を施したと考えられています。この時代の土器は、粘土を捏ねて天日で乾燥させた後、偶然火に焼かれて堅くなることを発見したことから、火を用いた焼成が行われるようになったと推考されています。これは約2万5千年~1万2千年以前のこととされています。
弥生時代
次の時代には「弥生式土器」が登場します。特に天孫族が築いた大和橿原を中心とする弥生式土器は「高天原土器」とも称されました。この頃の土器は、地上に据え、砂で覆い、燃料を積み重ねて焼き上げる方法で製作された粗製品であり、まだ釉薬は施されていませんでした。日本の焼物は、当初、食器の他に祭器(斎瓮)として発祥し、埴輪、陶棺、杯、皿、坩などの素焼きの器が作られていました。また、倭製の土器の他に朝鮮式の甕類などの土器も存在していました。
古墳時代~飛鳥時代
朝鮮半島との交流が盛んになるにつれて、製陶技術も発展しました。仲哀天皇の御代(西暦200年頃)、神功皇后の三韓出兵の帰途、肥前国上松浦(後の唐津)に同行した韓土の陶工が帰化し、朝鮮式の製法を導入した「唐津焼」が始まったとされています。これは日本の朝鮮系製陶として最古の歴史を持つものとされ、当時の唐津焼は無釉陶でした。
雄略天皇の時代には、百済から陶工が招かれ、河内国桃原で陶器を焼かせました。また、百済からは仏教と共に建築用瓦の技術が伝わり、日本で初めて瓦が焼かれ屋根を葺くことが始まったのもこの頃です。斉明天皇の御代(西暦650年代)には、肥前国上松浦に渡来した韓人により「高麗焼」が創製され、これは日本における施釉陶の始まりとされています。
奈良時代~平安時代
奈良時代には、宮廷に筥陶司が置かれ、陶工人の管理が行われました。また、称徳天皇の時代には、陶器が日用の雑器として用いられるようになりました。
平安時代に入ると、中国から「青瓷」(セラドン、秘色)が仏具として大量に輸入され、非常に愛好されました。嵯峨天皇の弘仁年間には、入唐して中国の瓷器(青瓷)技術を習得した三家人部乙麿が、尾張国で日本初の硬度瓷器(青瓷)を製作し、日本の中興陶祖と称されるに至りました。
醍醐天皇の延喜年間には、陶器を朝廷に奉る「輪(わ)となす制度」が発布され、青瓷が朝貢品の上位、普通の陶器が中位、土器が下位という階級が設けられました。儀式においては、瓷器は銀器、陶器は朱漆器、土器は黒漆器に相当するとされました。
鎌倉時代~安土桃山時代
鎌倉・室町時代には、斜面に掘られた「窖窯」(大窯、鉄砲窯)といった窯式が用いられ、有名陶器が多数焼かれました。釉薬を施さない「焼締」陶器も作られています。
安土桃山時代、豊臣秀吉の時代には茶の湯が全盛期を迎え、千利休らの影響により、多種多様な茶器が求められました。特に古田重勝の趣向を凝らした「織部焼」(黒褐色や緑釉に草花が描かれた茶壺など)が製作されました。
秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)を契機に、朝鮮から多くの優れた陶工が日本に渡来しました。彼らは朝鮮では賤民級の身分でしたが、日本では各地の諸侯に手厚く迎えられ、製陶技術の発展に大きく貢献しました。この時期の唐津焼は、仁治3年(今から693年前)に瀬戸で開窯された時期、あるいはそれ以前において、既に優れた陶器が製作されており、その古さと発達ぶりは他と比類のないものでした。関西地方では焼物の総称として「唐津物」が用いられるほど、その影響力は広範でした。
江戸時代
江戸時代に入ると、日本の陶磁器の歴史は大きな転換点を迎えます。日本人の「潔癖性」から、衛生的で清潔な「白磁」の必要性が高まりました。
「肥前陶磁史考」は、日本における最初の磁器発祥地を肥前国の上白川窯、すなわち天狗谷であると断言しています。有田焼の誕生は、日本の製陶界に**「大いなる革命」をもたらしました。この白磁の製造は他の地域の窯元から大いに羨望され、各地でその製法を習得しようと努められ、結果として白磁の製作熱が全国的に勃興し、従来の陶器(黒物)製作に取って代わることになったのです。 肥前から搬出される製品は、白磁の生産が他の地域でまだ見られなかった時代において、「伊万里焼」が磁器の代名詞とされるほど、その存在感は絶大でした。 特に有田では、柿右衛門の陶技が円熟し、白磁に赤絵を施した作品は、世界中で高い評価を得ました。フランスでは中国明代の赤絵以上とされ、当時柿右衛門製品を世界第一と称されるほどでした。ヨーロッパではまだ磁器の製造技術が確立していなかったため、柿右衛門焼は非常に珍重されました。また、鍋島藩では、幕府への献上品として、高度な技術で焼かれた「鍋島青磁」などの高級品が製作されました。 製陶技術の面では、燃料が木材から石炭へと転換され、石炭窯が導入されました。また、匣鉢重積法や棚板積法といった窯積込みの技術も改良され、生産効率が向上しました。顔料においては、中国から輸入された呉須**(コバルト顔料)が主でしたが、後に酸化コバルトの使用も広まりました。しかし、有田焼固有の釉相調和を重視し、コバルトは一部の加合彩料に留まることになりました。
江戸時代を通じて、有田焼/伊万里焼は、国内外に広く流通し、日本の主要な輸出品として大きな役割を果たしました。
このように、日本の陶磁器は縄文時代の素朴な土器から始まり、朝鮮半島や中国からの技術導入、茶の湯文化の発展、そして肥前地域での磁器の創製という大きな変革を経て、江戸時代には国際的に評価される高度な美術工芸品へと進化を遂げたのです。
【英語訳】[English translation]
How did Japanese ceramics change from 縄文時代 through 江戸時代?
According to “肥前陶磁史考,” the trajectory from 縄文時代 to 江戸時代 unfolds as follows.
縄文時代(Neolithic)
Japan’s pottery begins with 縄紋土器 said to have been made by the コロボックル人. Because grain cultivation was not yet known, patterns were impressed not with rope or straw but by wrapping natural vines—葛 or twisted creepers—around leather-hard vessels. After kneading clay and sun-drying, people discovered that accidental firing hardened the ware; controlled firing then followed. This stage is dated to roughly 25,000–12,000 years ago.
弥生時代
The next phase brings 弥生式土器. Centered on 大和橿原 established by the 天孫族, it was also called 高天原土器. Vessels were set on the ground, covered with sand, and fired by heaping fuel—producing coarse wares without glaze. Early Japanese ceramics arose not only as tableware but also as 祭器(斎瓮); unglazed pieces such as 埴輪, 陶棺, cups, plates, and crucibles were made. Alongside 倭製 wares, Korean-style jars and other forms also existed.
古墳時代~飛鳥時代
With intensified contact with the Korean Peninsula, technology advanced. In the reign of 仲哀天皇 (around A.D. 200), potters from 韓土 who accompanied 神功皇后 on the return from the 三韓出兵 settled in 肥前国上松浦 (later 唐津) and introduced Korean methods, initiating 唐津焼—regarded as the earliest Korean-lineage production in Japan; at that time it was 無釉陶. Under 雄略天皇, potters were invited from 百済 to fire wares at 河内国桃原. From 百済 also came the technology of roof tiles, together with Buddhism—the first tiled roofs in Japan. In 斉明天皇’s reign (the 650s), immigrants in 上松浦 created 高麗焼, marking the start of 施釉陶 in Japan.
奈良時代~平安時代
In Nara, the court established 筥陶司 to oversee artisans; by the time of 称徳天皇, pottery had become everyday household ware. Entering Heian, large quantities of 青瓷(celadon, 秘色)were imported from China as Buddhist implements and were highly prized. During 嵯峨天皇’s 弘仁 years, 三家人部乙麿, after study in 唐, produced Japan’s first hard-bodied 瓷器(青瓷) in 尾張国, earning the title 中興陶祖. In 醍醐天皇’s 延喜 years, the court promulgated the tribute 「輪(わ)となす制度」, ranking 青瓷 highest, ordinary 陶器 middle, and 土器 lowest; in ritual correspondence, 瓷器 matched silverware, 陶器 matched vermilion lacquer, and 土器 matched black lacquer.
鎌倉時代~安土桃山時代
In the Kamakura and Muromachi eras, hillside 窖窯(大窯/鉄砲窯)were used and many notable wares were fired; unglazed 焼締 pieces also appeared. In the Azuchi–Momoyama era under 豊臣秀吉, 茶の湯 flourished; under 千利休’s influence, diverse tea wares were sought. 古田重勝’s taste fostered 織部焼—tea jars with black-brown or green glaze and floral designs.
Following 朝鮮出兵(文禄・慶長の役), many skilled Korean potters came to Japan. Though low-status in Korea, they were warmly received by local lords in Japan and greatly advanced ceramic techniques. In this period, 唐津焼 was already of high quality by 仁治3年—when 加藤春慶 opened a kiln at 瀬戸—or earlier, evidencing antiquity and development unmatched elsewhere; in 関西方, pottery in general was called 「唐津物」.
江戸時代
A major turning point arrived. Motivated by a cultural preference for cleanliness, the need for hygienic 白磁 grew. The text asserts that Japan’s first birthplace of porcelain was 上白川窯, namely 天狗谷, in 肥前. The emergence of 有田焼 brought a “great revolution” to Japan’s ceramic world. White-porcelain techniques were coveted nationwide, spurring widespread adoption that displaced earlier black-ware production.
Products shipped from 肥前—伊万里焼—became virtually synonymous with porcelain when other regions had yet to produce 白磁. In 有田, 柿右衛門 perfected techniques; white porcelain with 赤絵 won global acclaim—said in France to surpass Ming-dynasty 赤絵, and at the time praised as world-class, second to none. As Europe had not yet established porcelain manufacture, 柿右衛門 pieces were highly prized. Under 鍋島藩, luxury wares such as 鍋島青磁 were produced as offerings to the shogunate.
Technically, fuel shifted from wood to coal and coal-fired kilns were introduced. Loading methods such as 匣鉢重積法 and 棚板積法 improved efficiency. For pigments, imported 呉須 (cobalt) predominated, later joined by cobalt oxide; yet 有田焼 emphasized harmony of its own glaze palette, keeping cobalt mainly to certain overglaze mixtures. Throughout the Edo period, 有田焼/伊万里焼 circulated widely at home and abroad and became major export commodities.
In sum, Japanese ceramics evolved from the simple earthenware of 縄文時代, through technologies from the Korean Peninsula and China, the flowering of 茶の湯, and the porcelain breakthrough in 肥前, culminating in the Edo era as sophisticated artworks of international renown.
【中国語訳(原文から簡体字)】[Chinese Simplified from Japanese]
从縄文時代到江戸時代,日本陶瓷器经历了怎样的变迁?
据《肥前陶磁史考》,其大致脉络如下。
縄文時代(新石器时代)
日本制陶肇始于コロボックル人制作的縄紋土器。当时尚未知谷物栽培,因而并非以绳或稻草压纹,而是以天然藤蔓(葛、撚蔓)缠绕半干器身以成纹。先揉泥、日晒干燥,后因偶然遇火而石化,由此推及以火烧成之法。年代约在距今2万5千年至1万2千年前。
弥生時代
出现弥生式土器。以天孫族所建之大和橿原为中心,亦称高天原土器。其法为置于地上、覆以砂、复堆燃料而烧,属粗制,无施釉。日本烧造之初,除餐具外并有祭器(斎瓮);还制作埴輪、陶棺、杯、皿、坩等素烧器。除倭制造品外,亦见朝鲜式甕类等器物。
古墳時代~飛鳥時代
随与朝鲜半岛往来增多,制陶技术精进。仲哀天皇时(约公元200年),神功皇后三韩出兵返途,随行之韓土陶工归化于肥前国上松浦(后之唐津),引入朝鲜式法,创唐津焼,为日本朝鲜系制陶最古者,时为無釉陶。至雄略天皇时,自百済召陶工于河内国桃原烧器;并自百済与佛教同来之建筑用瓦技术,使日本始有瓦屋顶。斉明天皇(650年代)时,入上松浦之韩人创制高麗焼,标志日本施釉陶之开端。
奈良時代~平安時代
奈良时,宫廷设筥陶司以统摄陶工;至称徳天皇时,陶器已为日用杂器。平安时,大量自中国输入青瓷(秘色)为佛具,备受嗜好。嵯峨天皇弘仁年间,入唐习瓷之三家人部乙麿在尾張国制成日本首见之硬质瓷器(青瓷),被称为中兴陶祖。醍醐天皇延喜年间颁行贡纳之**「輪(わ)となす制度」**,以青瓷为上、常陶为中、土器为下;礼制上,瓷器当银器,陶器当朱漆器,土器当黑漆器。
鎌倉時代~安土桃山時代
鎌仓、室町时采用山坡掘筑之窖窯(大窑/铁炮窑),名品迭出;亦有无釉之焼締。安土桃山期在豊臣秀吉政权下,茶の湯极盛,受千利休影响,茶器多样化。因古田重勝之审美,形成織部焼(黑褐或绿釉并绘草花之茶壶)。
随朝鮮出兵(文禄・慶長之役),多位朝鲜名匠来日,虽在朝鲜为贱级,于日本却受诸侯礼遇,极大推进技术。此时之唐津焼,在仁治3年****加藤春慶于瀬戸开窑之际或更早,已臻上乘;其古老与发达在当时无可比拟;関西方甚至以「唐津物」为烧物通称。
江戸時代
此期为大转折。因讲求清洁,白磁之需求上升。书断言日本最初之磁器发祥地唯上白川窯(即天狗谷)在肥前。有田焼之兴起,为日本制陶界带来**“大革命”。白磁技法为诸地所羡,竞相学习,遂全国兴起并取代以往之黑物。 自肥前运出的伊万里焼在他地尚无白磁时几成磁器代名词**。在有田,柿右衛門技艺臻熟,白地赤绘名扬四海;法国甚至评为高于明代赤绘,时称世界第一。彼时欧洲尚未自制磁器,故柿右衛門器尤为珍重。鍋島藩亦以进献幕府为目的,烧造鍋島青磁等高级品。
技术上,燃料由木转煤,采用煤窑;并改良匣鉢重積法、棚板積法等装窑法以提效。色料以自华输入之呉須(钴)为主,后普及氧化钴;惟有田焼重视其釉色和谐,钴多限用于部分加合彩料。整个江户期,有田焼/伊万里焼在内外销路广阔,成为日本重要出口品。
综上,日本陶瓷自縄文時代之朴拙土器起,经由朝鲜与中国技术的导入、茶の湯文化之繁荣,并因肥前地区之磁器创制而大变革,至江户期发展为享誉国际之高水平美术工艺品。
【中国語訳(原文から繁體字)】[Chinese Traditionalfrom Japanese]
從縄文時代到江戸時代,日本陶瓷器經歷了怎樣的變遷?
據《肥前陶磁史考》,其大致脈絡如下。
縄文時代(新石器時代)
日本製陶肇始於コロボックル人製作之縄紋土器。彼時未識穀物栽培,非以繩或稻草壓紋,而以天然藤蔓(葛、撚蔓)纏繞半乾器身以成紋。先揉泥、日晒乾燥,後因偶遇火而石化,遂推及以火燒成之法。年代約在距今2萬5千年至1萬2千年前。
弥生時代
出現弥生式土器。以天孫族所建之大和橿原為中心,亦稱高天原土器。其法為置於地上、覆以砂、再堆燃料而燒,屬粗製,未施釉。日本燒造之初,除餐具外並有祭器(斎瓮);亦製作埴輪、陶棺、杯、皿、坩等素燒器。除倭製之外,亦見朝鮮式甕類等器物。
古墳時代~飛鳥時代
隨與朝鮮半島往來增多,技術精進。仲哀天皇時(約西元200年),神功皇后三韓出兵返途,隨行之韓土陶工歸化於肥前國上松浦(後之唐津),引入朝鮮式法,創唐津焼,為日本朝鮮系製陶最古者,時為無釉陶。至雄略天皇時,自百済召陶工於河內國桃原燒器;並自百済與佛教同來之建築用瓦技術,使日本始有瓦屋頂。斉明天皇(650年代)時,入上松浦之韓人創製高麗焼,標誌日本施釉陶之開端。
奈良時代~平安時代
奈良時,宮廷設筥陶司以統攝陶工;至稱德天皇時,陶器已為日用雜器。平安時,大量自中國輸入青瓷(秘色)為佛具,極受喜愛。嵯峨天皇弘仁年間,入唐習瓷之三家人部乙麿於尾張國製成日本首見之硬質瓷器(青瓷),被稱為中興陶祖。醍醐天皇延喜年間頒行貢納之**「輪(わ)となす制度」**,以青瓷為上、常陶為中、土器為下;禮制上,瓷器當銀器,陶器當朱漆器,土器當黑漆器。
鎌倉時代~安土桃山時代
鎌倉、室町時採用山坡掘築之窖窯(大窯/鐵砲窯),名品迭出;亦有無釉之焼締。安土桃山期在豊臣秀吉治下,茶の湯極盛,受千利休影響,茶器多樣化。因古田重勝之審美,形成織部焼(黑褐或綠釉並繪草花之茶壺)。
隨朝鮮出兵(文祿・慶長之役),多位朝鮮名匠來日,雖在朝鮮屬賤級,然於日本受諸侯禮遇,對技術發展貢獻甚巨。其時之唐津焼,於仁治3年****加藤春慶在瀬戸開窯之際或更早,已臻上乘;其古老與發達在當時無可比擬;關西方甚至以「唐津物」為燒物通稱。
江戸時代
此期為大轉折。由於講求潔淨,白磁需求上揚。書斷言日本最初之磁器發祥地唯上白川窯(即天狗谷)在肥前。有田焼之興起,為日本製陶界帶來**「大革命」。白磁技法為諸地所羨,競相學習,遂全國興起並取代既往之黑物。 自肥前運出的伊万里焼在他地尚無白磁之時幾成磁器代名詞**。於有田,柿右衛門技藝臻熟,白地赤繪享譽全球;法國甚至評為高於明代赤繪,時稱世界第一。當時歐洲尚未自製磁器,故柿右衛門器尤為珍重。鍋島藩亦為進獻幕府而燒造鍋島青瓷等高級品。
技術上,燃料由木轉煤,採用煤窯;並改良匣鉢重積法、棚板積法等裝窯法以提效。色料以自華輸入之呉須(鈷)為主,後普及氧化鈷;惟有田焼重視其釉色調和,鈷多限於部分加合彩料。整個江戶期,有田焼/伊万里焼內外行銷廣闊,成為日本重要出口品。
總之,日本陶瓷自縄文時代之樸拙土器起,經由朝鮮與中國技術導入、茶の湯之繁榮,並以肥前之磁器創製為轉捩,至江戶期發展為享譽國際之高階美術工藝品。