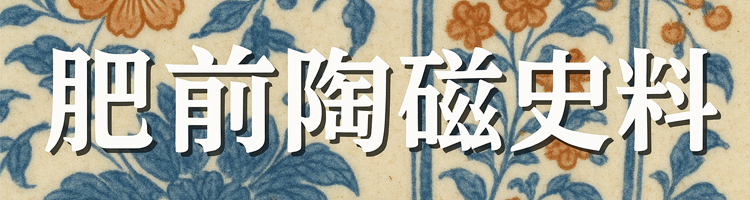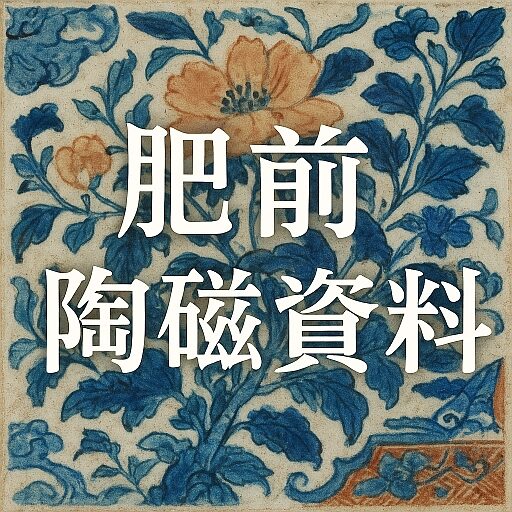『肥前陶磁史考』によると、本書自体が「焼物の何物なるかを説き、…肥前各山の沿革と其焼物の種類を記述せるものにして、…質は我邦陶磁史の中枢を成すものといふ可きである」とされており、肥前地域の陶磁器の歴史が日本の陶磁器全体の歴史において中枢的な位置づけにあると明言されています。
この中枢的な位置づけは、以下の多岐にわたる側面から裏付けられます。
1. 日本の陶器史における最古の起源と発展
- 唐津焼の創始: 我が国における韓系製陶として最も古い歴史を持つのが肥前国上松浦の唐津焼であり、仲哀天皇の時代(9年、西暦200年頃)に神功皇后の三韓出兵の帰路、朝鮮からの陶工が肥前上松浦の港(後の唐津)に帰化して製陶したのが始まりとされています。これは、朝鮮式の製法が日本に定着した最も確かな祖とみなされています。
- 汎称としての「唐津物」: 関東で焼物の汎称が「瀬戸物」と呼ばれるように、関西では「唐津物」と呼ばれ、地方によっては陶器を唐津物、磁器を伊万里物と称することもありました。この広範な呼称は、唐津焼が古くから日本全国に普及し、その名が広く知られていたことを示します。
- 施釉陶の始まり: 斉明天皇の時代には、朝鮮からの陶工が肥前国上松浦の地で高麗風の施釉陶器を製作したとされ、これが日本における施釉陶の始まりとされています。
- 陶工の全国的拡散: 「鬼子嶽崩れ」と呼ばれる出来事により、多くの陶工が全国各地に離散し、その窯技を分布させたことで、例えば美濃国久尻の陶窯改良に貢献した加藤景延のように、他地域の陶業発展に大きな影響を与えました。
2. 日本における磁器生産の発祥地
- 日本初の磁器製造: 有田の上白川窯(天狗谷)は、日本で最初の磁器発祥地であると明記されています。ここでは、李参平が泉山で最良の磁石を発見し、純白の磁器を初めて製造しました。これにより、陶器から磁器への製造転換が図られ、有田山磁器製造の発展は、周辺の陶器山から多くの陶工や商人を惹きつけ、一大工業地となりました。
- 国際的な「伊万里焼」ブランド: 有田内外山の製品だけでなく、大外山の製品まで伊万里市場を経由して搬出されたことから、肥前磁器全体の汎称として伊万里焼の名が世界に知られました。
- 柿右衛門様式の確立: 初代柿右衛門による赤絵の発明と、その卓抜した陶技は、世界の焼物代表国である中国(明代の赤絵の爛熟期とされる万暦以後)においても相当の地位を占め、フランスでは中国明代の赤絵以上と評価され、一時的に柿右衛門製品が世界第一と称されるほどでした。
- 鍋島焼の独自性: 鍋島焼は、他の窯銘がなくとも一見して判別できる独特の様式を持ち、その青磁は当代の首座に位置付けられ、特に砧手における麒麟の大床置や花瓶などの逸品は、宋代の砧手と比較しても遜色ない絶品とされています。これは幕府への献上品や贈答品として珍重されました。
- 三河内焼の精巧な技術: 三河内焼は、透彫りや造花のような繊細な技工が特徴であり、特に「薄手細工のテクニック」は需要が大きく、国際的にも高い評価を受け得る技術と期待されていました。
3. 技術革新と科学的アプローチの導入
- 窯業技術の改良: 窯を母胎とする成品によって焼物の種類を区別することの重要性や、ワゲネルによるコバルト青顔料の使用、石炭窯の試焼(日本における磁器の石炭窯試焼の嚆矢)、棚板積法の改良(天秤積法)など、効率と品質向上に向けた革新的な技術が肥前で発展しました。
- 科学的研究: ワゲネルはコバルトの希釈法や、各種の灰が珪砂を熔化する作用を教え、有田の陶工たちは科学的なアプローチで顔料や釉薬の研究を進めました。また、硬質陶器や耐酸磁器の開発など、製品の機能性向上に向けた研究も活発でした。
- 生産効率の改善: 従来、複数の製造家が共同で窯を使用していたことによる不便さから、西洋式の単独窯や、日本と西洋の構造を折衷した連接窯の改良が提案され、生産効率の向上が図られました。また、業務の分業化の必要性も提唱され、生産性向上に貢献しました。
4. 国際的な交流と貿易の促進
- 貿易の窓口: 肥前地域は古くから朝鮮や中国、インド方面との通商港として栄え、特に唐津は筑前博多と並ぶ九州北面の要衝でした。この交流を通じて、多様な陶器が輸入され、多くの陶工が渡来しました。
- 海外への輸出: 明治時代には、有田焼は海外市場に積極的に輸出され、特に柿右衛門焼はヨーロッパで絶賛されました。また、朝鮮向けの日用品輸出も重要な販路であり、横浜、神戸、長崎を通じて世界各国へ製品が届けられました。万国博覧会への出品も行われ、日本の陶磁器技術を世界に知らしめる役割を果たしました。
これらの要素から、肥前地域の陶磁器の歴史は、日本の陶磁器が陶器から磁器へと発展し、独自の様式を確立し、さらに国際的な産業として成長していく上で、技術、様式、国際交流、産業発展といった多方面で中心的な役割を担ってきたと言えるでしょう。