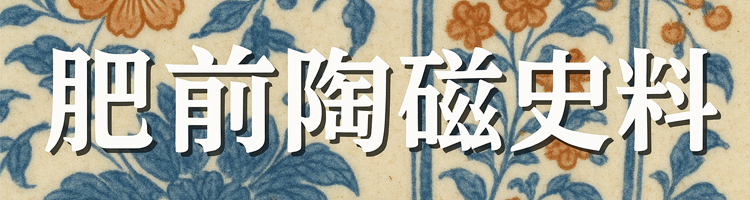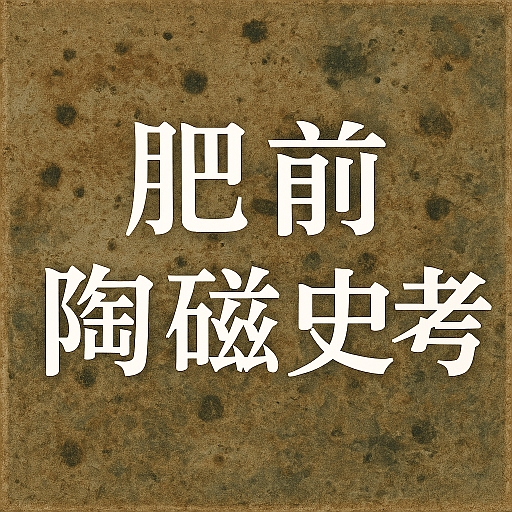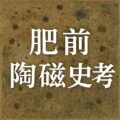【原文】
百濟の高貴を招く
雄略天皇製陶を盛んにすべしの聖旨あり天皇の七年歸化人西漢才伎(テビトは工人の意)歡因知利より、斯技に巧なる者韓土に多き由を奏聞す。天皇仍つて吉備の上道臣弟君に副使として遣はし、百済の陶部の高貴なる者を連れ帰り、河内國桃原(交野郡私市村)に於いて陶器を焼かしめたのである。
忌部焼
同朝の御代に於て備前國須惠村(邑久保郡釜ヶ原?)に於いて忌部焼なる陶器が創始された。此邊りは元野見宿禰が出雲の土師を招きて、埴輪を造らしめし土師鄉である。
贄の土師部
同朝の十七年三月二日、土師連等に詔して清器を進め造らしむ。是に於いて連の祖吾筍は攝津國來狹々村、山脊國内村(宇治)、同國俯見村(伏見) 伊勢國藤方村其他丹波、但馬、因おはにへ幡の陶工をして御贄の御清器を作り私民部を進む。これ贄の土師部の始めである。(贄は新物を新物を神にも人にも饗し自らも食する事である)
曲水宴の盤器
顕宗天皇の元年三月三日、始めて曲水の宴(御溝水に羽觴を流して詩歌を作るの興、めぐりみづのとよのあかり)を設け給ふや、瓜を酒魚として盤に盛り以て宴席に供せらるゝとあるは、既に此時皿を御器に用ひ給しことが證せらる。
蘇我氏專横時代佛教の渡来
欽明天皇の十三年十月十三日、百済の聖明王より佛教經論の贈献と共に、其式典に用ふ可き陶器と、建築用瓦の必要が生するに至った。
瓦工を献し奉る
崇峻天皇の元年百濟の威徳王より、佛寺堂塔建立の用に供するため、寺工―太郎未太文賈古子、鑢盤博士―將德白味淳、瓦博士―摩奈文奴陽貴文、陵貴文、昔麻帝彌、及び工―白加等を献じった。之より本邦に於て始めて瓦を焼きて屋根を葺くことが創められた。蓋し此頃より希臘藝術の模様が印度を経て支那に入り六朝美術となりしものが、又朝鮮を経て我邦へ輸入されしものであらう。
【現代語訳】
雄略天皇七年、天皇は陶業を盛んにせよとの詔を出された。帰化人の西漢才伎(テビト=工人の意)の歓因知利が、朝鮮には陶芸に優れた者が多いと奏上した。そこで天皇は吉備の上道臣弟君を副使として派遣し、百済の陶部に属する高位の陶工を伴って帰国させ、河内国桃原(交野郡私市村)で陶器を焼かせた。
同じ雄略天皇の御代、備前国須恵村(邑久郡釜ヶ原か)で「忌部焼」と呼ばれる陶器が創始された。この地はもとより野見宿禰が出雲から土師を招いて埴輪を作らせた土師郷である。
また天皇十七年三月二日には、土師連らに清浄な器を奉るよう詔があり、連の祖・吾筍は摂津国来狭々村や山背国宇治の内村、同国伏見の俯見村、伊勢国藤方村、さらに丹波・但馬・因幡・播磨の陶工を動員して御贄の清器を作り、朝廷に献上した。これが「贄の土師部」の始まりである。(贄とは、新しい収穫物などを神や人に饗応し、自らも食することである。)
顕宗天皇元年三月三日、初めて「曲水の宴」が催され、流れる水に杯を浮かべ詩歌を作った。その際、瓜を肴として盤に盛り宴席に供したと記録にあり、この時すでに「皿」が器として用いられていたことが分かる。
欽明天皇十三年十月十三日、百済の聖明王から仏教経典が贈られ、それとともに儀式で用いる陶器や、寺院建築のための瓦が必要とされるようになった。
崇峻天皇元年、百済の威徳王は日本に仏寺堂塔建立のための人材を献じた。寺工の太郎未太文賈古子、鑢盤博士の將德白味淳、瓦博士の摩奈文奴陽貴文・陵貴文・昔麻帝彌、さらに工人の白加らである。これによって日本で初めて瓦が焼かれ、屋根葺きに用いられるようになった。この頃から、ギリシャ美術の意匠がインドを経て中国に入り六朝美術を形成し、それがさらに朝鮮を経由して日本にも伝わったと考えられる。
【英語訳】
Inviting Potters from Baekje
In the seventh year of Emperor Yūryaku, the emperor decreed the promotion of pottery production. Kan In Chiri, a naturalized craftsman of the Seikan Saigi clan (the term tebito meaning “artisan”), reported that many skilled potters existed in Korea. The emperor then dispatched Kamimichi no Omi Otogimi of Kibi as a deputy envoy, who returned with a distinguished potter from the pottery bureau of Baekje. They were made to produce pottery in Momohara, Kawachi Province (now Kisaichi Village, Katano District).
During the same reign, pottery known as Imibe ware was first produced in Sue village, Bizen Province (likely Kamagahara in Oku District). This region had long been the settlement of the Haji clan, where Nomi no Sukune had once invited potters from Izumo to make haniwa clay figures.
On March 2, the seventeenth year of Emperor Yūryaku, an imperial edict ordered the Haji clan to produce pure vessels as offerings. Their ancestor, Wasun, mobilized potters from villages in Settsu Province (Kurasasa), Yamashiro Province (Uji and Fushimi), Ise Province (Fujikata), and from Tanba, Tajima, Inaba, and Harima, to craft ritual vessels for offerings. This marked the beginning of the “Haji potters of the offerings.” (The term nie refers to presenting the first produce to both gods and men while partaking of it oneself.)
In the first year of Emperor Kensō (March 3), the “Kyokusui Banquet” was held for the first time. Cups were floated along a stream and poetry composed. Records state that melons and fish were served on plates, showing that dishes (sara) were already in use as tableware.
In the thirteenth year of Emperor Kinmei (October 13), King Seong of Baekje presented Buddhist scriptures to Japan. Alongside these, ceramic vessels for rituals and roof tiles for temple architecture became necessary.
In the first year of Emperor Sushun, King Wideok of Baekje presented craftsmen for the construction of temples and pagodas in Japan. These included the temple artisan Taromi-no-tomonokokoshi, the master of grinding stones Jōtoku Hakumishun, tile masters Mana Monnu Yōkibumi, Ryōkibumi, and Sekimateimi, as well as the craftsman Shiraka. From this time, roof tiles were first fired and used for Japanese buildings. Around this period, Greco-Roman artistic motifs had traveled via India to China, becoming part of Six Dynasties art, and were then transmitted through Korea into Japan.
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】
雄略天皇七年,下诏兴盛陶业。归化人西汉才伎(“テビト”意为工匠)的欢因知利上奏称,朝鲜有许多善于制陶之人。于是天皇派遣吉备的上道臣弟君为副使,带回百济陶部的高位陶工,在河内国桃原(交野郡私市村)烧制陶器。
同一时期,在备前国须惠村(邑久郡釜ヶ原?)创制了“忌部烧”。此地原为野见宿祢从出云召来土师制作埴轮的土师乡。
天皇十七年三月二日,又诏令土师氏制作清器进献。其祖吾筍动员摄津国来狭々村、山城国宇治内村、同国伏见俯见村、伊势国藤方村,以及丹波、但马、因幡、播磨等地陶工,制作御贽清器进献朝廷。这是“贽之土师部”的开端。(“贽”指将新收之物奉献神明、款待人,并自食。)
顕宗天皇元年三月三日,首次举办“曲水宴”,在流水中浮杯作诗。当时以瓜、鱼盛于盘供宴,证明此时“皿”已被用作器皿。
欽明天皇十三年十月十三日,百济圣明王献上佛经,同时需要仪式用陶器与寺院建筑的瓦。
崇峻天皇元年,百济威德王献上工匠以建佛寺堂塔。包括寺工太郎未太文贾古子、磨盘博士将德白味淳、瓦博士摩奈文奴阳贵文、陵贵文、昔麻帝弥,以及工人白加等。由此日本首次烧制瓦片,用于屋顶覆盖。据说此时起,希腊艺术的图样经印度传入中国,形成六朝美术,再经朝鲜传至日本。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】
雄略天皇七年,下詔興盛陶業。歸化人西漢才伎(「テビト」意為工匠)的歡因知利上奏稱,朝鮮有許多善於製陶之人。於是天皇派遣吉備的上道臣弟君為副使,帶回百濟陶部的高位陶工,在河內國桃原(交野郡私市村)燒製陶器。
同一時期,在備前國須惠村(邑久郡釜ヶ原?)創製了「忌部燒」。此地原為野見宿祢從出雲召來土師製作埴輪的土師鄉。
天皇十七年三月二日,又詔令土師氏製作清器進獻。其祖吾筍動員攝津國來狹々村、山城國宇治內村、同國伏見俯見村、伊勢國藤方村,以及丹波、但馬、因幡、播磨等地陶工,製作御贄清器進獻朝廷。這是「贄之土師部」的開端。(「贄」指將新收之物奉獻神明、款待人,並自食。)
顯宗天皇元年三月三日,首次舉辦「曲水宴」,在流水中浮杯作詩。當時以瓜、魚盛於盤供宴,證明此時「皿」已被用作器皿。
欽明天皇十三年十月十三日,百濟聖明王獻上佛經,同時需要儀式用陶器與寺院建築的瓦。
崇峻天皇元年,百濟威德王獻上工匠以建佛寺堂塔。包括寺工太郎未太文賈古子、磨盤博士將德白味淳、瓦博士摩奈文奴陽貴文、陵貴文、昔麻帝彌,以及工人白加等。由此日本首次燒製瓦片,用於屋頂覆蓋。據說此時起,希臘藝術的圖樣經印度傳入中國,形成六朝美術,再經朝鮮傳至日本。
【中国語訳(英語から簡体字)】
雄略天皇七年,下令促进陶业发展。归化工匠西汉才伎的欢因知利报告称,朝鲜有许多精于制陶的人。于是派吉备的上道臣弟君为副使,带回百济陶部的高级陶工,在河内国桃原烧陶。
同一时期,在备前国须惠村创制了“忌部烧”。此地原为野见宿祢召来出云土师制作埴轮之地。
天皇十七年三月二日,下诏土师氏进献洁净之器。吾筍动员多地陶工制御贽清器,奉献朝廷,这成为“贽之土师部”的开端。
顕宗天皇元年三月三日,首次举办“曲水宴”,以盘盛瓜鱼供宴,显示皿已为食器。
欽明天皇十三年十月十三日,百济圣明王献佛经,并需陶器与寺瓦。
崇峻天皇元年,百济威德王献工匠修寺塔,日本始制瓦葺屋。希腊艺术经印度入华为六朝美术,再传朝鲜入日。
【中国語訳(英語から繁體字)】
雄略天皇七年,下令促進陶業發展。歸化工匠西漢才伎的歡因知利報告稱,朝鮮有許多精於製陶的人。於是派吉備的上道臣弟君為副使,帶回百濟陶部的高級陶工,在河內國桃原燒陶。
同一時期,在備前國須惠村創製了「忌部燒」。此地原為野見宿祢召來出雲土師製作埴輪之地。
天皇十七年三月二日,下詔土師氏進獻潔淨之器。吾筍動員多地陶工製御贄清器,奉獻朝廷,這成為「贄之土師部」的開端。
顯宗天皇元年三月三日,首次舉辦「曲水宴」,以盤盛瓜魚供宴,顯示皿已為食器。
欽明天皇十三年十月十三日,百濟聖明王獻佛經,並需陶器與寺瓦。
崇峻天皇元年,百濟威德王獻工匠修寺塔,日本始製瓦葺屋。希臘藝術經印度入華為六朝美術,再傳朝鮮入日。