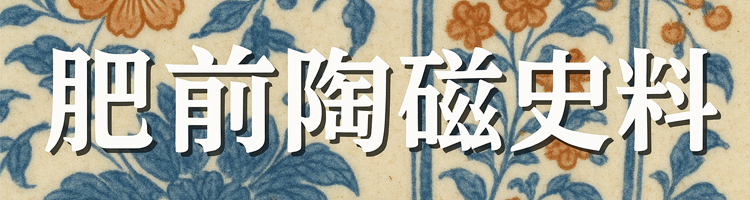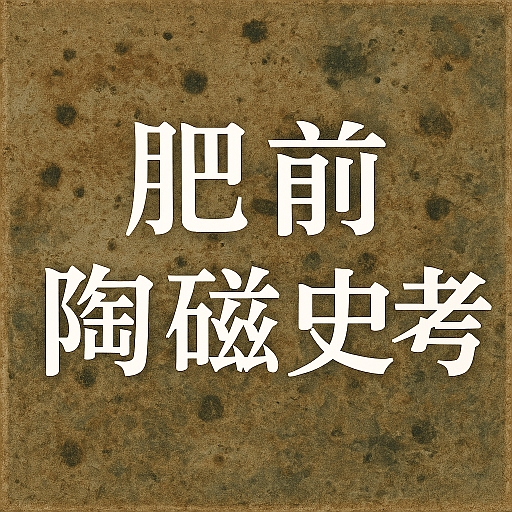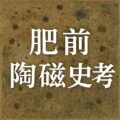【原文】
遣唐使始まる
推古天皇の十五年七月三日、大禮小野妹子を隋に派遣されしが、爾來我邦より遺唐使なる者の一行屢彼地に渡航することゝなり、之より又製陶の發展を促かす媒介となったのである。
法政改革時代筥陶司を置く
孝徳天皇の大化改新の際に於いて、宮廷の大膳職に四寮十三司の制を設けられ、其中に筥陶司を置きて土師の官職を廢し、土師の連の督する陶工を以つて之が所管となし、土工司を置きてを造ることを掌らしめしが、此革新に於いて土師の世襲業を解廢せられしは、陶史上特筆すべき事柄である。
高麗焼と布目瓦
齊明天皇の御代に於いて、韓土の陶工肥前國上松浦の地に渡来して高麗焼を創製した。之より此地方を陶村させらる。蓋し仲哀天皇の時唐津焼の始と稱するものは、未だ無釉陶なりしも、此時より始めて施釉陶か我邦に於いて製作されし稱せらる。又其頃肥前國に於いて瓦焼が始められしが、それは彼の布目なるべしといはれてゐる。
陶工の戸を定む
文武天皇の大寶元年、筥陶司の職制を正一人、佑一人、令史一人、使部六人、直十一人を爲し、陶工人の戸を定められた。(筥戸は陶工にて、泥工即ち瓦工と區別せし名稀である)
奈良朝時代=行基敷瓦を焼かしむ
元明天皇の和銅四年、僧行基は堂宇建立に用ふるため、近江國瀬田に於いて敷瓦を焼かしめたのである。(和泉三才圖會には、之より先天智天皇の朝和泉國大鳥郡陶村に於いて、行基法を教へて陶器を焼かしむとあり)
豊磨の留學
聖武天皇の神亀元年七月、土師の豊磨韓土の陶法を學ぶ可く彼地に派遣さることなつた。蓋し土師の外国に留學せしは此時を以つて始めと稱せらる。又同年十一月八日太政官の奏請により、宮屋を葺くに瓦を以てし、塗るに丹を以てすることを許された。
唐三彩の陶器を作る
同朝の天平六年奈良の禁廷に於いて、河内國交野の土を探りて原料とし、唐三彩(交趾焼の如き鉛釉土器なるべし)の陶器を製作せしめられた。
【現代語訳】
推古天皇十五年七月三日、大礼使として小野妹子が隋に派遣された。これ以降、日本から遣唐使がたびたび渡航するようになり、これが陶芸の発展を促す大きな契機となった。
孝徳天皇の大化改新の際、宮廷の大膳職の下に四寮十三司の制度が設けられ、その中に筥陶司が置かれた。これにより土師氏の官職は廃止され、土師氏が統率していた陶工たちが筥陶司の管轄に組み込まれた。また土工司を設けて瓦の製作を掌らせた。この改革で土師氏の世襲的地位が失われたことは、陶業史上特筆すべきことである。
斉明天皇の御代には、朝鮮から肥前国上松浦に陶工が渡来し「高麗焼」が始められた。これによってこの地は陶村となった。仲哀天皇の時代に唐津焼の起源とされるものはまだ無釉陶であったが、この時から初めて施釉陶が日本で製作されたと伝わる。またこの頃、肥前国で瓦の製作も始まり、それが布目瓦であったとされている。
文武天皇大宝元年には、筥陶司の職制として正一人・佑一人・令史一人・使部六人・直十一人が定められ、陶工の戸籍が整備された。(「筥戸」は陶工を指す名で、泥工=瓦工とは区別された。)
元明天皇和銅四年、僧・行基は堂宇建築のため、近江国瀬田で敷瓦を焼かせた。(『和泉三才図会』には、これ以前に天智天皇の時代、和泉国大鳥郡陶村で行基が陶法を教え、陶器を焼かせたと記されている。)
聖武天皇神亀元年七月、土師氏の豊磨が朝鮮の陶法を学ぶため派遣された。日本の陶工が外国に留学した最初の事例とされる。また同年十一月八日には、太政官の奏請により、宮殿の屋根を瓦で葺き、丹で塗ることが許可された。
同朝天平六年、奈良の禁廷において、河内国交野の土を原料として唐三彩(おそらく交趾焼に似た鉛釉陶器)が製作された。
【英語訳】
The Beginning of Missions to China
On July 3, in the fifteenth year of Empress Suiko, Ono no Imoko was dispatched to the Sui dynasty as an envoy. From then on, Japanese envoys to China (Kentōshi) traveled frequently, becoming a major factor in the advancement of Japanese ceramics.
During Emperor Kōtoku’s Taika Reforms, the court established the Office of the Great Kitchen with four bureaus and thirteen offices, including the Hakusei no Tsukasa (Office of Pottery). This abolished the hereditary Haji clan’s official role, bringing the potters under direct government control. Another office, the Dobu-shi, was established to oversee roof-tile making. The removal of the Haji clan’s hereditary monopoly was a significant milestone in ceramic history.
In the reign of Empress Saimei, Korean potters came to Kamimatsuura in Hizen Province and created Koma ware. This turned the region into a pottery village. Whereas the early Karatsu ware of Emperor Chūai’s era was unglazed, it was during this time that glazed pottery was first produced in Japan. Roof tile production also began in Hizen, believed to be the origin of patterned nunome-gawara tiles.
In the first year of Emperor Monmu’s Taihō era, the Office of Pottery was staffed with one chief, one assistant, one recorder, six functionaries, and eleven clerks, and households of potters were formally registered. (Hakuto referred specifically to potters, distinct from dobu or tile makers.)
In the fourth year of Empress Genmei’s Wadō era, the monk Gyōki produced paving tiles in Seta, Ōmi Province, for temple construction. (The Izumi Sanzai Zue records that even earlier, during Emperor Tenchi’s reign, Gyōki taught ceramic methods and produced pottery in Tōson, Ōtori District, Izumi Province.)
In the first year of Emperor Shōmu’s Jinki era (July), the Haji potter Toyoma was dispatched to Korea to study ceramic techniques, the first known instance of a Japanese potter studying abroad. Later that year, on November 8, the Dajōkan approved the use of roof tiles and cinnabar paint for palace buildings.
In the sixth year of the Tenpyō era, in the imperial palace at Nara, pottery was produced using clay from Katano in Kawachi Province. This included Tang sancai (likely lead-glazed pottery similar to Jiaozhi ware).
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】
推古天皇十五年七月三日,小野妹子被派遣至隋朝。此后,日本遣唐使频繁出航,成为推动陶艺发展的重要媒介。
孝德天皇大化改新时,宫廷设立大膳职下的“四寮十三司”制度,其中设有“筥陶司”,废除了土师氏的官职,将其管辖的陶工纳入国家管理。同时设“土工司”专管瓦的制造。这一改革使土师氏的世袭地位被打破,是陶业史上重要的转折点。
齐明天皇时期,朝鲜陶工渡来肥前国上松浦,创制“高丽烧”,使此地成为陶村。仲哀天皇时期的唐津烧尚属无釉陶,而此时开始出现施釉陶。肥前国也开始制瓦,被认为是布目瓦的起源。
文武天皇大宝元年,筥陶司的官制确立:正一人、佑一人、令史一人、使部六人、直十一人,并正式登记陶工户籍。(“筥户”专指陶工,与泥工=瓦工不同。)
元明天皇和铜四年,僧行基在近江国濑田烧制铺地瓦,用于佛堂建设。(《和泉三才图会》记载更早在天智天皇时期,行基在和泉国大鸟郡陶村传授陶法并制陶。)
圣武天皇神龟元年七月,土师的丰磨被派往朝鲜学习陶法,这是日本陶工首次留学海外。同年十一月八日,太政官准许宫殿屋顶用瓦覆盖,并以丹涂饰。
天平六年,奈良禁廷以河内国交野的土为原料,制作唐三彩(类似交趾烧的铅釉陶器)。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】
推古天皇十五年七月三日,小野妹子被派遣至隋朝。此後,日本遣唐使頻繁出航,成為推動陶藝發展的重要媒介。
孝德天皇大化改新時,宮廷設立大膳職下的「四寮十三司」制度,其中設有「筥陶司」,廢除了土師氏的官職,將其管轄的陶工納入國家管理。同時設「土工司」專管瓦的製造。這一改革使土師氏的世襲地位被打破,是陶業史上重要的轉折點。
齊明天皇時期,朝鮮陶工渡來肥前國上松浦,創製「高麗燒」,使此地成為陶村。仲哀天皇時期的唐津燒尚屬無釉陶,而此時開始出現施釉陶。肥前國也開始製瓦,被認為是布目瓦的起源。
文武天皇大寶元年,筥陶司的官制確立:正一人、佑一人、令史一人、使部六人、直十一人,並正式登記陶工戶籍。(「筥戶」專指陶工,與泥工=瓦工不同。)
元明天皇和銅四年,僧行基在近江國瀨田燒製鋪地瓦,用於佛堂建設。(《和泉三才圖會》記載更早在天智天皇時期,行基在和泉國大鳥郡陶村傳授陶法並製陶。)
聖武天皇神龜元年七月,土師的豐磨被派往朝鮮學習陶法,這是日本陶工首次留學海外。同年十一月八日,太政官准許宮殿屋頂用瓦覆蓋,並以丹塗飾。
天平六年,奈良禁廷以河內國交野的土為原料,製作唐三彩(類似交趾燒的鉛釉陶器)。
【中国語訳(英語から簡体字)】
推古天皇十五年七月三日,小野妹子被派往隋朝。自此以后,日本遣唐使频繁航行,推动了陶艺的发展。
孝德天皇大化改新时,宫廷设“大膳职”下“四寮十三司”,其中有“筥陶司”,废除土师氏的世袭职务,将陶工纳入国家管理。同时设“土工司”专管瓦片生产。这标志着陶业史的重要改革。
齐明天皇时期,朝鲜陶工渡来肥前上松浦,创制“高丽烧”,首次在日本生产施釉陶。肥前国同时开始制瓦,被认为是布目瓦的起源。
文武天皇大宝元年,设官制并正式登记陶工户籍。
元明天皇和铜四年,僧行基在近江国濑田制铺地瓦。
圣武天皇神龟元年七月,土师的丰磨被派往朝鲜学陶,这是日本陶工首次留学。十一月八日,太政官准许宫殿用瓦葺屋并以丹涂饰。
天平六年,奈良宫廷以河内国交野之土制“唐三彩”。
【中国語訳(英語から繁體字)】
推古天皇十五年七月三日,小野妹子被派往隋朝。自此以後,日本遣唐使頻繁航行,推動了陶藝的發展。
孝德天皇大化改新時,宮廷設「大膳職」下「四寮十三司」,其中有「筥陶司」,廢除土師氏的世襲職務,將陶工納入國家管理。同時設「土工司」專管瓦片生產。這標誌著陶業史的重要改革。
齊明天皇時期,朝鮮陶工渡來肥前上松浦,創製「高麗燒」,首次在日本生產施釉陶。肥前國同時開始製瓦,被認為是布目瓦的起源。
文武天皇大寶元年,設官制並正式登記陶工戶籍。
元明天皇和銅四年,僧行基在近江國瀨田製鋪地瓦。
聖武天皇神龜元年七月,土師的豐磨被派往朝鮮學陶,這是日本陶工首次留學。十一月八日,太政官准許宮殿用瓦葺屋並以丹塗飾。
天平六年,奈良宮廷以河內國交野之土製「唐三彩」。