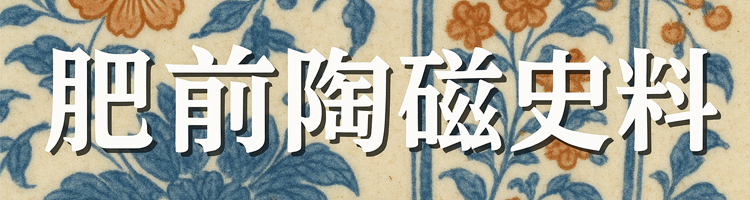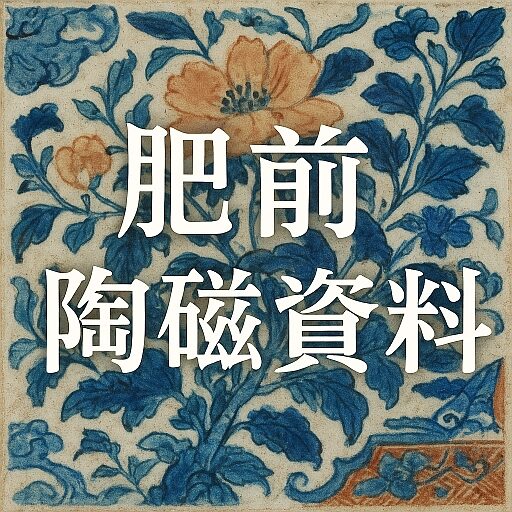日本の陶磁器の発展は、その分類方法と、土器から磁器へと進化していく過程において、様々な技術革新と文化的交流が深く関わっています。
1. 日本の陶磁器の分類
日本の陶磁器は、その製法、原料、焼成温度、性質によって多様に分類されています。
- 焼物の本体: 科学的には「珪酸塩の熟化されたる結晶物体」と説明され、酸化金属と硝子質の共同焼成によって色彩と可塑性を備えた耐久性のある物体と定義されています。
- 陶器の名称: 元来「須惠母乃(スヱノウツハモノ)」と呼ばれ、「据える物」の意義から起こったとされています。後に、高台が付けられ据えられる器となり、現在では「土器」「炻器」「磁器」を含む全ての焼物を総括的に「陶器」と呼ぶようになりました。
現代の分類では、焼物は大きく以下の5種類に分けられます:
- 土器(アーセンウエア):
- 人類の元始時代から造られた最も簡素な器で、科学的には一番劣等の部類に属します。
- 粘土のみを焼成するため、脆弱で気孔が多く、水分を夥しく吸収します。
- 焼成火度は通常摂氏400〜700度程度とされ、施釉されないものと施釉されたものがあります。弥生式土器や埴輪、楽焼などがこの分類に属します。
- 陶器(フハイヤンス又はポッタリー):
- 磁器に比べて粘土分が多く、長石分が少ないのが特徴です。
- 叩くと木のような音を発する粗質なもので、焼成火度は摂氏900度内外から1200度に達するものもあります。
- 胎土は暗色と白色の数種があり、いずれも水分を吸収します。肥前の唐津焼や近江の信楽焼などが代表的です。
- 硬質陶器(アイアン・ストーン・チャイナ又はハードポッタリー):
- 磁土、長石、石英を適切に使用し、磁器と反対に素焼きの火度を1200度程度の高度で焼き、軟釉を施して1000度程度で本焼きしたものです。
- 色は不透明な乳白色を呈し、気孔質で吸水性があります。近代に創造された製法とされます。
- 炻器(ストーン・ウェア):
- 多く粘土に砂を混ぜて製作されたもので、焼成火度は摂氏1000度から1200度です。
- 磁器と同様に堅く緻密で、量も重く、叩くと石のような音を発し、全く水分を吸収しません。
- 粘土中の鉄分のため、多く淡褐色や黝青色を帯びますが、無釉物には朱泥、白泥、梨皮泥などがあります。尾張の常滑焼や備前の伊部焼などがこれに属します。
- 磁器(ボースレイン):
- 焼物の中で最も進歩した製品とされ、磁土、長石、珪石(石英)を主成分として形成されます。
- 一旦摂氏700〜1000度程度で素焼きし、これに彩書や釉薬を施し、さらに1250度から1300度以上で本焼きされた珪酸質焼物です。
- 緻密で堅牢な素地は水分を吸収せず、叩くと金属のような清音を発します。肥前の有田焼、三河内焼、波佐見焼などが代表的な産地です。
また、これらを軟陶と硬陶に大別することもあります。軟陶は土器や陶器類、硬陶は炻器や磁器が該当します。分類の決め手は、原料ではなく、焼き上がった物が土のようか石のようか、そして水分吸収の有無、つまり無気孔質か否かによって区別されます。磁器だけは、その純白の透明質と素地の堅牢さから、誰でも一見して判別できるとされています。
さらに、近代の陶器の種類として「半磁器」という珪酸質焼物も登場しています。これは長石分が少なく粘土を主成分とし、透明を防ぐため暗色が多く用いられました。主に貿易品として軽量化と、不透明にすることで関税を少なくする目的で製作されたようです。
2. 土器から磁器への進化
日本の陶磁器は、原始的な土器から洗練された磁器へと、数千年にわたる技術革新と文化的交流を経て進化してきました。
1. 原始土器の製作と初期の焼成技術
- 起源: 人類が土器を作り始めたのは、新石器時代に至って漸く発見されたもので、今から約2万5千年〜1万2千年以前のこととされています。
- 初期の製法: 最初は土を水でこねて手捻りで形を作り、天日で乾燥させていました。偶然火に焼かれたことで器が堅くなることを発見し、好奇心から様々な工夫が凝らされました。
- 初期の焼成: 始めは開放的な環境で冠せた薪の熱を用いて焼き固められたと推考されます。弥生式土器などは、地上に据え、砂で覆い隠し、四方から燃料を積み重ねて焼き上げられたと言われています。地面を掘り窪め、周囲に石を築いて焼く方法も考えられますが、陶窯を知らない時代の粗製品であり、火度が弱く破損しやすかったとされます。
2. 窯と釉薬の導入
- 窯の発展:
- 後代になると、斜面に細長く穴を掘り、練土でアーチ形に構造された「窖窯(あながま)」が工夫されました。これが焼物窯の祖先とされています。
- やがて室内を数室に仕切った「長窯」や、丸窯を連鎖させた「登窯(のぼりがま)」が構成され、後年には「竪窯」や「トンネル窯」など多様な様式が築造されました。
- 釉薬の創始:
- 器に液体の吸収を防ぎ、滑らかな外被を与える「釉薬(わくすり)」が施されるまでには長い年月を要しました。
- 最初の発見は偶然で、窯に入れた器に窯内の降灰が付着し、それが高熱で焼成された結果、器の表面に化学的変化が起こりガラス状の被覆物が生じたことによります。この偶然の出来事から、灰を混ぜて釉薬を施す方法が創見されました。
3. 朝鮮半島からの製陶技術の導入(唐津焼の発展)
- 唐津焼の始まり: 仲哀天皇の時代(西暦200年頃)、神功皇后の三韓出兵からの帰還の際、従ってきた韓土の陶工が肥前国上松浦の港(後の唐津)で製陶を始めたことが、後年の「唐津焼」の起源とされています。これは朝鮮式の製法を日本に定着させた「最も精確なる始祖」と評されています。
- 施釉陶器の始まり: 斉明天皇の御代には、韓土の陶工が肥前国上松浦の地で「高麗焼」を創製し、これにより日本で初めて施釉陶器が製作され始めたとされています。初期の唐津焼は無釉陶器でしたが、この時期に施釉技術が導入されたと見られています。
- 作風の多様化: 朝鮮陶工の渡来により、轆轤の使用など、成形技術も進化しました。唐津焼は「朝鮮式の唐津風」という陶系を確立し、多様な釉薬や作風が見られます。
4. 磁器製造の開始(有田焼の発祥)
- 磁石の発見と製造の成功: 日本の製陶界に大きな革命をもたらしたのは、元和年間(1615〜1624年頃)、朝鮮から渡来した陶工李参平(金ヶ江三兵衛)が有田郷乱橋に来て泉山で最良の磁石(陶石)を発見し、白川に移住して初めて純白な磁器を製出したことでした。これは「我日本に於ける最初の磁器發祥地」とされ、日本の磁器史における画期的な出来事でした。
- 初期の磁器製造: 最初は良質の陶土(くろもの土)を探していた李参平が、偶然泉山で大磁石鉱に遭遇したと考えられています。当初は焼成技術の未熟さから色相が不純なものも多かったですが、徐々に良質の採石と焼成法の練達により、今日の有田焼の基礎が築かれました。
- 生活様式への影響: 土器や陶器が吸水性や衛生面での課題を抱えていたのに対し、清潔で衛生的、かつ堅緻な白磁の登場は、日用品としての需要を高め、大内の御食器にも採用されるなど、日本の食文化と生活に大きな変革をもたらしました。
5. 様式と顔料の革新(赤絵と錦手の発展)
- 上絵付の発展: 磁器は高温で焼成されるため、釉下では発色しにくい彩料が多く、釉色の単調さがありました。このため、一度焼成された器に色を補う「上絵付(赤絵付、錦付)」が発展しました。
- 柿右衛門様式: 喜三右衛門は、従来の白磁製造に新たな工夫を加え、「濁し手焼(乳白手)」を創作しました。これは厚い釉薬で青みを帯びる古伊万里とは異なり、薄い釉薬で乳白色を呈する純白な磁器でした。正保3年(1646年)には柿右衛門が錦彩磁器の創製を企図し、苦心の末に発明に至ったとされます。彼の赤絵技術は「彌々圓熟の境に達した」と評され、中国明代の赤絵以上とされ、フランスで「世界第一」と称されるほど高い国際評価を得ました。
- 顔料の導入と改良:
- 赤彩料のフラックスとして中国から「唐石」や「唐土」(鉛丹)が導入されました。また、日の岡石(京都産珪酸)が焼成時の氷裂防止に用いられました。
- 青花顔料としては中国呉洲(酸化コバルト)が輸入されました。明治時代にはドイツ人化学者ワゲネルが酸化コバルト顔料の有効性を発見し、希釈法を指導したことで、品質の安定と大量生産が可能となりました。
- 黄色、薄墨色、紅色、緋色など、多様な色彩料の研究も進められました。
6. 近代化と産業化への取り組み
- 窯の改良: 古代の窖窯から登窯への進化に加え、明治時代にはドイツ人ワゲネルによる石炭窯の試焼が行われ、その有用性が示されました。低価格生産の観点から石炭窯は普及し、窯の構造も二層や三層式にすることで、素焼きと本焼きを同時に行う効率的な方法が考案されました。また、電気熱を用いた「鋼鉄電熱窯」も登場し、従来の700度から600度での焼成が可能になり、彩釉の光沢が増しました。
- 積込技術の革新: 辰十によって、積込効率を大幅に向上させる「天秤積法」が考案され、これは窯業史上特筆すべき功績とされています。その後、深海市郎によってさらに改良された「伽藍積」も考案されました。
- 成形技術の進化: 手捻りから轆轤、押型、石膏型込法へと発展し、近年では「泥漿溶作法」が薄壁で平均した厚みの小口物製作に広く応用されています。
- 分業制の提唱: ワゲネルは、磁器製造における経済的分業の重要性を説き、各工程を専門化することで事業の発展と進歩を促すことを提言しました。
- 特殊製品の開発: 耐酸磁器、碍子、磁製ローラーといった化学的・工業的特許品の研究・製造が進み、浴槽用タイルや硬質タイル、便器などの建築用陶磁器も生産されるようになりました。
これらの技術革新と、朝鮮半島、中国、ヨーロッパなどとの多様な文化的交流が複合的に作用し、肥前陶磁器は「我邦陶磁史の中枢」を成すと言われるほどに発展を遂げてきました。