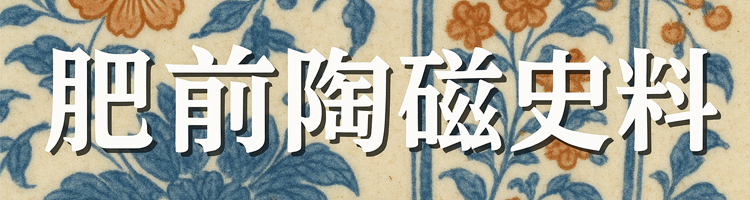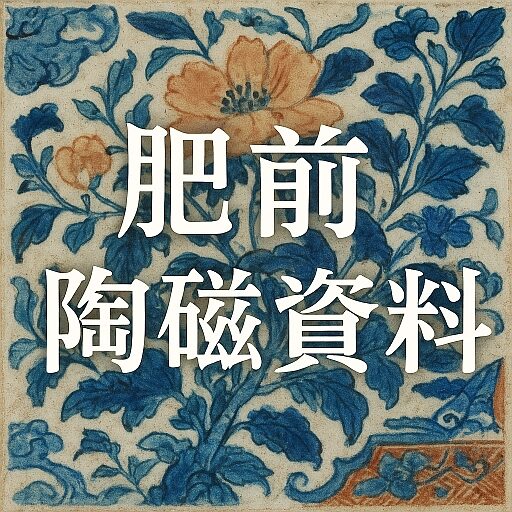肥前地域、特に唐津と有田における陶磁器の歴史は、日本の陶磁史全体において中枢的な位置づけを占めています。これは、その起源から発展、技術革新、そして国際的な影響力に至るまで、日本の陶磁器の歩みに深く関わってきたためです。
肥前陶磁器の日本の陶磁史における位置づけは、以下の点にまとめられます。
- 朝鮮半島からの技術導入の始祖としての唐津焼
- 日本の陶磁器の歴史において、朝鮮半島の製陶技術が本格的に導入されたのは、仲哀天皇9年(神功皇后の三韓出兵時)に帰化した韓土の陶工によって、肥前国上松浦の港(後の唐津)で製陶が始められた「唐津焼」が「朝鮮式の製法を我邦に扶植せし最も精確なる始祖」とされています。これにより、肥前地域は朝鮮半島からの技術・様式の主要な入口となりました。
- 関西地方では、陶器全般を「唐津物」と呼ぶほど、その影響は広範でした。このことは、唐津焼が単なる一地方の焼き物ではなく、当時の日本における陶器の代表的存在として広く認識されていたことを示しています。
- 高麗風の施釉陶器が日本で製作され始めたのも、斉明天皇の御代に韓土の陶工が肥前国上松浦の地で「高麗焼」を創製した時からとされています。
- 日本における磁器生産の発祥地としての有田焼
- 日本の陶磁器史における最大の転換点の一つは、磁器の国産化です。肥前の上白川窯、すなわち天狗谷が「我日本に於ける最初の磁器發祥地」であると明確に記されています。これは、陶祖・李参平(三兵衛)が元和年間に有田郷乱橋に来て泉山で最良の磁石を発見し、白川に移住して初めて純白な磁器を製出したことによるとされています。
- この磁器製造の成功は、「我製陶界に大いなる革命であつた」と評価されており、有田の白磁生産が他の陶山に大きな影響を与え、各地で磁器製作への転換が試みられました。
- 有田焼の創業地は、当初、黒牟田や南川原地方が陶器を焼く古窯地として栄え、その後小樽や岩谷川内などが韓人による最初の磁器開窯地であったとされています。
- 独自様式の確立と国際的な評価
- 有田焼は、単に磁器を国産化しただけでなく、その後の発展において世界的に高い評価を受ける独自の様式を確立しました。
- 柿右衛門様式:初代柿右衛門の赤絵技術は「彌々圓熟の境に達した」とされ、その作品は中国の爛熟期における赤絵以上に評価され、フランスでは「世界第一」と称されました。これは、日本の陶磁器が国際市場で最高峰の評価を得た事例であり、肥前がその中心であったことを示しています。
- 色鍋島:鍋島焼は「一見して、判明さる獨得の超越」を示しており、その青磁は「當代の首座に位し」幕府への献上品として製作されるなど、極めて貴重なものとされました。
- これらの様式は、支那(中国)や朝鮮、欧州の美術、更紗模様などの影響を巧みに取り入れながら、日本独自の美的感覚で発展しました。
- 有田焼は、単に磁器を国産化しただけでなく、その後の発展において世界的に高い評価を受ける独自の様式を確立しました。
- 技術革新と産業的発展
- 肥前地域は、製陶技術の進歩においても中心的役割を果たしました。初期の有田焼における「濁し手焼(乳白手)」の創作 や、顔料としての酸化コバルト(呉洲)の導入と利用法の研究、さらには石炭窯の導入 や機械化 など、近代的な製陶技術の導入と改良が積極的に行われました。
- 明治時代以降には、製陶業の産業化と輸出振興に力が注がれ、窯業試験場の設立 や工業学校での人材育成 など、官民一体となった取り組みが進められました。
大川内子爵による日本の陶系と作風の分類では、「古雅式の瀬戸風」「純日本式の京都風」「朝鮮式の唐津風」「支那式の有田風」の四つの系統に大別されており、肥前地域の陶磁器(唐津風と有田風)が、日本の陶磁器全体を特徴づける主要な二つの系統を形成していることが明示されています。
これらの歴史的経緯から、肥前地域の陶磁器は、外国からの技術導入、磁器生産の開始、独自の様式確立、そして産業的発展という点で、日本の陶磁史において極めて重要かつ多大な貢献をしてきたと言えます。