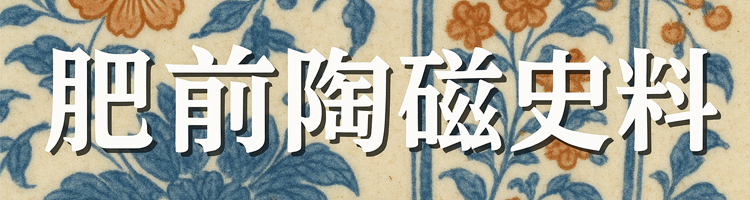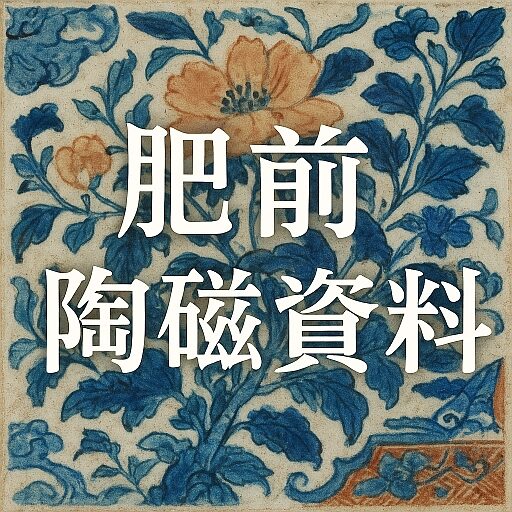肥前地域における陶磁器の発展は、技術革新と多様な文化的交流によって大きく推進されてきました。これらの要素は、日本の陶磁器全体の歴史において、肥前陶磁器が「我邦陶磁史の中枢」 を成すと言われる所以でもあります。
1. 主要な技術革新
肥前陶磁器の発展に影響を与えた技術革新は多岐にわたります。
- 製陶技術の導入(唐津焼の起源)
- 日本の陶磁器史において、朝鮮半島からの製陶技術が本格的に導入された始祖とされているのが「唐津焼」です。仲哀天皇9年に神功皇后が三韓出兵から帰還した際、従ってきた韓土の陶工が肥前国上松浦の港(後の唐津)で製陶を始めたとされています。
- 斉明天皇の御代には、韓土の陶工が肥前国上松浦の地で「高麗焼」を創製し、これにより日本で初めて施釉陶器が製作され始めたと見られています。初期の唐津焼は無釉陶器でしたが、後に施釉技術が導入されました。
- 磁器製造の開始(有田焼の発祥)
- 日本の陶磁器史における最も画期的な技術革新の一つが磁器の国産化です。元和年間、陶祖・李参平(金ヶ江三兵衛)が有田郷乱橋に来て泉山で最良の磁石を発見し、白川に移住して初めて純白な磁器を製出したことで、上白川窯、すなわち天狗谷が「我日本に於ける最初の磁器發祥地」となりました。これは「我製陶界に大いなる革命」と評されています。
- 磁器の主要原料である磁土、長石、珪石(石英)を主成分とし、高温で焼成することで緻密堅牢な素地を持つことが特徴です。
- 様式と顔料の革新
- 濁し手(乳白手)の創作:喜三右衛門は従来の白磁製造に新たな工夫を加え、「濁し手焼(乳白手)」を創作しました。これは厚い釉薬で青みを帯びる古伊万里とは異なり、薄い釉薬で乳白色を呈する純白な磁器でした。
- 赤絵技術の発展(柿右衛門様式):正保3年(1646年)には柿右衛門が錦彩磁器の創製を企図し、苦心して発明に至ったとされます。初代柿右衛門の赤絵技術は「彌々圓熟の境に達した」と評され、その作品は中国明代の赤絵以上とされ、フランスで「世界第一」と称されるほど高い国際評価を得ました。この様式は、中国の爛熟期における赤絵を模倣しつつ、日本独自の美的感覚を取り入れたものです。
- コバルト顔料の導入と改良:明治時代には、ドイツ人化学者ワゲネルによって酸化コバルト顔料の有効性が発見され、日本の製陶界に紹介されました。これにより、従来の中国呉洲に比べて品質が安定し、大量生産が可能になりました。当初は濃すぎて使用できないとされたコバルトも、地土で希釈する方法が発見され、普及しました。
- その他の顔料開発:赤彩料のフラックスとして唐石や唐土が調合され、日の岡石が焼成時の氷裂防止に用いられました。黄色や薄墨色、緋色といった新たな色彩料の研究も進められました。
- 窯と積込技術の改良
- 古代の焼物窯は、斜面に掘られた細長い窖窯が始まりとされ、後に長窯や丸窯を連鎖させた登窯が構成されました。
- 石炭窯の導入:明治初期にはドイツ人ワゲネルによって石炭窯の試焼が行われ、その有用性が示されました。当初は技術的な課題がありましたが、後に低価格生産の観点から普及が進みました。
- 積込技術の革新:辰十によって、従来の重ね積法から、積込効率を大幅に向上させる「天秤積法」が考案されました。これは窯業史上特筆すべき功績とされています。その後、八代深海市郎によってさらに改良された「伽藍積」も考案されました。
- 成形技術の進化
- 初期の土器成形は手捻りが主でしたが、後に轆轤(手車、蹴車)が導入され、さらに押型や石膏型込法、動力廻轉機が応用されるようになりました。近年では泥漿溶作法も広く応用されています。
- 現代化と産業化への取り組み
- 分業制の提唱:ワゲネルは、磁器製造における経済的分業の重要性を説き、各工程を専門化することで事業の発展と進歩を促すことを提言しました。
- 特殊製品の製造:耐酸磁器、碍子、磁製ローラーなど、化学的・工業的特許品の研究・製造が進められました。また、浴槽用タイルや硬質タイル、便器などの建築用陶磁器も生産されるようになりました。
- 教育機関の設立:有田徒弟学校(後の有田工業学校)の設立は、技術者育成の基礎となり、肥前陶磁器の技術向上と産業的発展に大きく貢献しました。
2. 主要な文化的交流
肥前陶磁器の発展は、国内外の様々な文化との交流によって形成されてきました。
- 朝鮮半島からの影響
- 陶工の渡来と技術移転:日本の陶器生産の本格的な始まりは、三韓出兵時に肥前に帰化した韓土の陶工による唐津焼の創始とされています。彼らは轆轤の使用など朝鮮式の製法を日本に伝えました。
- 磁器製造の起源:日本の磁器製造もまた、朝鮮半島の陶工・李参平によって始められました。彼と同郷である金江島出身の韓人たちが協力して磁器技術を確立したと推測されています。
- 作風への影響:大川内子爵の分類にもあるように、「朝鮮式の唐津風」は日本の陶系の一つとして確立されています。唐津焼の多様な釉薬や作風には、朝鮮半島の陶磁器からの影響が見られます。
- 中国からの影響
- 青磁の輸入と模倣:平安朝時代には、仏具として支那の青瓷(青磁)が多量に輸入され、日本でも模倣されるようになりました。
- 様式と絵付け:有田焼は「支那式の有田風」と分類されるように、中国の「青花」(染付)や「赤絵」に倣って発展しました。特に柿右衛門様式は、中国の赤絵技術を模倣しつつ、日本独自の様式を確立しました。
- 顔料の導入:青花顔料である呉洲(酸化コバルト)や、赤絵の顔料である白玉、唐土(鉛丹)なども中国から輸入されました。
- 貿易の媒介:長崎に居留する支那人を通じて、製陶に必要な材料が購入され、技術的な情報ももたらされたと考えられます。また、中国で柿右衛門様式の模造品が製作され、ヨーロッパへ輸出された事例も指摘されています。
- ヨーロッパとの交流
- 柿右衛門様式の世界的評価:柿右衛門の赤絵は、17世紀後半にはヨーロッパの宮廷で高く評価され、「世界第一」と称されるほどでした。これにより、日本の陶磁器は国際的な名声を得ることになりました。
- オランダ貿易:オランダを通じて、日本の陶磁器はヨーロッパへ輸出され、同時にヨーロッパの美術や更紗模様などが日本の陶磁器のデザインに取り入れられる機会も生まれました。
- 西洋技術の導入:ドイツ人化学者ワゲネルの来日は、肥前陶磁器の科学化と近代化に大きな影響を与えました。彼は石炭窯、コバルト顔料、石灰釉などの研究・導入を指導し、日本の陶磁器産業に大きな恩恵をもたらしました。
- 国際博覧会への出品:パリ万国博覧会をはじめとする国際的な展示会への出品は、日本の陶磁器を世界に紹介し、その評価を高める機会となりました。
- 輸出市場への対応:海外市場の嗜好に合わせて製品が開発され、例えば細口の徳利がランプスタンドとして人気を博すなど、用途の多様化が見られました。
- 日本国内他地域との交流
- 国内市場での影響力:関西地方で陶器全般を「唐津物」と呼ぶほど、唐津焼は全国的に影響力を持っていました。また、肥前磁器は「伊万里焼」として広く認識され、磁器の代名詞となりました。
- 技術伝播と交流:有田の赤絵技術が京都の野々村仁清に伝わったとされる「碗久物語」 のような事例は、国内の陶工間の交流を示しています。また、瀬戸や美濃といった他地域の陶工との比較研究も行われました。
- 茶道の流行:千利休に始まる茶の湯の全盛期は、唐津焼や織部焼など、土器や陶器の持つ「窯變の妙、胎土の味、箆の作行、手捻りの技法」といった特殊な妙味を愛好する文化を育み、肥前陶磁器の多様な発展を促しました。
これらの技術革新と文化的交流が複合的に作用し、肥前陶磁器は日本の陶磁史において、その発展の中心的役割を担うことになりました。