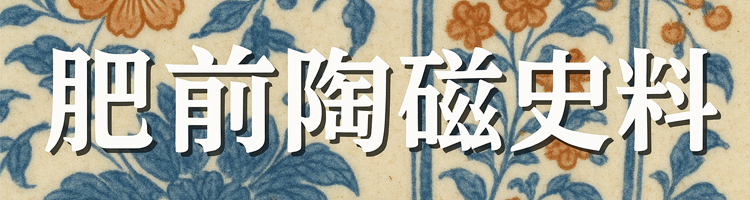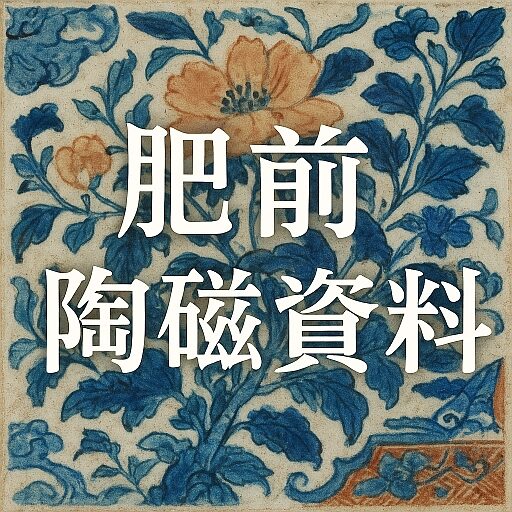肥前地域の陶磁器の歴史は、日本の陶磁器全体の歴史において中枢を成すものと位置づけられています。
その主要な位置づけと貢献は以下の通りです。
- 朝鮮陶技の導入と陶器の発展:
- 日本の陶磁史において、韓系の製陶として最古の歴史を持つのが肥前国上松浦の唐津焼です。神功皇后の三韓出兵後、朝鮮の陶工が肥前(後の唐津)に帰化し、朝鮮式の製法を日本に植え付けたことが唐津焼の始まりとされています。
- 仁治3年(約693年前)、瀬戸の加藤春慶が窯を開いたのと同時代、あるいはそれ以前に、唐津では釉薬を用いた堅緻で優秀な陶器が製作されており、その製作の古さや発達は「本邦中他に比類あらざる」と評されています。
- 関西地方では、焼物の汎称が「瀬戸物」である関東に対し、「唐津物」と呼ばれるほどに普及し、陶器を唐津物、磁器を伊万里物と称する地域もあったほどです。これは唐津焼が日本の陶器文化に深く根付き、その代名詞となるほどの広がりを持っていたことを示しています。
- 日本における磁器生産の創始と革命:
- 有田焼の発祥は、食器として清白透明な磁器の時代を創造し、「我製陶界に大いなる革命であつた」とされています。
- 金ヶ江三兵衛が泉山で天然の単味磁石(磁鉱)を発見したことが、硬質な磁器製作の完成へと繋がり、「我日本に於ける最初の磁器發祥地は、此上白川窯則ち天狗谷を措いて他にはない」と明言されています。
- 有田での白磁製造の成功は、他山の領主や陶工たちの羨望を集め、各地で磁器製作の熱が高まり、従来の陶器(黒物)製作に代わるものとなりました。これにより、肥前地域が日本の磁器産業の起爆剤となったことが伺えます。
- 国際的な評価と貿易の拡大:
- 肥前地域の磁器は、伊万里市場を経由して搬出されたことから、「伊万里焼」が日本の磁器の汎称となり、白磁の製作が未だ見られなかった当時、伊万里焼は磁器の代名詞とされていました。
- 柿右衛門の陶技は「世界第一」と称賛され、フランスでは中国明代の赤絵よりも優れていると評価されるなど、国際的にも最高水準の芸術性を誇りました。
- 肥前陶業は、鎖国論や攘夷説を「井蛙的愚見」として退け、積極的に海外貿易を展開しました。第一次世界大戦後には、有田町の陶磁器生産額の50%が外国に輸出されるなど、日本の主要な輸出品としての地位を確立しました。
- 鍋島焼は、窯銘がなくとも一見してわかる「獨得の超越」した美意識と技術を持ち、その精巧な技術はヨーロッパの美術家をも驚かせました。
- 技術革新と近代化への貢献:
- コバルト青顔料の使用は、有田焼の製法を便法化させ、古伊万里の特色を失わせる一方で、日用品の拡販という経済的側面から大きな進歩をもたらしました。
- 松村八次郎が日本で初めて硬質陶器の製作に成功し、輸入品の防止に貢献するなど、肥前は近代的な陶磁器技術の革新においても中心的な役割を担いました。
- 窯業試験場の設立や陶工の育成など、技術指導と教育の基盤整備も進められました。
肥前古陶展覧会では、鍋島家内庫所の青磁麒麟の置物や深川栄左衛門の錦手鳳凰の大丼など、数々の逸品が展示され、肥前磁器の真価が郷土の人々に知らされたとあります。このように、肥前地域の陶磁器は、技術の導入、磁器の創始、国際貿易、そして近代的な技術革新を通じて、日本の陶磁器全体の歴史と発展に決定的な影響を与え、その中心的な役割を担ってきたと言えます。