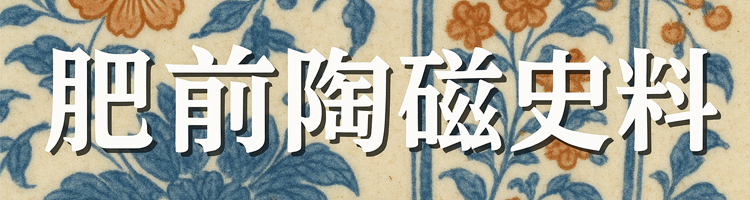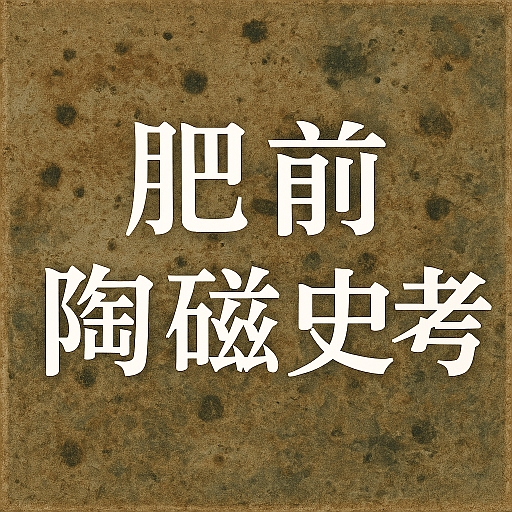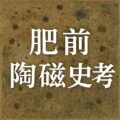【原文】[Original text]
焼物の種類
現代にては焼物の種類を土器(アーセンウエア)陶器(フハイヤンス又はポッタリー)硬質陶器(アイアン・ストーン・チャイナ又はハードポッタリー)炻器(ストーン・ウェア)磁器(ボースレイン)の五種に區別されてゐるが或は又土器や陶器類を軟陶に、炻器や磁器を硬陶に大別することもある。
焼物の硬軟
而して軟質の原料にて製作されたとしても、焚き方の技法と其焼成火度に因つては硬質の焼物と成るのがあり、又硬質の原料とても前記の方法次第にては軟質の焼物が出來るのである。故に結局は窯を母胎としての成品に依て區別する外はない。蓋し軟陶とするも、幾程度の焼成物が土器であり、そして又どこ迄の焼成物が陶器であるか、一見しては定め難きものがあり、斯くて陶器と炻器との中間程度に焼成されたのがある。
要するに軟陶と硬陶との區別は、それが本来土を捏ねて焼きしか、石を砕いて焼きしかの原料上の問題でなく、燒上た物の性質が土の様であるか或は石の如くであるか、そして―水分吸収の有無―水分を吸収せぬ無氣孔質か、否かとの區別に依る外はない。蓋し磁器だけは白袖の透明質と素地の堅牢さを一見して、誰人にてもそれと判別し得るのである。
磁器の硬軟
尚石焼と稱する磁器の中にても、原料や焼成火度に依っての硬軟があり、又種々の特質がある。倒せば天然磁石にて焼成されし有田焼は、色相純白ならざるも硬度に於ては此種の冠たる可く。而して同じ礦質にても天草の原料にて焼成されし磁器は、前器と比較して縁邊缼を生じ易く。又瀬戸や美濃の磁器に至つては調合原料の關係にて色相頗る純白なるも、硝子の如く眞二つに壌はれ易い丈軟質である。
扨此種の焼物を原料と燒成火度に依って區別すれば、―磁器―磁器とは磁土、長石、珪石(石英)の主成分を以て形成された物を、一旦攝氏七・八百度より一千度位迄に素焼して、之に彩書及釉薬を施し、更に千二百五十度より千三百度以上に本焼せし珪酸質焼物にて、緻密堅牢なる素地は敢て水分を吸収することなく、打ては金属の如き清音を発する物、之が焼物中にて一番進歩せる製品である。其代表産地が肥前の有田焼及同三河内燒同波佐見焼、同嬉野焼をはじめ、京都の清水焼、尾張の瀬戸焼、美濃の多治見焼、加賀の九谷焼、岩代の會津焼、伊豫の砥部焼、但馬の出石焼、攝津の三田焼、羽前の平清水焼等である。
炻器
炻器とは多く粘土に砂を混じて製作せし物にて、焼成火度は攝氏千度乃至千二百度である。而して磁器と同様堅なる密器性にて量重く打てば石音を發し全く水分を吸収せぬ。色相は粘土の鐵分のため多く淡褐色や黝青色を帯びてゐるも、無釉物には朱泥、白泥、梨皮泥等がある。此種に属する物は尾張の常滑焼、伊勢の萬古焼、磐城の相馬焼、備前の伊部焼、伊賀の丸柱焼、筑前の高取焼、大隅の帖佐焼、肥後の八代焼、石見の石見焼、常陸の笠間焼、下野の益子焼 美濃の温故燒等の諸山がある。
硬質陶器
硬質陶器とは磁土、長石、石英を應分に使用せしものにて、焼成方法は磁器と反對に素焼の火度を千二百度位の高度に焼き、之に軟釉を施して千度位にて本燒せし物である。色は不透明乳白色なるが、氣孔質なる吸水性である。此製法は近代の創造にて製作所は名古屋の松村硬質陶器合名會社、同地の三引製陶會社、同地日本陶器株式會社、加賀の株式會社加賀製陶所、同金澤の日本硬質陶器株式會社(釜山の日本硬質陶器株式會社を本社とす)小倉の東洋陶器株式會社、四日市の山庄製陶所、有田の帝國窯業會社等である。
半磁器
陶器の種類にて近來又半磁器と稱する珪酸質燒物がある。それは長石分少なく粘土を主成分として透明を防ぎ、多く暗色を用ひられてゐる彼大正萬古などである。此種は概ね貿易品とし輸送の關係上軽量を主眼とし、且不透明なるは陶器として彼地の關税を少なうすべく目論まれし製品らしく、重なる製造地は京都、尾張、美濃及伊勢の四日市等である。
陶器
陶器は磁器に比して粘土分多く長石分少なく、打てば木音を發する粗質である。焼成火度は攝氏九百度内外より千二百度に達する物がある。胎土は暗色と白色とに数種があり、何れも水分を吸収する。古きは肥前の唐津焼より近江の信楽焼京都の粟田焼、豊前の上野焼、薩摩の苗代川焼、長門の萩焼、大和の赤膚焼、出雲の布志名焼、淡路の珉平焼等産地甚だ多い或は又 マジョリカ(石英質)及普通タイルの如きも此種類に属するものである。
土器
土器は遠く人類の元始時代より簡單に造られし器にて、焼物中にては一番劣等の部類に属するも、それは科學上より見たる區別にて、若し好事家の骨董的に賞翫する茶器などに至つては、驚く可き高價なる物あることは申すまでもない。
土器は粘土のみにて焼成されし物なるがゆえに脆弱にして氣孔ある粗質にて、打てば土音を發し且夥しく水分を吸収する。焼成火度は通常攝氏四五百度乃至七百度位といはれ、そして之に施釉せ物とらざる物とがある。古代の彌生式土器や埴輪、埴瓮など此部類にて、京都の樂焼、武藏の今戸焼、加賀の大樋焼、或は瓦、焙烙、焜爐等皆此種類に属するところの物である。
【現代語訳】[Modern Japanese translation]
焼物の種類
現代では、焼物は大きく五種類に分けられています。すなわち、土器(Earthenware)、陶器(Faïence または Pottery)、硬質陶器(Iron Stone China または Hard Pottery)、炻器(Stoneware)、磁器(Porcelain)です。また、土器や陶器を「軟陶」、炻器や磁器を「硬陶」と大別する場合もあります。
焼物の硬軟
柔らかい原料から作られていても、焼成の方法や火度によっては硬質の焼物になることがあります。逆に硬質の原料を用いても、方法次第で軟質に仕上がることもあります。結局のところ、窯から出てきた焼き上がりの製品の性質によって区別するしかありません。どこまでが土器で、どこからが陶器か、一見して判断するのは難しい場合もあり、陶器と炻器の中間の性質を持つものも存在します。
要するに、軟陶と硬陶の違いは原料の種類(土か石か)よりも、焼き上がった製品の性質にあります。それが土のように水分を吸収するか、あるいは石のように吸収しないか。つまり多孔質か無気孔質かで区別されます。磁器だけは白く透明感のある素地と強靱さを備え、誰でもひと目で見分けられるものです。
磁器の硬軟
磁器の中にも、原料や焼成温度によって硬質・軟質の違いがあり、さまざまな特質があります。例えば天然磁石の原料で焼かれた有田焼は、色は純白ではありませんが硬度においては最上位にあります。同じ鉱質でも、天草の原料で作られた磁器は縁に欠けが生じやすい傾向があります。また瀬戸や美濃の磁器は、原料の調合の関係で色は非常に純白ですが、ガラスのように真っ二つに割れやすく、むしろ軟質です。
一般的に磁器とは、磁土・長石・石英を主成分とし、まず摂氏700〜1000度で素焼きした後、彩色や釉薬を施し、さらに1250〜1300度以上で本焼きしたものを指します。その結果できる素地は緻密で堅牢であり、水分をまったく吸収せず、打てば金属のように澄んだ音を発します。磁器は焼物の中で最も進歩した製品であり、代表的な産地には肥前の有田焼・三河内焼・波佐見焼・嬉野焼、京都の清水焼、尾張の瀬戸焼、美濃の多治見焼、加賀の九谷焼、岩代の会津焼、伊予の砥部焼、但馬の出石焼、摂津の三田焼、羽前の平清水焼などがあります。
炻器
炻器は、粘土に砂を混ぜて作られる焼物で、焼成温度は摂氏1000〜1200度です。磁器と同じく緻密で堅く、水分を吸収しません。打てば石のような音を発します。色調は粘土に含まれる鉄分のため、淡褐色や青みがかった色になることが多く、釉薬をかけないものには朱泥・白泥・梨皮泥などがあります。代表的な産地は、常滑焼(尾張)、萬古焼(伊勢)、相馬焼(磐城)、伊部焼(備前)、丸柱焼(伊賀)、高取焼(筑前)、帖佐焼(大隅)、八代焼(肥後)、石見焼(石見)、笠間焼(常陸)、益子焼(下野)、温故焼(美濃)などです。
硬質陶器
硬質陶器は、磁土・長石・石英を配合して用い、磁器とは逆に素焼きを摂氏1200度ほどの高温で行い、その後、軟釉をかけて摂氏1000度前後で本焼きしたものです。色は不透明な乳白色で、気孔質のため吸水性があります。この製法は近代に考案されたもので、代表的な製造会社として、名古屋の松村硬質陶器合名会社、三引製陶会社、日本陶器株式会社、加賀製陶所、日本硬質陶器株式会社(金沢・釜山)、小倉の東洋陶器株式会社、四日市の山庄製陶所、有田の帝国窯業会社などがあります。
半磁器
近代には「半磁器」と呼ばれる焼物も登場しました。これは長石の割合が少なく粘土が主成分で、透明感を抑え、暗色を用いることが多い製品です。大正時代の萬古焼などがその例です。主に輸出用に作られ、軽量であることや、陶器扱いとして関税を低く抑える目的があったようです。京都、尾張、美濃、伊勢の四日市などが主な産地です。
陶器
陶器は、磁器に比べ粘土分が多く長石分が少ないため、打つと木のような鈍い音がする粗質の焼物です。焼成温度は摂氏900度前後から1200度程度まであります。胎土には暗色系と白色系があり、いずれも水分を吸収します。代表的な産地は、肥前の唐津焼、近江の信楽焼、京都の粟田焼、豊前の上野焼、薩摩の苗代川焼、長門の萩焼、大和の赤膚焼、出雲の布志名焼、淡路の珉平焼などであり、さらにマジョリカ(石英質)や一般的なタイルなどもこの範疇に入ります。
土器
土器は人類の原始時代から作られてきたもっとも古い焼物で、科学的に見れば最も劣った種類に属します。しかし、骨董として珍重される茶器などの中には驚くほど高価なものもあります。土器は粘土だけで作られるため脆く、多孔質で水をよく吸収し、打てば鈍い「土の音」がします。焼成温度は摂氏450〜700度程度で、施釉したものと無釉のものがあります。弥生式土器や埴輪、埴瓮などがその例で、京都の楽焼、武蔵の今戸焼、加賀の大樋焼、瓦や焙烙、火鉢などもこの種類に含まれます。
【英語訳】[English translation]
Types of Pottery
In modern times, pottery is classified into five main categories: Earthenware, Pottery (Faïence or Pottery), Hard Pottery (Iron Stone China or Hard Pottery), Stoneware, and Porcelain. Sometimes, however, earthenware and pottery are grouped together as “soft pottery,” while stoneware and porcelain are grouped as “hard pottery.”
Hard and Soft Pottery
Even when made from soft materials, the firing method and temperature can produce hard pottery. Conversely, even with hard materials, depending on the method, a softer ware may result. In the end, the distinction depends on the finished product that comes from the kiln. It is often difficult to judge at a glance where earthenware ends and pottery begins, and there are products that fall in between pottery and stoneware.
Thus, the difference between soft and hard pottery lies not in the raw materials (whether clay or stone) but in the properties of the finished product—whether it behaves like clay and absorbs water, or like stone and remains impermeable. Only porcelain is easily recognizable at a glance due to its whiteness, translucence, and strength.
Hardness of Porcelain
Even within porcelain, differences in hardness exist depending on raw materials and firing temperature, with various distinct characteristics. For example, Arita ware, made from natural magnetite, is not pure white but excels in hardness. Porcelain made with Amakusa clay, though of similar mineral composition, is prone to chipping. Porcelain from Seto and Mino, on the other hand, is highly pure white due to material blending but is soft and easily breaks like glass.
Generally, porcelain is made from kaolin, feldspar, and quartz. It is first bisque-fired at 700–1000°C, then decorated and glazed, and finally fired at 1250–1300°C or higher. The result is a dense, durable body that absorbs no water and produces a metallic ring when struck. This is the most advanced form of ceramic ware. Representative production centers include Arita, Mikawachi, Hasami, and Ureshino in Hizen; Kiyomizu in Kyoto; Seto in Owari; Tajimi in Mino; Kutani in Kaga; Aizu in Iwashiro; Tobe in Iyo; Izushi in Tajima; Sanda in Settsu; and Hirashimizu in Uzen.
Stoneware
Stoneware is made by mixing clay with sand and firing at 1000–1200°C. Like porcelain, it is dense and impermeable, producing a stone-like sound when struck. Its color is often light brown or bluish due to iron in the clay. Unglazed wares include red clay, white clay, and pear-skin clay. Representative types include Tokoname (Owari), Banko (Ise), Soma (Iwaki), Bizen (Imbe), Iga (Marubashira), Takatori (Chikuzen), Chosa (Osumi), Yatsushiro (Higo), Iwami ware (Iwami), Kasama (Hitachi), Mashiko (Shimotsuke), and Onko ware (Mino).
Hard Pottery
Hard pottery uses kaolin, feldspar, and quartz. Unlike porcelain, it is first bisque-fired at a high temperature (about 1200°C), then coated with a soft glaze and fired again at about 1000°C. The result is an opaque, milky-white, porous, and water-absorbing ware. This method is a modern invention. Representative manufacturers include Matsumura Hard Pottery Partnership, Sanbiki Pottery Company, and Nippon Toki in Nagoya; Kaga Pottery Company and Nippon Hard Pottery Company in Kanazawa (with headquarters in Busan); Toyo Toki in Kokura; Yamasho Pottery in Yokkaichi; and Teikoku Pottery in Arita.
Semi-Porcelain
Semi-porcelain is another type of siliceous ware that appeared in modern times. It contains less feldspar and more clay, resulting in opaque, darker-colored products. Taishō-era Banko ware is a typical example. It was mainly produced for export, designed to be lightweight for shipping and classified as pottery to reduce tariffs. Major production areas were Kyoto, Owari, Mino, and Yokkaichi in Ise.
Pottery
Pottery has more clay and less feldspar than porcelain, giving it a coarse body that makes a wooden sound when struck. Firing temperatures range from about 900°C to 1200°C. Clay bodies come in both dark and white varieties, all of which absorb water. Famous production centers include Karatsu (Hizen), Shigaraki (Ōmi), Awata (Kyoto), Agano (Buzen), Naeshirogawa (Satsuma), Hagi (Nagato), Akahada (Yamato), Fushina (Izumo), and Minpei (Awaji). Majolica (siliceous) and common tiles also fall into this category.
Earthenware
Earthenware is the oldest type of pottery, dating back to prehistoric times. Scientifically, it is considered the most inferior category, but among tea wares appreciated by collectors, some command astonishingly high prices. Because earthenware is made only from clay, it is fragile, porous, and highly water-absorbent, producing a dull, earthy sound when struck. It is usually fired at 450–700°C and may be glazed or unglazed. Examples include Yayoi pottery, haniwa, hanihe jars, as well as Raku (Kyoto), Imado (Musashi), Ōhi (Kaga), and everyday wares like roof tiles, braziers, and cooking stoves.
—
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】[Chinese Simplified from Japanese]
烧物的种类
现代的烧物大致分为五类:土器(Earthenware)、陶器(Faïence 或 Pottery)、硬质陶器(Iron Stone China 或 Hard Pottery)、炻器(Stoneware)、瓷器(Porcelain)。有时也把土器和陶器归为“软陶”,把炻器和瓷器归为“硬陶”。
烧物的硬与软
即使用软质原料制作,也可能因烧成方法和温度不同而变得坚硬。反之,即使用硬质原料,也可能因方法不同而成为软质。归根到底,只能依靠窑中烧成品的性质来区分。究竟哪一部分算土器,哪一部分算陶器,一眼看去很难判定,甚至会出现介于陶器与炻器之间的制品。
总之,软陶与硬陶的区别不在于原料是泥土还是石头,而在于成品的性质——是否吸水、是否致密。若能吸水则属多孔质,不能吸水则属无孔质。唯独瓷器,因其白色透明的胎质与坚固性,任何人都能一眼分辨。
瓷器的硬与软
瓷器之中也因原料和烧成温度不同而有硬、软之别,并各具特色。例如以天然磁石原料烧成的有田烧,虽不纯白,却在硬度上居首。同样矿质的天草瓷器则容易出现边口缺损。至于濑户、美浓的瓷器,由于原料调和的关系,色泽非常纯白,但质地柔软,像玻璃一样容易碎裂。
一般而言,瓷器是以瓷土、长石、石英为主成分,先在700~1000℃进行素烧,再施彩绘和釉药,最后在1250~1300℃以上本烧而成。其胎质致密坚固,不吸水,敲击时发出如金属般的清音。这是烧物中最先进的制品。代表产地有肥前的有田烧、三河内烧、波佐见烧、嬉野烧,以及京都的清水烧、尾张的濑户烧、美浓的多治见烧、加贺的九谷烧、岩代的会津烧、伊予的砥部烧、但马的出石烧、摄津的三田烧、羽前的平清水烧等。
炻器
炻器是将黏土掺入砂制成,烧成温度约1000~1200℃。与瓷器一样质地致密坚硬,不吸水,敲之发石音。因含铁多呈浅褐色或青色,无釉制品有朱泥、白泥、梨皮泥等。代表产地有常滑烧(尾张)、万古烧(伊势)、相马烧(磐城)、伊部烧(备前)、丸柱烧(伊贺)、高取烧(筑前)、帖佐烧(大隅)、八代烧(肥后)、石见烧(石见)、笠间烧(常陆)、益子烧(下野)、温故烧(美浓)等。
硬质陶器
硬质陶器是将瓷土、长石、石英配合使用,与瓷器相反,先在约1200℃素烧,再施软釉,在约1000℃本烧而成。色泽呈不透明乳白色,具多孔性,能吸水。这是近代发明的制法。代表制造地有名古屋的松村硬质陶器合名会社、三引制陶会社、日本陶器株式会社,加贺的加贺制陶所、日本硬质陶器株式会社(金泽、釜山),小仓的东洋陶器株式会社,四日市的山庄制陶所,有田的帝国窑业会社等。
半瓷器
近代又出现一种称为“半瓷器”的硅酸质烧物。其长石含量少,以黏土为主成分,抑制透明感,多用暗色调,如大正时期的万古烧。此类产品多为出口品,重量轻便于运输,并作为陶器以减低关税。主要产地有京都、尾张、美浓和伊势的四日市。
陶器
陶器与瓷器相比,黏土含量高而长石少,质地粗糙,敲击时发木音。烧成温度约900~1200℃。胎土有暗色和白色几种,均能吸水。代表产地有唐津烧(肥前)、信乐烧(近江)、粟田烧(京都)、上野烧(丰前)、苗代川烧(萨摩)、萩烧(长门)、赤肤烧(大和)、布志名烧(出云)、珉平烧(淡路)等。此外,马乔里卡(石英质)和普通瓷砖也属此类。
土器
土器是人类原始时代起最早制作的器物,科学上属于烧物中最低等级。但在茶器等古董收藏品中,有的价值极高。土器仅以黏土制成,质地脆弱,多孔,吸水力强,敲之发“土音”。烧成温度约450~700℃,有施釉与无釉之别。弥生式土器、埴轮、埴瓮均属此类,京都的乐烧、武藏的今户烧、加贺的大樋烧,以及瓦、焙烙、火炉等也属此类。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】[Chinese Traditional from Japanese]
燒物的種類
現代的燒物大致分為五類:土器(Earthenware)、陶器(Faïence 或 Pottery)、硬質陶器(Iron Stone China 或 Hard Pottery)、炻器(Stoneware)、瓷器(Porcelain)。有時也把土器與陶器歸為「軟陶」,把炻器與瓷器歸為「硬陶」。
燒物的硬與軟
即使用軟質原料製作,也可能因燒成方法與溫度不同而變得堅硬。反之,即使用硬質原料,也可能因方法不同而成為軟質。歸根到底,只能依靠窯中燒成品的性質來區分。究竟哪一部分算土器,哪一部分算陶器,一眼難以判定,甚至會出現介於陶器與炻器之間的製品。
總之,軟陶與硬陶的區別不在於原料是泥土還是石頭,而在於成品的性質——是否吸水、是否致密。若能吸水則屬多孔質,不能吸水則屬無孔質。唯獨瓷器,因其白色透明的胎質與堅固性,任何人都能一眼分辨。
瓷器的硬與軟
瓷器之中也因原料和燒成溫度不同而有硬、軟之別,並各具特色。例如以天然磁石原料燒成的有田燒,雖不純白,卻在硬度上居首。同樣礦質的天草瓷器則容易出現邊口缺損。至於瀨戶、美濃的瓷器,由於原料調和的關係,色澤非常純白,但質地柔軟,像玻璃一樣容易碎裂。
一般而言,瓷器是以瓷土、長石、石英為主成分,先在700~1000℃進行素燒,再施彩繪和釉藥,最後在1250~1300℃以上本燒而成。其胎質緻密堅固,不吸水,敲擊時發出如金屬般的清音。這是燒物中最先進的製品。代表產地有肥前的有田燒、三河內燒、波佐見燒、嬉野燒,以及京都的清水燒、尾張的瀨戶燒、美濃的多治見燒、加賀的九谷燒、岩代的會津燒、伊予的砥部燒、但馬的出石燒、攝津的三田燒、羽前的平清水燒等。
炻器
炻器是將黏土摻入砂製成,燒成溫度約1000~1200℃。與瓷器一樣質地緻密堅硬,不吸水,敲之發石音。因含鐵多呈淺褐色或青色,無釉製品有朱泥、白泥、梨皮泥等。代表產地有常滑燒(尾張)、萬古燒(伊勢)、相馬燒(磐城)、伊部燒(備前)、丸柱燒(伊賀)、高取燒(筑前)、帖佐燒(大隅)、八代燒(肥後)、石見燒(石見)、笠間燒(常陸)、益子燒(下野)、溫故燒(美濃)等。
硬質陶器
硬質陶器是將瓷土、長石、石英配合使用,與瓷器相反,先在約1200℃素燒,再施軟釉,在約1000℃本燒而成。色澤呈不透明乳白色,具多孔性,能吸水。這是近代發明的製法。代表製造地有名古屋的松村硬質陶器合名會社、三引製陶會社、日本陶器株式會社,加賀的加賀製陶所、日本硬質陶器株式會社(金澤、釜山),小倉的東洋陶器株式會社,四日市的山莊製陶所,有田的帝國窯業會社等。
半瓷器
近代又出現一種稱為「半瓷器」的矽酸質燒物。其長石含量少,以黏土為主成分,抑制透明感,多用暗色調,如大正時期的萬古燒。此類產品多為出口品,重量輕便於運輸,並作為陶器以減低關稅。主要產地有京都、尾張、美濃和伊勢的四日市。
陶器
陶器與瓷器相比,黏土含量高而長石少,質地粗糙,敲擊時發木音。燒成溫度約900~1200℃。胎土有暗色和白色幾種,均能吸水。代表產地有唐津燒(肥前)、信樂燒(近江)、粟田燒(京都)、上野燒(豐前)、苗代川燒(薩摩)、萩燒(長門)、赤膚燒(大和)、布志名燒(出雲)、珉平燒(淡路)等。此外,馬喬里卡(石英質)和普通瓷磚也屬此類。
土器
土器是人類原始時代起最早製作的器物,科學上屬於燒物中最低等級。但在茶器等古董收藏品中,有的價值極高。土器僅以黏土製成,質地脆弱,多孔,吸水力強,敲之發「土音」。燒成溫度約450~700℃,有施釉與無釉之別。彌生式土器、埴輪、埴瓮均屬此類,京都的樂燒、武藏的今戶燒、加賀的大樋燒,以及瓦、焙烙、火爐等也屬此類。
【中国語訳(英語から簡体字)】[Chinese Simplified from English]
陶器的种类
在现代,陶器主要分为五类:土器(Earthenware)、陶器(Faïence 或 Pottery)、硬质陶器(Iron Stone China 或 Hard Pottery)、炻器(Stoneware)以及瓷器(Porcelain)。有时也把土器和陶器归为“软陶”,炻器和瓷器归为“硬陶”。
软陶与硬陶
即使使用软质原料制作,由于烧成方法和温度不同,也可能制成坚硬的陶器。相反,即使用硬质原料,如果方法不同,也可能得到软质制品。因此,区分的标准只能依靠出窑后的成品特征。有时难以明确界定土器与陶器的界限,也存在介于陶器与炻器之间的制品。
因此,软陶和硬陶的区别不在于原料是泥土还是石头,而在于成品的性质——是否像土一样吸水,还是像石头一样致密不吸水。唯一的例外是瓷器,它因洁白透明的质地与坚固性,任何人都能一眼辨认。
瓷器的硬与软
瓷器内部也有硬质和软质的差别,取决于原料和烧成温度,并表现出不同的特性。例如,有田烧使用天然磁石为原料,虽不纯白,却以硬度著称。天草的瓷器虽然原料相近,却容易在边缘产生缺口。瀬户和美浓的瓷器因原料调配的关系,色泽极为纯白,但质地柔软,像玻璃一样容易破裂。
通常,瓷器是由高岭土、长石和石英制成。首先在700–1000℃素烧,再施以彩绘和釉药,最后在1250–1300℃以上本烧。成品致密坚固,不吸水,敲击时发出金属般的清音。瓷器是最先进的陶器制品。代表产地有肥前的有田、三河内、波佐见、嬉野,以及京都的清水、尾张的濑户、美浓的多治见、加贺的九谷、岩代的会津、伊予的砥部、但马的出石、摄津的三田、羽前的平清水等。
炻器
炻器是将黏土混入砂制成,在1000–1200℃烧成。与瓷器一样,质地致密坚硬,不吸水,敲击时发出石声。由于含铁成分,颜色多为浅褐色或青色。无釉制品有朱泥、白泥、梨皮泥等。代表产地有常滑(尾张)、万古(伊势)、相马(磐城)、伊部(备前)、丸柱(伊贺)、高取(筑前)、帖佐(大隅)、八代(肥后)、石见(石见)、笠间(常陆)、益子(下野)、温故(美浓)等。
硬质陶器
硬质陶器以高岭土、长石、石英为原料。与瓷器相反,先在约1200℃素烧,再施以软釉,于约1000℃本烧。其色泽为不透明乳白色,属多孔质,能吸水。这种制法是近代的发明。代表制造商有名古屋的松村硬质陶器合名会社、三引制陶会社、日本陶器株式会社;加贺的加贺制陶所、日本硬质陶器株式会社(金泽、釜山);小仓的东洋陶器株式会社;四日市的山庄制陶所;有田的帝国窑业会社等。
半瓷器
近代还出现了一种“半瓷器”。它含长石少,以黏土为主,减少透明感,多为暗色调,如大正时期的万古烧。主要为出口制品,设计轻便以利运输,并作为陶器处理以降低关税。主要产地有京都、尾张、美浓和伊势的四日市。
陶器
陶器与瓷器相比,含泥量高而长石少,质地粗糙,敲击时发木声。烧成温度在900–1200℃之间。胎土有暗色和白色两种,都能吸水。代表产地有唐津(肥前)、信乐(近江)、粟田(京都)、上野(丰前)、苗代川(萨摩)、萩(长门)、赤肤(大和)、布志名(出云)、珉平(淡路)等。此外,马约里卡(石英质)和普通瓷砖也属此类。
土器
土器是人类史前时期最早制作的器物,从科学角度看属于最低级的一类。但作为古董的茶器中,有些价值极高。土器仅用黏土制成,质地脆弱,多孔,强吸水,敲击时发“土声”。烧成温度通常为450–700℃,有的施釉,有的无釉。弥生式土器、埴轮、埴瓮都属于此类,京都的乐烧、武藏的今户烧、加贺的大樋烧,以及瓦、焙烙、火炉等都属于此类。
【中国語訳(英語から繁體字)】[Chinese Traditional from English]
陶器的種類
在現代,陶器主要分為五類:土器(Earthenware)、陶器(Faïence 或 Pottery)、硬質陶器(Iron Stone China 或 Hard Pottery)、炻器(Stoneware)以及瓷器(Porcelain)。有時也把土器和陶器歸為「軟陶」,炻器和瓷器歸為「硬陶」。
軟陶與硬陶
即使用軟質原料製作,由於燒成方法和溫度不同,也可能製成堅硬的陶器。相反,即使用硬質原料,如果方法不同,也可能得到軟質製品。因此,區分的標準只能依靠出窯後的成品特徵。有時難以明確界定土器與陶器的界限,也存在介於陶器與炻器之間的製品。
因此,軟陶和硬陶的區別不在於原料是泥土還是石頭,而在於成品的性質——是否像土一樣吸水,還是像石頭一樣緻密不吸水。唯一的例外是瓷器,它因潔白透明的質地與堅固性,任何人都能一眼辨認。
瓷器的硬與軟
瓷器內部也有硬質和軟質的差別,取決於原料和燒成溫度,並表現出不同的特性。例如,有田燒使用天然磁石為原料,雖不純白,卻以硬度著稱。天草的瓷器雖然原料相近,卻容易在邊緣產生缺口。瀨戶和美濃的瓷器因原料調配的關係,色澤極為純白,但質地柔軟,像玻璃一樣容易破裂。
通常,瓷器是由高嶺土、長石和石英製成。首先在700–1000℃素燒,再施以彩繪和釉藥,最後在1250–1300℃以上本燒。成品緻密堅固,不吸水,敲擊時發出金屬般的清音。瓷器是最先進的陶器製品。代表產地有肥前的有田、三河內、波佐見、嬉野,以及京都的清水、尾張的瀨戶、美濃的多治見、加賀的九谷、岩代的會津、伊予的砥部、但馬的出石、攝津的三田、羽前的平清水等。
炻器
炻器是將黏土混入砂製成,在1000–1200℃燒成。與瓷器一樣,質地緻密堅硬,不吸水,敲擊時發出石聲。由於含鐵成分,顏色多為淺褐色或青色。無釉製品有朱泥、白泥、梨皮泥等。代表產地有常滑(尾張)、萬古(伊勢)、相馬(磐城)、伊部(備前)、丸柱(伊賀)、高取(筑前)、帖佐(大隅)、八代(肥後)、石見(石見)、笠間(常陸)、益子(下野)、溫故(美濃)等。
硬質陶器
硬質陶器以高嶺土、長石、石英為原料。與瓷器相反,先在約1200℃素燒,再施以軟釉,於約1000℃本燒。其色澤為不透明乳白色,屬多孔質,能吸水。這種製法是近代的發明。代表製造商有名古屋的松村硬質陶器合名會社、三引製陶會社、日本陶器株式會社;加賀的加賀製陶所、日本硬質陶器株式會社(金澤、釜山);小倉的東洋陶器株式會社;四日市的山莊製陶所;有田的帝國窯業會社等。
半瓷器
近代還出現了一種「半瓷器」。它含長石少,以黏土為主,減少透明感,多為暗色調,如大正時期的萬古燒。主要為出口製品,設計輕便以利運輸,並作為陶器處理以降低關稅。主要產地有京都、尾張、美濃和伊勢的四日市。
陶器
陶器與瓷器相比,含泥量高而長石少,質地粗糙,敲擊時發木聲。燒成溫度在900–1200℃之間。胎土有暗色和白色兩種,都能吸水。代表產地有唐津(肥前)、信樂(近江)、粟田(京都)、上野(豐前)、苗代川(薩摩)、萩(長門)、赤膚(大和)、布志名(出雲)、珉平(淡路)等。此外,馬約里卡(石英質)和普通瓷磚也屬此類。
土器
土器是人類史前時期最早製作的器物,從科學角度看屬於最低級的一類。但作為古董的茶器中,有些價值極高。土器僅用黏土製成,質地脆弱,多孔,強吸水,敲擊時發「土聲」。燒成溫度通常為450–700℃,有的施釉,有的無釉。彌生式土器、埴輪、埴瓮都屬於此類,京都的樂燒、武藏的今戶燒、加賀的大樋燒,以及瓦、焙烙、火爐等都屬於此類。