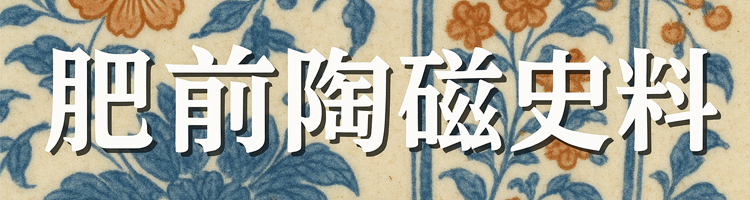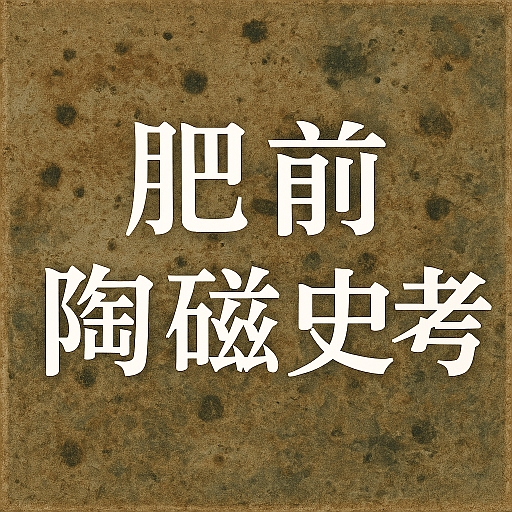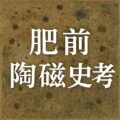【原文】[Original text]
焼物と其分類
現代生活と焼物
吾々が生活上の要件である衣食住の中に、毎日缺ぐ可からざる食事の容器であり、又茶器であるところの焼物に就いて、概念的にも之が知識を備ふることは頗る必要であり。そして今や住宅の建築用材より、衣服の装身具にま焼物の用さる時代となった。故に吾々の生活と焼物とはに不可分的の關係あるものさいはねばならぬ。
焼物知識の必須
それかあらぬか、近來此焼物に於ける観賞と應用の研究者頓に増加し、或は床上の装飾物より臺所の日用品にまで、趣味と濟上よりの知識欲求が熾烈なるに至ったのである。殊に文化の發達に伴なひ益々複雑多岐に成りゆく現代に於いて、指導者たる可き爲政家や、敢育家の如きに至つては、より豊富なる廣況に亘つての知識涵養が必要なるはいふまでもなきに、管に其郷土の沿革史さへ知らずして漫然其職に携はる如きは、海図と羅針盤との準備なくして茫々たる太洋に乗出せし船員たるのあるを免れね。
況んや本業たる焼物製作者及び共販資者は勿論の事として、又學生にも或程度の製法や、商品學しての予備知識を要するがあり、就中該品の鑑賞に趣味を有する好陶家に於いては、全然必須の事柄であらねばならぬ。而して此焼物の要点たる性格 其沿革を識らんと欲すれば、先づ製法を全國に傅へし肥前の陶磁史を識るにあらざれば、未だ以て焼物を語る資格なき者と断せざるを得ぬ。
本書は焼物の何物なるかを説き、而して人類と焼物の密接なる關係より我國の陶史に及ぼし、次に肥前各山の沿革と其焼物の種類を記述せるものにして、此書を繙きて始めて斯業の根元地たる肥前と、全國各製陶地との關係をも識るに至る可く、故に肥前陶磁史考と稱するも、質は我邦陶磁史の中樞を成すものといふ可きである。
焼物の本体
焼物の本体なるものは、何であるかと言へば、それは珪酸塩の熟化されたる結晶物体である。尚換言すれば酸化金属と、硝子質の共同焼成の結果、さらに色彩と可塑性とを具へたこの耐久性物体であると科學者は説明してゐる、が、かゝる化學的解釋は専門の範圍に属するを以て、此處には既に焼成されたる物体の來歴と其性格とにつき重に記述するものである。
陶器の名稱
抑陶器といへる名稱は、古への須惠母乃、スヱノウツハモノにて、もと据ゑる物(古代の土器は下部丸くして据らぬ物なりしが、後に高臺「臺輪、糸切、糸底、糸尻、ひねりどめ」なる物を形造りて、据ゑる器となせし物であらう)の意義より起りし由なるが、後には土器にも、炻器にも、磁器にも、すべての焼物を總括的に皆陶器とせられてゐる。土器とは須惠母乃よりも脆き、土師器にて、之をハジモノ、ハニモノハジノウツハモノと稱するは、即ち土師の造る物或は埴輪物又は埴瓮(クレーフイガ)等の略稱であらう。(埴とは赤土又ねば土のことである)
瓷器其他
古への瓷器所謂シノウツハモノとは青瓷(セラドン)のことにて、即ちアホシ又秘色と稱せられ物にあたり、當時頗る貴重せし焼物なるも、天平瓷器は未た軟陶に属し、弘仁瓷器に至つて始めて硬胸に類す稱せらる。蓋し胎質が磁器に改まりしは勿論後代のことであらう。炻器とは砂陶の硬度に焼成されし物であり。磁器とは支那の宋代に於て、河南省彰德府(今の直隸省廣東府)の磁州窯に製せられし白磁より名つけられしといはれてゐる。
【現代語訳】[Modern Japanese translation]
焼物とその分類
現代生活と焼物
私たちの生活に欠かせない衣食住の中で、食事の器や茶器として毎日使われるのが焼物です。そのため、焼物について基本的な知識を持つことはとても大切です。さらに近年では、住宅の建築資材から衣服の装飾品にまで焼物が使われるようになり、焼物と私たちの生活は切り離せない関係にあります。
焼物知識の必要性
そのため近年、焼物の鑑賞や応用について研究する人が急に増えました。床の間を飾る美術品から台所の日用品に至るまで、趣味と実用の両面から知識を求める人が多くなったのです。特に文化がますます複雑に発展する現代において、政治家や教育者といった社会を導く立場の人々には、幅広い知識が必要です。もし郷土の歴史すら知らずに職務に就くならば、それは海図や羅針盤を持たずに大海へ漕ぎ出す船員のようなものです。
ましてや焼物を作る職人や販売に携わる人はもちろんのこと、学生にとっても、製法や商品学としての基礎知識は必要です。とりわけ焼物の鑑賞を趣味とする愛好家にとっては、欠かすことのできない知識といえます。そして焼物の本質や歴史を理解しようとするならば、まず全国にその製法を広めた肥前の陶磁史を学ばなければ、焼物について語る資格はないといわざるを得ません。
本書は焼物とは何かを説明し、人類との深い関わりから日本の陶磁の歴史を述べ、さらに肥前各地の窯とその焼物の種類を記録しています。この書を読むことで、肥前が日本陶磁の根本的な地であること、また全国の産地との関係を知ることができます。したがって「肥前陶磁史考」と題してはいますが、実質的には日本陶磁史の中心に位置づけられるものです。
焼物の本質
焼物の本体とは何かといえば、それは珪酸塩が焼き固められて結晶化した物体です。別の言い方をすれば、酸化金属とガラス質が一体となって焼成され、色彩と可塑性を備えた耐久性のある物質です。科学者はこのように説明していますが、この書では専門的な化学解釈ではなく、すでに焼成された焼物の歴史とその特徴について記すこととします。
陶器という名称
「陶器」という呼び名は、古代の「須恵器(すえもの)」に由来するといわれます。本来は据えて置ける器を意味しました。古代の土器は底が丸く据えられなかったため、のちに高台(台輪・糸切・糸底・糸尻・ひねり止めなど)を付けて据えられるようにしたのです。そのため「据え物=陶器」と呼ばれるようになったと考えられます。のちには、土器・炻器・磁器を含めたすべての焼物を総称して陶器と呼ぶようになりました。
「土器」とは須恵器より脆い「土師器(はじき)」のことで、「ハジモノ」「ハニモノ」と呼ばれました。つまり土師が作った器、あるいは埴輪や埴製の壺(埴瓮=くれふいが)などを指す略称です。(「埴」とは赤土や粘土を意味します)
磁器その他
古代に「瓷器(しのうつわもの)」と呼ばれたのは青磁(セラドン)のことで、「秘色」や「あおし」とも呼ばれ、当時は非常に貴重な焼物でした。ただし天平時代の瓷器はまだ軟陶に属し、弘仁時代になって初めて硬質陶器に近いものとされました。胎土が磁器に改まったのはもっと後の時代です。
炻器とは、砂を多く含む陶土を高温で焼き締めて硬度を持たせた焼物です。磁器という名称は、中国宋代に河南省彰徳府(現在の直隷省広東府)にあった磁州窯で作られた白磁に由来すると伝えられています。
【英語訳】[English translation]
Classification of Pottery
Modern Life and Pottery
Among the essentials of life—clothing, food, and shelter—pottery is indispensable as tableware and as utensils for tea. Therefore, it is important to have at least a basic understanding of pottery. Today, pottery is not only used for building materials but even for accessories in clothing, making it inseparable from our daily lives.
The Necessity of Pottery Knowledge
In recent times, interest in the study of pottery—both in terms of appreciation and practical use—has rapidly increased. From decorative items in alcoves to daily utensils in kitchens, the desire for both aesthetic enjoyment and practical knowledge has become intense. Especially in today’s increasingly complex cultural landscape, leaders such as politicians and educators require a broad and well-rounded knowledge. To take up a role without even knowing one’s local history is like a sailor setting out into the vast ocean without charts or a compass.
Needless to say, potters and merchants must have such knowledge, but even students are expected to acquire a certain understanding of production methods and commercial aspects. For pottery enthusiasts in particular, such knowledge is absolutely essential. And to truly understand the essence and history of pottery, one must first learn the history of Hizen, which spread ceramic techniques throughout Japan. Without this, one cannot be said to have the qualifications to speak on pottery.
This book explains what pottery is, its deep connection with humanity, and the history of ceramics in Japan. It then describes the history of the kilns in Hizen and their products. By reading it, one can see how Hizen served as the foundation of Japanese ceramics and understand its relation to other regions. Thus, though titled “A Study of Hizen Ceramic History,” its essence forms the very core of Japan’s ceramic history.
The Nature of Pottery
What, then, is the essence of pottery? It is a crystallized body of silicate compounds formed by firing. In other words, it is a durable material that results from the joint firing of metallic oxides and glassy substances, endowed with both color and plasticity. While scientists explain it in such chemical terms, this book will focus not on chemical analysis but on the history and characteristics of pottery as already fired objects.
The Name “Tōki” (Pottery)
The word “tōki” (pottery) is said to originate from ancient “Sue ware” (Sue no utsuwa-mono), which referred to vessels that could be placed firmly on a surface. Ancient earthenware often had rounded bottoms and could not stand, but later, bases such as kōdai (foot rings and related forms) were added, allowing them to stand upright. From this meaning of “set vessels” came the name tōki. Over time, the word came to encompass not only earthenware but also stoneware and porcelain, serving as a general term for all fired wares.
“Earthenware” refers to Haji ware, which is more fragile than Sue ware. It was also called “Hajimono” or “Hanemono,” meaning items made by the Haji people, or it could refer to haniwa figurines and haji pots (hanihe, or Kurefiga). (“Hani” here refers to red or clay soil.)
Porcelain and Others
In ancient times, the term “shino-utsuwa-mono” referred to celadon, also called “hisoku” (secret color) or “aoshi,” which was highly prized. However, porcelain from the Tenpyō period still belonged to soft pottery, and only in the Kōnin period was it considered close to hard ceramics. The change of clay body into true porcelain occurred much later.
Stoneware refers to pottery fired to the hardness of sandy clay. The name “porcelain” is said to have originated in China during the Song dynasty, from white porcelain produced at the Cizhou kilns in Xiangde Prefecture, Henan Province (present-day Guangdong in Zhili Province).
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】[Chinese Simplified from Japanese]
烧物及其分类
现代生活与烧物
在我们生活必需的衣食住中,餐具和茶具是每天都不可或缺的,而这正是烧物。因此,掌握烧物的基本知识非常重要。近年,烧物甚至被用于建筑材料和服饰装饰品,烧物与我们的生活已密不可分。
烧物知识的必要性
因此,近年来关于烧物的鉴赏与应用的研究者骤然增加。从床间的装饰品到厨房的日用品,人们对趣味与实用两方面知识的需求日益强烈。尤其在文化日益复杂多样的现代,政治家、教育家等社会领袖更需要广博的知识。如果连自己的乡土历史都不了解而贸然任职,就如同没有海图和罗盘便驶入茫茫大海的水手。
更不用说制陶者和销售者,甚至学生也需要具备一定的制法和商品学基础。特别是以鉴赏烧物为乐趣的陶艺爱好者,更是必须具备这样的知识。而要理解烧物的本质与历史,首先必须学习传播到全国的肥前陶瓷史,否则便无资格谈论烧物。
本书阐述了烧物的本质,说明了其与人类的密切关系,并进一步叙述了日本陶史,特别是肥前各窑的历史与产品。通过本书,可以认识到肥前是日本陶瓷的根本地,并理解其与全国各产地的关系。因此,虽题名为《肥前陶瓷史考》,实质上却是日本陶瓷史的核心。
烧物的本质
烧物的本体是什么呢?那是烧结后的硅酸盐结晶体。换言之,它是金属氧化物与玻璃质共同烧成的产物,具备色彩与可塑性的耐久物质。科学家如此解释,但本书不深入化学分析,而是着重于烧物的历史与特征。
陶器的名称
“陶器”一词,据说源自古代的须惠器,本意是“能放置的器物”。古代土器多为底部圆形,无法安放,后来在器物底部加上高台(台轮、线切、线底、线尻、收口等),才能稳固地置放,因此被称为陶器。后来,这一名称逐渐扩展,泛指土器、炻器、瓷器在内的所有烧物。
“土器”是指比须惠器更脆弱的“土师器”,又称“ハジモノ”或“ハニモノ”,意为土师制作的器物,或埴轮、埴制陶罐(埴瓮)。其中“埴”是指赤土或黏土。
瓷器及其他
古代所谓的“瓷器”,指的是青瓷(即青瓷、秘色、青子),当时极为珍贵。但天平时代的瓷器仍属软陶,至弘仁时代才被认为接近硬陶。胎质转为真正瓷器,是后世之事。
炻器是以含砂陶土高温烧结而成的坚
硬陶器。至于“瓷器”一名,相传起源于中国宋代河南省彰德府(今直隶省广东府)磁州窑出产的白瓷。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】[Chinese Traditional from Japanese]
燒物及其分類
現代生活與燒物
在我們生活必需的衣食住中,餐具與茶具是每天都不可或缺的,而這正是燒物。因此,掌握燒物的基本知識非常重要。近年,燒物甚至被用於建築材料與服飾裝飾品,燒物與我們的生活已密不可分。
燒物知識的必要性
因此,近年來關於燒物的鑑賞與應用的研究者驟然增加。從床間的裝飾品到廚房的日用品,人們對趣味與實用兩方面知識的需求日益強烈。尤其在文化日益複雜多樣的現代,政治家、教育家等社會領袖更需要廣博的知識。如果連自己的鄉土歷史都不了解而貿然任職,就如同沒有海圖和羅盤便駛入茫茫大海的水手。
更不用說製陶者和銷售者,甚至學生也需要具備一定的製法和商品學基礎。特別是以鑑賞燒物為樂趣的陶藝愛好者,更是必須具備這樣的知識。而要理解燒物的本質與歷史,首先必須學習傳播到全國的肥前陶瓷史,否則便無資格談論燒物。
本書闡述了燒物的本質,說明了其與人類的密切關係,並進一步敘述了日本陶史,特別是肥前各窯的歷史與產品。透過本書,可以認識到肥前是日本陶瓷的根本地,並理解其與全國各產地的關係。因此,雖題名為《肥前陶瓷史考》,實質上卻是日本陶瓷史的核心。
燒物的本質
燒物的本體是什麼呢?那是燒結後的矽酸鹽結晶體。換言之,它是金屬氧化物與玻璃質共同燒成的產物,具備色彩與可塑性的耐久物質。科學家如此解釋,但本書不深入化學分析,而是著重於燒物的歷史與特徵。
陶器的名稱
「陶器」一詞,據說源自古代的須惠器,本意是「能放置的器物」。古代土器多為底部圓形,無法安放,後來在器物底部加上高台(台輪、線切、線底、線尻、收口等),才能穩固地置放,因此被稱為陶器。後來,這一名稱逐漸擴展,泛指土器、炻器、瓷器在內的所有燒物。
「土器」是指比須惠器更脆弱的「土師器」,又稱「ハジモノ」或「ハニモノ」,意為土師製作的器物,或埴輪、埴製陶罐(埴瓮)。其中「埴」是指赤土或黏土。
瓷器及其他
古代所謂的「瓷器」,指的是青瓷(即青瓷、秘色、青子),當時極為珍貴。但天平時代的瓷器仍屬軟陶,至弘仁時代才被認為接近硬陶。胎質轉為真正瓷器,是後世之事。
炻器是以含砂陶土高溫燒結而成的堅硬陶器。至於「瓷器」一名,相傳起源於中國宋代河南省彰德府(今直隸省廣東府)磁州窯出產的白瓷。
【中国語訳(英語から簡体字)】[Chinese Simplified from English]
陶器及分类
现代生活与陶器
在衣食住三大生活必需品中,陶器作为餐具与茶具不可或缺。因此,掌握陶器的基本知识十分重要。如今,陶器甚至被用于建筑材料和服饰装饰,与日常生活密不可分。
陶器知识的必要性
近年来,对陶器的研究骤然增加,涵盖了鉴赏与应用。从装饰品到厨房用具,人们对美与实用的知识需求日益增强。尤其在文化复杂发展的现代,政治家、教育家等社会领袖更需要广博知识。若连本地历史都不知便担任职务,就如同水手无图无罗盘而入大海。
制陶匠人和商贩自然更需相关知识,学生也需具备基本制法与商品学常识。尤其爱好陶器鉴赏者,更离不开这种知识。而若要真正理解陶器的本质与历史,就必须先学习传播至全国的肥前陶瓷史,否则无资格谈陶器。
本书解释陶器是什么,说明其与人类的紧密联系,并叙述日本陶史,尤其是肥前各窑及其制品。由此可知肥前是日本陶瓷的根本地,并能理解其与其他产地的关系。因此,本书虽名为《肥前陶瓷史考》,实质是日本陶瓷史的核心。
陶器的本质
陶器本质是烧结后的硅酸盐晶体。换言之,是金属氧化物与玻璃质共同烧成的耐久物,具有色彩与可塑性。科学家如此解释,但本书着重叙述陶器的历史与特征,而非化学分析。
“陶器”的名称
“陶器”一词源自古代须惠器,原意为“能放置的器皿”。古代土器多为圆底,无法安放,后来加上高台使其稳固,因而称为陶器。此后,陶器一词逐渐扩展为土器、炻器、瓷器的总称。
“土器”是比须惠器更脆弱的“土师器”,亦称“ハジモノ”或“ハニモノ”,指土师制作的器物,或指埴轮与埴制陶罐(埴瓮)。其中“埴”即赤土或黏土。
瓷器及其他
古代所谓“瓷器”,指青瓷(秘色、青子),当时极其珍贵。但天平时代的瓷器仍属软陶,至弘仁时代才接近硬陶。胎质真正转为瓷器,是后世之事。
炻器是以含砂陶土高温烧制而成的坚硬陶器。瓷器一名,相传源自中国宋代河南省彰德府磁州窑出产的白瓷。
【中国語訳(英語から繁體字)】[Chinese Traditional from English]
陶器及分類
現代生活與陶器
在衣食住三大生活必需品中,陶器作為餐具與茶具不可或缺。因此,掌握陶器的基本知識十分重要。如今,陶器甚至被用於建築材料和服飾裝飾,與日常生活密不可分。
陶器知識的必要性
近年來,對陶器的研究驟然增加,涵蓋了鑑賞與應用。從裝飾品到廚房用具,人們對美與實用的知識需求日益增強。尤其在文化複雜發展的現代,政治家、教育家等社會領袖更需要廣博知識。若連本地歷史都不知便擔任職務,就如同水手無圖無羅盤而入大海。
製陶匠人和商販自然更需相關知識,學生也需具備基本製法與商品學常識。尤其愛好陶器鑑賞者,更離不開這種知識。而若要真正理解陶器的本質與歷史,就必須先學習傳播至全國的肥前陶瓷史,否則無資格談陶器。
本書解釋陶器是什麼,說明其與人類的緊密聯繫,並敘述日本陶史,尤其是肥前各窯及其製品。由此可知肥前是日本陶瓷的根本地,並能理解其與其他產地的關係。因此,本書雖名為《肥前陶瓷史考》,實質是日本陶瓷史的核心。
陶器的本質
陶器本質是燒結後的矽酸鹽晶體。換言之,是金屬氧化物與玻璃質共同燒成的耐久物,具有色彩與可塑性。科學家如此解釋,但本書著重敘述陶器的歷史與特徵,而非化學分析。
「陶器」的名稱
「陶器」一詞源自古代須惠器,原意為「能放置的器皿」。古代土器多為圓底,無法安放,後來加上高台使其穩固,因而稱為陶器。此後,陶器一詞逐漸擴展為土器、炻器、瓷器的總稱。
「土器」是比須惠器更脆弱的「土師器」,亦稱「ハジモノ」或「ハニモノ」,指土師製作的器物,或指埴輪與埴製陶罐(埴瓮)。其中「埴」即赤土或黏土。
瓷器及其他
古代所謂「瓷器」,指青瓷(秘色、青子),當時極其珍貴。但天平時代的瓷器仍屬軟陶,至弘仁時代才接近硬陶。胎質真正轉為瓷器,是後世之事。
炻器是以含砂陶土高溫燒制而成的堅硬陶器。瓷器一名,相傳源自中國宋代河南省彰德府磁州窯出產的白瓷。