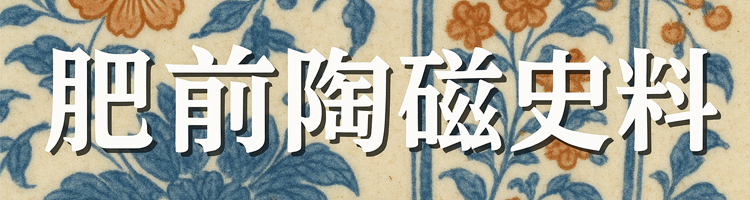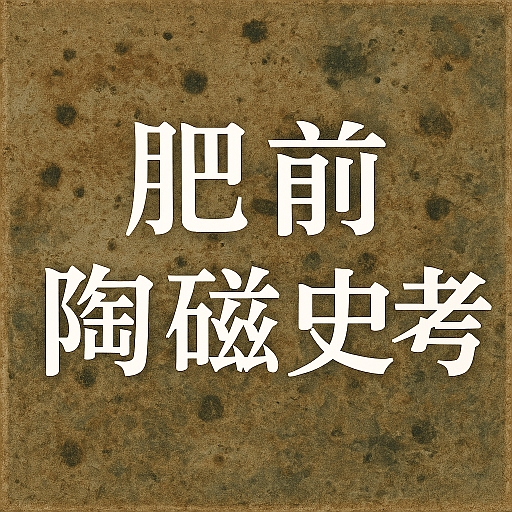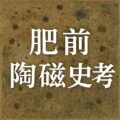【原文】
神代=天御中主神
我神代史に徹するに、天御中主命が海濱の真砂に白き物の附着してゐるを嘗めて味を知りたまひ、眞土を水にて掘り凹める土器を造り、それに海水を入れ火を焚きて眞砂を煎し、其湯固まりて塩となることを発見し給ひきっと開闢記に記載されてゐる。
簸の川上の製甕
それより天神七代伊弉諾尊のいざなぎ御子素盞鳴尊(天照皇大神の御舎弟)が、彼櫛名田媛を救はせ給ひしとき、八岐入頭の大蛇に毒酒を盛り給ひしことは人口に膾炙せる故事なるが。
そのとき用ひ給へる八個の甕は、足名椎と手名椎に命じて、出雲國簸の川上(大原郡)に於いて焼かし給ひし由傳へらる。夫れは嘗て尊が韓郷島(朝鮮)にましませし時、すでに製陶の法を会得さ居り給ひしと推せらる。
其後天孫天忍穂耳尊(素盞鳴尊の御子にて天照皇大神宮の御養子)を葦原の中つ国へ下し給ひてより、我邦の西端(筑紫)は近き支那及朝鮮の薫化を享け、従つて同地方にはその製陶の技を習得する者があつたであらう。當時の陶技は筑紫、出雲、大和の三方面より發せしといはれてゐる。
彌生式土器
而して我が民族が、最古に用ひしさいばし土器(土師器)は褐黄色を呈し、形状は多く鍋底式の丸くして高臺なく、概して無文とされてゐる。中に僅に刷毛目を存する物があり、火度は六百度より七百度位に焼成されしが如く、之が今彌生式土器又は高天原土器と稱せらるゝところのものである。
陶祖大陶祇
素盞鳴尊六世の孫天冬衣尊の御子大已貴尊(大國主神)の御時、茅渟の縣といふ此處に大陶祗(陶津耳命)なる者ありて、陶器を造りしよし古事記にある。此大陶祗は大巳貴尊の舅にて土地の豪族なりしが如く、之が我邦の陶麗と稱すべきであらう。(茅淳は難波の浦方面の名にて其縣なる和泉國の深坂村、田園村、辻の村、大村、北村、府久田村、高村、岩室村以上を陶器莊「大鳥郡」と言ひ傳へらる)
天日槍の渡来
此頃韓鄉島の天日槍我邦に歸化し、暫らく近江吾名邑なる鏡谷に在りしが、當時從ひ来れる陶工ありて此地に於いて焼物を焼きしの口碑がある。(天日槍は其後但馬に住し、其子但馬諸助以下代々此地に在り、此處の伊豆志神社は天日槍を祀れるである。又天日槍を新羅の王子とするも、新羅の建國は崇神天皇の三十七年、漢の宣帝五鳳元年にて、尚甚だ後世のことである)
大和建国時代
神武天皇即位前三年、大和の賊八十梟師(一群の夷族の長)を討平の際、推根津彥及び弟猾等に命じ天の香具山(大和國磯城郡香久山村戒下)の埴土を探りて、平迦(淺き瓮)八拾個、手抉(手指を以て剔抉せる小壺) 八拾個及び厳瓮(酒殿にて神酒を醸す甕或は祭神の酒器ともいふ)等を造らしめた。
祝部土器
之が齋瓮(伊波比閇又祝部或は祝瓶の土器)即ち忌部(忌)の始にて、胎土は灰色茶褐色とあり。最初の陶質は埴土物なりしならんも、後には彌生式よりも稍堅固なる須惠母となりし如く。そして焼成されし火度は九百度より千百度のものにてあり、之が王朝より平安朝まで繼續された物である。
徐福の帰化
孝霊天皇七十二年秦の始皇帝は、道士徐福に命じて東方蓬莱國に不老不死の霊薬を求む可く派遣した。それは男女五十八人大船四十八艘に分乗し、米穀金帛數萬石を搭載して紀伊國熊野浦に着きしが、其齎らせる中に數種の焼物があり、又陶師ありて、茲に支那直傳の陶法を享けし口傳された。そして此陶師の子孫が陶を姓氏とする者の祖といはれてゐる。
垂仁天皇の二十八年十月五日、皇弟倭彥命薨せらるゝや、十二月二日命を葬るに當り、近習者の悉くを其陸域に生埋めにして甚だ惨状を極めしかば、天皇乃ち詔して爾後殉死を禁せられた。
野見宿禰の埴輪
而して同三十二年七月六日皇后日葉酢媛薨去せらるゝに及び、出雲の人野見宿稲の建策を容れ給ひ、殉死に代ふるに埴土を以つて人偶像を造り焼き、そして墓陵を繞り半ば地に埋めて輪の如く樹て列ねしより、之を埴輪又立物と稱するに至つた。
土師職を置く
天皇之より土師の職を置きて諸國に製陶の地を定め、宿禰をして土師の長たらしめ給ふ。彼は出雲の土師(陶工)一百人を大和へ連れて埴輪を製作した。之より製陶地を出雲、備前、大和、河内、和泉、伊勢、近江、但馬、阿波、讃岐、淡路、播磨、筑前の十三ヶ國に定められしが、更に又山城、攝津、尾張、三河、美濃、上野、下野、丹波、因幡、周防、長門、筑後の十二ヶ國を加へて二十五ヶ國に土師職を置くこと成った。これ土師を姓とする者の濫觴である。
神前に人馬の像を建つ
景行天皇の御宇肥前國の山中(後の佐嘉郡)に、往來の人を暴殺する魔神ありて此地の大荒田大いに憂へるを、山田村(川上川の畔)の土蜘蛛(一種の夷族)大山田、狭山田の姉妹ありて建策するに、下田村(今の松梅村)の埴土を探りて大形なる人馬の像を造り、焼きて祠前に祀らば必ず神意を和らぐ可し。大荒田其言の如く行ひしに果して神鎮まるに至つた。これ本邦に於いて神前に人馬の像を建立せし最古の事と稱せらる。
【現代語訳】
日本神話の時代、天御中主神は海辺の砂に白いものが付着しているのを舐めて味を知り、真土を掘って土器を作り、それに海水を入れて火にかけ砂を煎ると塩が得られることを発見したと「開闢記」に記されている。
その後、素盞嗚尊が八岐大蛇を退治する際、毒酒を入れるために用いた八つの甕は、出雲の簸の川上で焼かせたものと伝わる。素盞嗚尊が朝鮮に赴いた時、すでに製陶の技術を会得していたと考えられる。やがて天忍穂耳尊が葦原の中つ国に降ると、筑紫は中国や朝鮮の影響を受け、製陶技術もそこから広まった。当時の陶芸は筑紫・出雲・大和の三方面から発展したとされる。
日本人が最初に用いた土器(土師器)は褐黄色で、丸底で高台がなく、無文が多く、焼成温度は600~700度ほどだった。これが弥生式土器、すなわち高天原土器と呼ばれるものである。
大国主神の時代には、大陶祇という人物が和泉国の茅渟の地で陶器を作ったと記されている。彼は大国主の舅であり、土地の豪族と伝えられる。この地は後に陶器の里「大鳥郡」と称された。
また、韓国から渡来した天日槍が近江に住んだとき、従者に陶工がいて焼物を作ったという伝承がある。彼は後に但馬に住み、伊豆志神社に祀られた。
神武天皇の建国時代には、戦いの際に命じて香具山の土を使い、浅い瓮や小壺、神酒を入れる甕などを作らせた。これが祝部土器であり、胎土は灰褐色で、焼成温度は900~1000度と高く、平安時代まで続いた。
孝霊天皇の時代、秦の始皇帝は徐福を東方に送り、不老不死の薬を求めさせたが、彼が紀伊に上陸した際、陶師を伴っており、中国直伝の製陶法が日本にもたらされたと伝えられる。
垂仁天皇の時代、殉死を禁止する代わりに野見宿禰が提案し、埴土で人形を作って墓に並べた。これが埴輪の始まりである。その後、天皇は土師の職を設け、諸国に製陶地を定めた。土師氏はこれを起源とする。
景行天皇の時代、肥前の山中で魔神を鎮めるため、土蜘蛛族が人馬の像を土で作り祠に祀った。これが日本で神前に人馬像を建立した最初の例とされる。
【英語訳】
In the age of the gods, Amenominakanushi discovered that the white substance adhering to seaside sand was salty when tasted. He made an earthen vessel from true clay, filled it with seawater, and boiled the sand in it, thus discovering the process of making salt, as recorded in the Kaibyaku-ki.
Later, when Susanoo defeated the eight-headed serpent, he used eight jars for poisoned sake, which were fired at the upper reaches of the Hi River in Izumo. It is believed he had already learned pottery techniques during his stay in Korea. After his son Ame-no-Oshihomimi descended to Ashihara-no-Nakatsukuni, Tsukushi came under Chinese and Korean influence, and pottery techniques spread. Pottery culture at that time developed from three regions: Tsukushi, Izumo, and Yamato.
The earliest pottery used by the Japanese was Haji ware: brownish-yellow, round-bottomed without stands, mostly undecorated, fired at 600–700°C. These are known today as Yayoi ware, or Takamagahara ware.
In the age of Okuninushi, a man named Ootogui in Chinu of Izumi Province made pottery, as recorded in the Kojiki. He was said to be Okuninushi’s father-in-law and a powerful local ruler. This area later became known as Otori District, famed for pottery.
The Korean prince Amenohiboko settled in Japan and lived in Omi, bringing potters who produced wares there. He later moved to Tajima, where the Izushi Shrine enshrines him.
During Emperor Jimmu’s reign, clay from Mount Kagu was used to produce vessels—shallow jars, small hand-shaped pots, and ritual sake jars—for ceremonies and offerings. These became known as Iwai-be vessels, fired at 900–1000°C, and continued in use until the Heian period.
In Emperor Kōrei’s reign, Qin Shihuang sent Xu Fu eastward in search of the elixir of immortality. Landing in Kii, he brought potters who transmitted Chinese techniques.
In Emperor Suinin’s time, human sacrifice was banned. Instead, Nomi-no-Sukune proposed making clay figurines to be buried around tombs. Thus began the haniwa. The emperor then established the Haji potters’ office, appointing Nomi-no-Sukune its head and designating pottery regions across the land, the origin of the Haji clan.
During Emperor Keikō’s reign, in Hizen, clay was taken from Shimoda and shaped into large clay images of men and horses to pacify a raging deity. This is regarded as the first instance in Japan of enshrining clay human and horse figures before a shrine.
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】
在日本神话时代,天御中主神发现海边砂上的白色物质有咸味,于是掘土制成土器,将海水倒入,加火煮砂,得到了盐。《开辟记》记载了此事。
后来,素盏鸣尊退治八岐大蛇时,所用的八个酒甕是在出云簸川上烧制的。据说他曾到过朝鲜,已掌握制陶技艺。其子天忍穗耳尊降临葦原中国后,筑紫受中国、朝鲜影响,制陶技术由此传播。当时的陶艺从筑紫、出云、大和三地兴起。
日本最早使用的土器是土师器,呈褐黄色,多为圆底、无高台、无纹饰,烧成温度约600~700度。这就是弥生式土器,即高天原土器。
在大国主神的时代,和泉国茅渟有大陶祇制作陶器,《古事记》有载。他是大国主的岳父,被视为陶艺始祖。该地后来被称为陶器之乡大鸟郡。
此时,来自韩国的天日槍归化,带来陶工,在近江烧制陶器,后迁居但马,伊豆志神社奉祀他。
神武天皇时期,战役中命人取香具山的土制作瓮、壶、祭器等。这些土器胎土灰褐,烧成温度高达900~1000度,延续至平安时期,被称为祝部土器。
孝灵天皇时,秦始皇派徐福东渡求仙药,登陆纪伊时带来陶工,传入中国陶法。
垂仁天皇时,废除殉葬,由野见宿禰提议改以陶人偶代替,这便是埴轮的起源。天皇设立土师职,指定各地制陶,土师氏由此起源。
景行天皇时,肥前有魔神为害,当地土蜘蛛族制人马陶像供奉神前,神意得以安抚。这是日本最早的神前人马像。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】
在日本神話時代,天御中主神發現海邊砂上的白色物質有鹹味,於是掘土製成土器,將海水倒入,加火煮砂,得到了鹽。《開闢記》記載了此事。
後來,
素盞鳴尊退治八岐大蛇時,所用的八個酒甕是在出雲簸川上燒製的。據說他曾到過朝鮮,已掌握製陶技藝。其子天忍穗耳尊降臨葦原中國後,筑紫受中國、朝鮮影響,製陶技術由此傳播。當時的陶藝從筑紫、出雲、大和三地興起。
日本最早使用的土器是土師器,呈褐黃色,多為圓底、無高台、無紋飾,燒成溫度約600~700度。這就是彌生式土器,即高天原土器。
在大國主神的時代,和泉國茅渟有大陶祇製作陶器,《古事記》有載。他是大國主的岳父,被視為陶藝始祖。該地後來被稱為陶器之鄉大鳥郡。
此時,來自韓國的天日槍歸化,帶來陶工,在近江燒製陶器,後遷居但馬,伊豆志神社奉祀他。
神武天皇時期,戰役中命人取香具山的土製作甕、壺、祭器等。這些土器胎土灰褐,燒成溫度高達900~1000度,延續至平安時期,被稱為祝部土器。
孝靈天皇時,秦始皇派徐福東渡求仙藥,登陸紀伊時帶來陶工,傳入中國陶法。
垂仁天皇時,廢除殉葬,由野見宿禰提議改以陶人偶代替,這便是埴輪的起源。天皇設立土師職,指定各地製陶,土師氏由此起源。
景行天皇時,肥前有魔神為害,當地土蜘蛛族製人馬陶像供奉神前,神意得以安撫。這是日本最早的神前人馬像。
【中国語訳(英語から簡体字)】
在神话时代,天御中主神发现海边砂上的白色物质有咸味,他制成土器煮海水,发现了盐的制作方法。
后来,素戔嗚尊在退治八岐大蛇时,用的八个酒甕是在出云簸川上烧制的。据说他在朝鲜时已学会制陶。其子天忍穗耳尊降临后,筑紫受中韩影响,陶艺从筑紫、出云、大和三地发展。
最早的陶器是土师器,褐黄色,圆底无高台,多数无纹,烧成温度约600–700度,即弥生式土器。
大国主时代,大陶祇在和泉国制作陶器,被视为陶艺始祖。
韩人天日槍归化时带陶工到近江,后迁居但马。
神武天皇时,用香具山的土制成祭器。祝部土器胎土灰褐,烧成900–1000度,延续到平安。
孝灵天皇时,秦始皇派徐福东渡,带来陶工。
垂仁天皇时,殉葬被废,野见宿禰改以陶偶,始有埴轮。土师氏的起源也在此。
景行天皇时,肥前以陶制人马像镇邪神,这是日本最早的神前人马像。
【中国語訳(英語から繁體字)】
在神話時代,天御中主神發現海邊砂上的白色物質有鹹味,他製成土器煮海水,發現了鹽的製作方法。
後來,素戔嗚尊在退治八岐大蛇時,用的八個酒甕是在出雲簸川上燒製的。據說他在朝鮮時已學會製陶。其子天忍穗耳尊降臨後,筑紫受中韓影響,陶藝從筑紫、出雲、大和三地發展。
最早的陶器是土師器,褐黃色,圓底無高台,多數無紋,燒成溫度約600–700度,即彌生式土器。
大國主時代,大陶祇在和泉國製作陶器,被視為陶藝始祖。
韓人天日槍歸化時帶陶工到近江,後遷居但馬。
神武天皇時,用香具山的土製成祭器。祝部土器胎土灰褐,燒成900–1000度,延續到平安。
孝靈天皇時,秦始皇派徐福東渡,帶來陶工。
垂仁天皇時,殉葬被廢,野見宿禰改以陶偶,始有埴輪。土師氏的起源也在此。
景行天皇時,肥前以陶製人馬像鎮邪神,這是日本最早的神前人馬像。