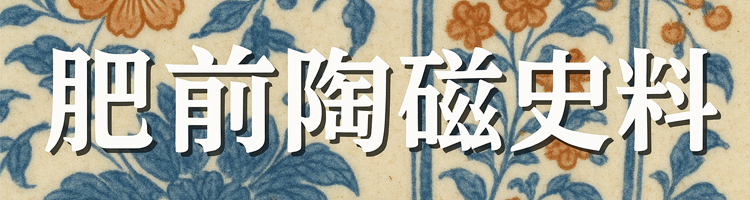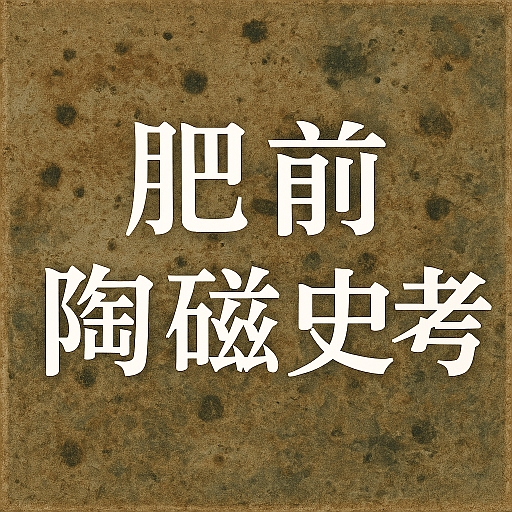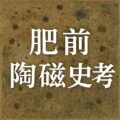【原文】
我邦民族の種別
我邦の陶史を記述するには、先づ有史以前の民族について、概念的にも其發祥を辿る可き必要が生じて来る。元來我が日本島國がもと亜細亜大陸の一端なりしことは、マンモスの如き動物の遺骨や、平戸野島のガマノセ貝發見等にても證明されしさころにて。幾萬年かの往古に於いて、地變の爲めに分離されて島國を形成せしものと見る可く、彼の隠岐や佐渡及壹岐、對馬の如きは其中間に残留して、水平線上に現はし小片であらう。或は海底火山が一旦陸起後、其一部が沈降したのかも知れぬ。
コロボックル人の縄文土器
而して新石器時代に於いて、最古の島民としてコロボックルと稱せらる、小人種が住ひしと傳へらるゝは、或はエスキモー人と同種かも知れぬが、此人種が製作せし遺陶とてコロボックル 縄紋土器(又縄目土器といふ)なる物がある。蓋し當時は未だ穀物の栽培を知らざる時代とて、勿論縄や藁などを用ひて印花せしものにはなく、天然植物の葛や撚蔓などを器の生乾きの際に巻きつけし如く見らるゝのである。
アイヌ人の渡来
次は四・五千年以前、間宮海峡を渡りて我邦に來りして稱せらるゝアイヌ人種に分布は本州の中國邊にまで延びてゐる。彼等は海岸や山間に住して狩獵及漁獵の外農耕の道を知らず、そして又土器を製して使用した。然るに其後渡せる人種の為に打破られて、奥州や北海道又は千島等へ退したのである。
貝塚土器
此アイヌ人の祖先が、其造りしころの土器を各地へ遺してゐる。それは北海道は勿輪中國は岩國邊まで及べるが、尚佐渡、伊豆、大島及初島等にも發見されたのである。此土器の胎色は褐色を呈し渦模様のある即ち貝塚土器と稱せらるゝ物にて、まづ六百五十度より七百五十度位に焼成されし物といはれてゐる。又國栖、蝦夷白み などの種族は、何れもアイヌに属する者との説がある。
ツングース人
次には北東西比利亞に任せしツングース人が渡した。此人種は古代支那の歴史に於いて、東胡或は匈奴と呼ばれし大民族にて、西比利亞より満洲に占據し、當時の支那を絶えず脅かして春秋戰國時代萬里の長城を築造せしめし種族である。そして是が先住民族とするところのであらう。
奥羽族
而して此種族の渡來に就いては三つの時期ありと稱せられ、第一はアイヌと共に間宮海峡を渡りて出羽や越後に住居せし者であり。―出雲族―第二は満洲方面にありし者が朝鮮に入り來り、其一部が日本海を渡って出雲の国を中心地として殖民せしところの出雲民族であるといはれてゐる。
天孫族
第三は大陸地方及朝鮮半島に殘留せし一民族が、對馬海峡を渡って九州に上陸し、日向地方を中心地として勢力を伸張せし者にて。第一第二の渡來族が古代史にいはゆる國津神にあたり最後に渡來せしものが 天孫族則ち天津神であらう。
此三つの種族は、狩猟、漁獵の外農耕生活に入、そして金屬使用時代に移りしものゝ如く。彼等は又アイヌと戦うて之を破り、且此種族を山間や奥地に追込んだのである。此三期の渡来族中、天孫族が最優秀なる智力を武力を有し、九州より東上して他族を征服して都を中國に定め、我が日本建國の基礎を築きしものにて―高天原土器―その大和橿原を中心として造りし彌生式土器が、則ち高天原土器と稱する物である。
苗族
次に我國へ渡せしは、支那の先住民たる苗族である。彼等は漢族の勃興の爲め印度支那方面へ驅逐されし者にて、此種族は土器を造るの外農業を知り、又青銅器の使用を解してゐた。而して斯族の一部が海路九州北部に渡り一社會を建設せし者の如く、そして彼等が我邦へ稻の栽培を齎らせし稱せらる。
隼人族
次には南洋方面より海潮に乗って渡來せしインドネシアン族にて、彼等は九州の南方に根據を据ゑ印度支那族とも長く闘争せし薩摩隼人の祖先である。―ネグリート族―次に渡せしは黒人系に旅するネグリートにて、印度より追はれて南洋に渡り一部が日本に漂着した。(短かい体軀の縮毛にて扁平なる鼻の所有者)是等の大部分は最初奴隷級にありしが如く、そして漸減少し絶滅せしと稱せらるゝも、今何其遺系の面貌を見ること少くない。
漢民族
次には漢民族(支那帝國の創立者)にて、我神武紀元前約千年以前に於いて、朝鮮北部に勢力を伸ばし樂浪 臨屯、玄苑、眞蕃等の一部が我邦に移入せし者である。以上の各人種關係より考察するも、當時我邦の製陶が各種の様式に於いて試みられことが推せらる。要するに我邦の焼物は、始め食器の外祭器(即ち齋瓮)として發祥せしものゝ如く、何れも素焼物にて其他は埴輪、陶棺の外、杯、皿、坩の如きがあり、此倭製土器の外に甕類などの朝鮮式土器があつた。又渦土器と稱するは須惠母乃に丸き木口を印花せし物である。後年河内の國府より發掘されし土器の如きは、三千年以前の遺物と鑑査されたのである。
【現代語訳】
日本の陶磁史を記すには、まず歴史以前に存在した民族の起源をたどる必要がある。日本列島がもともとアジア大陸の一部であったことは、マンモスの化石や平戸野島で発見されたガマノセ貝などによって証明されている。数万年前、地殻変動によって大陸から分かれて島国が形成されたと考えられる。隠岐・佐渡・壱岐・対馬などは、その過程で取り残され、水平線上に点在する小島となったのだろう。あるいは海底火山が一度隆起した後に一部が沈降したのかもしれない。
新石器時代には、最古の島民とされる小人種「コロボックル」が住んでいたと伝えられる。彼らはエスキモーに近い人々とも考えられており、縄文土器(縄目土器)を作った。これはまだ穀物栽培が知られていなかった時代であり、縄や藁で模様をつけたのではなく、葛や蔓など天然植物を乾きかけの器に巻き付けた跡とみられている。
その後、約四、五千年前に間宮海峡を渡ってアイヌ人が渡来し、本州の中国地方にまで広がった。彼らは狩猟や漁労を行ったが農耕は知らず、土器を製作して用いた。しかしのちに別の民族に圧迫され、奥州・北海道・千島などへ退いた。アイヌの祖先が残した土器は北海道から中国地方の岩国周辺、さらには佐渡・伊豆・大島・初島などでも発見されている。胎土は褐色で渦巻模様があり、650~750度程度で焼かれたと推定され、貝塚土器と呼ばれる。また、國栖や蝦夷白みなどの種族もアイヌ系とされる。
次に渡来したのはツングース人で、古代中国史において東胡や匈奴と呼ばれた大民族である。彼らは西シベリアから満洲にかけて勢力を持ち、中国を脅かし続け、春秋戦国時代には万里の長城を築かせた種族でもある。
このツングース系の渡来には三段階あったとされる。第一はアイヌとともに間宮海峡を渡って出羽・越後に住んだ人々、第二は満洲から朝鮮半島を経て出雲に殖民した出雲族、第三は朝鮮半島から対馬海峡を渡り九州の日向に上陸して勢力を広げた天孫族である。第一・第二の渡来民は国津神、最後に渡来した天孫族は天津神と伝えられる。彼らは農耕を営み金属を使用し、アイヌと戦ってこれを破り、山地や辺境へ追いやった。中でも天孫族は最も優れた知力と武力を持ち、九州から東へ進出して他族を征服し、中国地方に都を定め、日本建国の基礎を築いた。大和橿原を中心に造られた弥生式土器は「高天原土器」とも呼ばれる。
さらに中国の先住民族・苗族も渡来した。彼らは漢族の勃興によりインドシナ方面へ追われた民族で、土器を作り農業を営み、青銅器の使用も知っていた。その一部が海路で九州北部に渡来し、稲作を伝えたとされる。
次に南方から渡来したのがインドネシア系の民族で、九州南部に拠点を築き、インドシナ系と抗争した薩摩隼人の祖先である。さらにインドから追われ南洋に移ったネグリート人の一部も日本に漂着した。彼らは小柄で縮れ毛、扁平な鼻を持ち、多くは奴隷的な身分であったが、やがて減少し絶滅したといわれる。しかしその特徴は今なお一部に見られる。
次に渡来したのは漢民族で、神武紀元前およそ千年前に朝鮮北部へ勢力を広げ、楽浪・臨屯・玄菟・真番の一部が日本に移住した。これらの交流から推しても、当時日本の製陶はさまざまな様式で試みられていたと考えられる。日本の焼物は当初、食器のほか祭祀用の斎瓮として発祥したもので、いずれも素焼きであった。他には埴輪・陶棺・杯・皿・坩などがあり、倭製土器のほかに朝鮮式土器の甕類もあった。渦土器と呼ばれるものは、須惠母乃で丸木の口縁を押して模様をつけたものである。河内の国府から出土した土器の中には、三千年前の遺物と鑑定されたものもある。
【英語訳】
To describe the history of Japanese ceramics, one must first trace the origins of the peoples who lived before recorded history. The Japanese archipelago was originally part of the Asian continent, as proven by discoveries such as mammoth fossils and Gamano-se shells on Hirado Nojima. Tens of thousands of years ago, tectonic shifts caused the land to separate, forming the islands. Oki, Sado, Iki, and Tsushima remained as fragments on the horizon, perhaps due to undersea volcanoes that rose and later partially sank.
In the Neolithic period, the earliest island inhabitants were said to be the small-statured Korobokkuru, possibly related to the Eskimos. They created Jomon pottery, known as cord-marked ware. Since agriculture was not yet known, the impressions were not made with ropes or straw but with vines and natural plants wrapped around the clay when still damp.
Around four to five thousand years ago, the Ainu crossed the Strait of Mamiya and spread as far as central Honshu. They hunted and fished but did not farm, and they also produced pottery. Later, they were driven northward into Tohoku, Hokkaido, and the Kuril Islands. Their pottery, known as shell mound ware, has been found from Hokkaido to Iwakuni, as well as Sado, Izu, Oshima, and Hatsushima. It was brownish with spiral patterns, fired at about 650–750°C. Some tribes such as Kusu and certain Emishi groups are thought to have been Ainu-related.
The Tungusic people later arrived from northeastern Siberia. Known in ancient Chinese history as Donghu or Xiongnu, they were a great people who occupied Manchuria and threatened China, even prompting the construction of the Great Wall during the Spring and Autumn and Warring States periods.
Their migrations into Japan are said to have occurred in three waves: first with the Ainu into Dewa and Echigo, second from Manchuria via Korea into Izumo (the Izumo people), and third across the Tsushima Strait into Kyushu (the Tenson tribe, or descendants of Amatsukami). These groups introduced agriculture and metal use, fought the Ainu, and drove them into remote areas. Among them, the Tenson were the most advanced, conquering other tribes, establishing a capital in central Japan, and laying the foundation for the Japanese nation. The Yayoi-style pottery produced around Kashihara in Yamato is known as Takamagahara ware.
Later, the Miao people, indigenous to China, arrived. Driven southward by the rise of the Han Chinese, they already knew farming and bronze technology. Some crossed by sea to northern Kyushu, bringing rice cultivation.
The Indonesian peoples followed, arriving on ocean currents and settling in southern Kyushu. They became the ancestors of the Satsuma Hayato, who long fought with other groups. The Negritos, small-statured people with curly hair and flat noses, also drifted to Japan after being driven out of India into Southeast Asia. Many were initially slaves, later diminishing in number and said to have vanished, though traces remain in some features today.
The Han Chinese came next, around one thousand years before the Jimmu era, expanding into northern Korea. Groups from Lelang, Lintun, Xuantu, and Zhenfan migrated into Japan. From these contacts, it is clear that Japanese pottery developed in many styles. Early Japanese ceramics were primarily unglazed ritual vessels (such as saihe) and tableware. Other forms included haniwa, ceramic coffins, cups, plates, and crucibles. Alongside native Japanese pottery, Korean-style jars also existed. Spiral-patterned pottery, made by impressing round wooden edges, has also been found. Some excavated pieces from Kawachi have been dated to over three thousand years ago.
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】
要讲述日本的陶瓷史,必须首先追溯史前民族及其起源。日本列岛原本是亚洲大陆的一部分,这一点从猛犸象化石和平户野岛发现的ガマノセ贝中可以得到证明。数万年前,地壳变动使
日本从大陆分离,形成了岛国。隐岐、佐渡、壹岐、对马等岛屿,是当时残留下来的碎片。也可能是海底火山隆起后部分沉没的结果。
在新石器时代,最早的岛民是被称为“コロボックル”的小个子民族,可能与爱斯基摩人同源。他们制作了绳文土器(绳纹土器),并不是用绳索或稻草压印,而是用葛藤等天然植物缠绕在半干的陶坯上形成纹样。
约四、五千年前,阿伊努人渡过间宫海峡来到日本,分布到本州中部。他们以狩猎、捕鱼为生,不知农业,也制作并使用陶器。但后来被其他民族击退,退入奥州、北海道和千岛。阿伊努人留下的陶器遍布北海道到中国地方的岩国,佐渡、伊豆、大岛、初岛等地也有出土。这些陶器胎土呈褐色,饰有涡纹,烧成温度约650~750度,被称为贝冢土器。
随后,来自西伯利亚东北的通古斯人渡来。古代中国称他们为东胡或匈奴,是占据满洲的大民族,曾威胁中原,使春秋战国时期修建了万里长城。
通古斯人的渡来有三次:第一次是与阿伊努人一同经间宫海峡到达出羽、越后;第二次是由满洲经朝鲜渡海到达出云的出云族;第三次是从朝鲜半岛经对马海峡到达九州的天孙族(天津神)。他们开始农业和金属使用,并与阿伊努作战,将其驱入山区。三者之中,天孙族最为强盛,东进征服他族,在中国地方建立都城,奠定了日本建国的基础。其中心在大和橿原制造的弥生式土器,被称为“高天原土器”。
后来,中国的苗族也渡来。他们因汉族崛起被逐往印度支那,懂得农业与青铜器制造,其中一部分海路到达九州北部,并将稻作带入日本。
再后来,印尼系民族乘海潮到来,定居于九州南部,成为萨摩隼人的祖先。被逐出印度的尼格利陀人(矮小、卷发、扁鼻)也有一部分漂到日本,多数沦为奴隶,逐渐减少而绝灭,但其遗貌至今仍可见。
最后是汉民族,大约在神武纪元前千年进入朝鲜北部,部分乐浪、临屯、玄菟、真番人迁入日本。从这些交流可见,当时日本陶器已有多样化的样式。最初的陶器主要是食器和祭祀用的斋瓮,均为素烧,此外有埴轮、陶棺、杯、盘、坩等。除倭制土器外,还有朝鲜式陶器。所谓涡土器,是用圆木口印压而成的纹饰。后来在河内国府出土的土器,经鉴定为三千年前的遗物。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】
要講述日本的陶瓷史,必須首先追溯史前民族及其起源。日本列島原本是亞洲大陸的一部分,這一點從猛獁象化石和平戶野島發現的ガマノセ貝中可以得到證明。數萬年前,地殼變動使日本從大陸分離,形成了島國。隱岐、佐渡、壹岐、對馬等島嶼,是當時殘留下來的碎片。也可能是海底火山隆起後部分沉沒的結果。
在新石器時代,最早的島民是被稱為「コロボックル」的小個子民族,可能與愛斯基摩人同源。他們製作了繩文土器(繩紋土器),並不是用繩索或稻草壓印,而是用葛藤等天然植物纏繞在半乾的陶坯上形成紋樣。
約四、五千年前,阿伊努人渡過間宮海峽來到日本,分布到本州中部。他們以狩獵、捕魚為生,不知農業,也製作並使用陶器。但後來被其他民族擊退,退入奧州、北海道和千島。阿伊努人留下的陶器遍布北海道到中國地方的岩國,佐渡、伊豆、大島、初島等地也有出土。這些陶器胎土呈褐色,飾有渦紋,燒成溫度約650~750度,被稱為貝冢土器。
隨後,來自西伯利亞東北的通古斯人渡來。古代中國稱他們為東胡或匈奴,是佔據滿洲的大民族,曾威脅中原,使春秋戰國時期修建了萬里長城。
通古斯人的渡來有三次:第一次是與阿伊努人一同經間宮海峽到達出羽、越後;第二次是由滿洲經朝鮮渡海到達出雲的出雲族;第三次是從朝鮮半島經對馬海峽到達九州的天孫族(天津神)。他們開始農業和金屬使用,並與阿伊努作戰,將其驅入山區。三者之中,天孫族最為強盛,東進征服他族,在中國地方建立都城,奠定了日本建國的基礎。其中心在大和橿原製造的彌生式土器,被稱為「高天原土器」。
後來,中國的苗族也渡來。他們因漢族崛起被逐往印度支那,懂得農業與青銅器製造,其中一部分海路到達九州北部,並將稻作帶入日本。
再後來,印尼系民族乘海潮到來,定居於九州南部,成為薩摩隼人的祖先。被逐出印度的尼格利陀人(矮小、卷髮、扁鼻)也有一部分漂到日本,多數淪為奴隸,逐漸減少而絕滅,但其遺貌至今仍可見。
最後是漢民族,大約在神武紀元前千年進入朝鮮北部,部分樂浪、臨屯、玄菟、真番人遷入日本。從這些交流可見,當時日本陶器已有多樣化的樣式。最初的陶器主要是食器和祭祀用的齋瓮,均為素燒,此外有埴輪、陶棺、杯、盤、坩等。除倭製土器外,還有朝鮮式陶器。所謂渦土器,是用圓木口印壓而成的紋飾。後來在河內國府出土的土器,經鑑定為三千年前的遺物。
【中国語訳(英語から簡体字)】
要描述日本陶瓷史,必须首先追溯史前民族的起源。日本列岛原本是亚洲大陆的一部分,这一点从猛犸象化石和平户野岛发现的ガマノセ贝可见一斑。数万年前,地质变动使土地分离,形成岛国。隐岐、佐渡、壹岐、对马等岛屿是残留的碎片,可能是海底火山隆起后部分下沉的结果。
新石器时代,最早的居民是小个子民族コロボックル,可能与爱斯基摩人有关。他们制作了绳文土器,用藤蔓等天然植物在半干的陶器上留下印痕。
约四五千年前,阿伊努人渡过间宫海峡进入日本,分布到本州中部,从事狩猎和捕鱼,也制作陶器,但被其他民族击退,退居北方。阿伊努遗留的陶器发现于北海道、岩国、佐渡、伊豆等地,呈褐色,有螺旋纹,烧成温度650–750度。
通古斯人随后渡来,被中国史书称为东胡或匈奴,威胁中原并导致万里长城的修建。他们三度进入日本,形成出羽、出云和天孙族。天孙族最强,征服他族,建立政权,并制作弥生土器,被称为高天原土器。
苗族后来渡来,带来稻作与青铜器。印尼人定居九州南部,成为萨摩隼人祖先。尼格利陀人漂到日本,部分为奴隶,逐渐灭绝,但特征仍存在。
汉族约在神武纪元前千年扩展至朝鲜,并有部分迁入日本,促进陶器多样化。早期陶器以素烧为主,用于祭祀与日常器具,此外还有朝鲜式陶器与涡纹土器,部分出土器物被鉴定为三千年前。
【中国語訳(英語から繁體字)】
要描述日本陶瓷史,必須首先追溯史前民族的起源。日本列島原本是亞洲大陸的一部分,這一點從猛獁象化石和平戶野島發現的ガマノセ貝可見一斑。數萬年前,地質變動使土地分離,形成島國。隱岐、佐渡、壹岐、對馬等島嶼是殘留的碎片,可能是海底火山隆起後部分下沉的結果。
新石器時代,最早的居民是小個子民族コロボックル,可能與愛斯基摩人有關。他們製作了繩文土器,用藤蔓等天然植物在半乾的陶器上留下印痕。
約四五千年前,阿伊努人渡過間宮海峽進入日本,分布到本州中部,從事狩獵和捕魚,也製作陶器,但被其他民族擊退,退居北方。阿伊努遺留的陶器發現於北海道、岩國、佐渡、伊豆等地,呈褐色,有螺旋紋,燒成溫度650–750度。
通古斯人隨後渡來,被中國史書稱為東胡或匈奴,威脅中原並導致萬里長城的修建。他們三度進入日本,形成出羽、出雲和天孫族。天孫族最強,征服他族,建立政權,並製作彌生土器,被稱為高天原土器。
苗族後來渡來,帶來稻作與青銅器。印尼人定居九州南部,成為薩摩隼人祖先。尼格利陀人漂到日本,部分為奴隸,逐漸滅絕,但特徵仍存在。
漢族約在神武紀元前千年擴展至朝鮮,並有部分遷入日本,促進陶器多樣化。早期陶器以素燒為主,用於祭祀與日常器具,此外還有朝鮮式陶器與渦紋土器,部分出土器物被鑑定為三千年前。