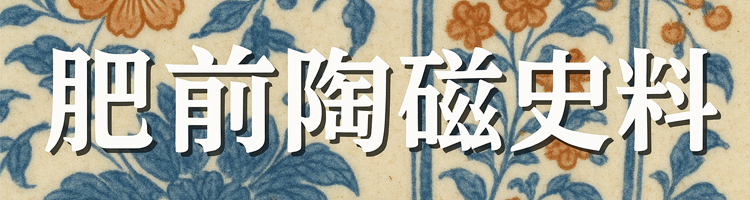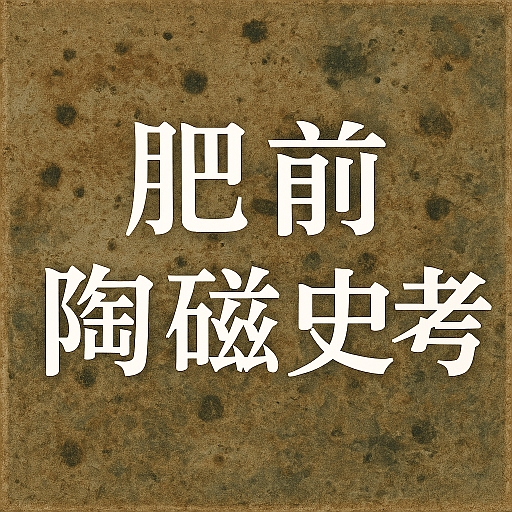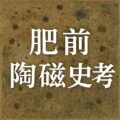【原文】
原始人と土器
抑人類が青銅器時代より以前に於て、土器を造り創めたることは頗る遠きものゝ如く、今之を考察するに、初期古石器時代のネアンデルタール人の長き元始生活漸く終り。クロマニヨン人種や、グリマルデイス人種の後期古石器時代に至り、絵書と彫刻の技能は稱見る可き遺物の發見さるゝも、土器に至つては只粘土を捏ねて何かの塑像を造り、之を天日に乾燥せものゝ如く、所謂古代アーセンウエアを稱する物の外嘗て焼成されし遺物を発見せぬ。
新石器時代
次の馴鹿人種(オーリニヤセアン時代ソリュトリアン時代マグダニアン時代)を經て、アズイリヤン乃ち地中海イベリアス人種の新石器時代に至り、漸く土器を焼くことを創見せしもの如く、今より殆と二萬五千年乃至一萬二千年以前のことゝいはれてゐる。
原始人火を造る
蓋し燧石を應用せしは、ハイデルベルグ人より始まるとの説に従へば、土器創作は前記の年代より尚繰上ぐ可きやも計られぬ。此原始人が物と物との摩擦に因つ始めて火を造り出せし大發見は、彼等に大なる驚異と歓喜でありしに相違ない。次には其火を用ひて火食を知り始め、従つて飲食器の必要に騙られし境遇を考察するに、彼等が土を以て土器を焼くに至りしこさは當然の歸結である。
原始人の土器焼成
此必要が發見の母となり、最初は土を水にて捏ね手捻りにて物を造り、それを天日に乾かせしうちに。或機會に之が火に焼けし爲に堅くなることを発見した。更に好奇心は爾來色々と工夫を凝らし、始めは開放氣中におつ冠せる薪の熱を用ひて焼固めしものと推考さる。又我邦の彌生式土器などは、製器を地上に据ね其上に砂を以って掩ひ匿くし、四方より燃料を積み重ねて焼上げしものさいはれてゐる。
次には地面を掘り凹め、周園に垣石を築きて焼きしかも知れぬが、未だ陶窯を築くことを識らぬ時代の粗製品なるを以って、火度弱くして破損し易く。又釉薬(上藥、わくすりといふアルミナを含有する硝子の如きもの)を施さざる為に其器に液体を盛れば之が浸潤し、或は中なる食物の調味に變化を來すの止むを得なかつた。
焼物の窯
漸く後代に於て工夫されしは、斜面の土地に細長く穴を掘り、天井だけをを苆を離せし練土にてアーチ形に構造されし窖窯なるものであつた。蓋し之が焼物窯の鼻祖であらう。(又大窯及鐵砲窯など稱するは此型らしく、鎌倉、足利時代の有名なる陶器は多く此窯式にて焼かれてゐる)或は其室内を四五間に仕切りし長窯が出来、又丸窯の連鎖せる登窯が構成され、後年に至つて竪窯や徳利窯及びトンネル窯など種々の様式が築造されたものである。
原始人の成形法
又最初の焼物成形法は、壺や甕の如き立体器を作るには、棒に縄を巻き太めて其上に粘土を押し當てがひ、成器稍乾燥せる頃縄の中心より解き出す古代の朝鮮式があり。又粘土を紐狀に細長く続伸してそれを螺旋状に巻き重ね而して後其上を手工せる紐造りの手法などありしものゝ如く。後には轆轤の使用が発見されてそれが手車と蹴車とに別れ或は押型や石膏型込法又は動力廻轉機等が應用さるに至ったのである。
釉薬の創始
而して此容器に、外面より浸入する水分の吸収を防ぎ、旦光滑なる外被を纏はす釉藥の施さるゝまでには長き歳月を經しものゝ如く本場の支那に於てさへ六朝時代より創始されして言傅へられてあり。そして又當時の施釉物称せられし彼祝部土器の如きも、質は人工的に塗飾せしものといはれてゐる。
此施釉法の最初の發見は、或時窯入れせし器に窯内の降灰が附着して、それが高熱にて焼上げらし爲に、器の表面に化學的變化を起して硝子狀の被覆物が生じたのである。此偶然の出来事より灰を混じて釉薬を施す方法が創見されたので、即ち釉質が灰を混すれば、素地料にアルカリ性の熔媒を加へて熱に解け易きことが模索的に知得さるるに至ったのである。
焼物の進歩
斯くて赤褐色の氣孔に富める軟質土器より、青色に焼締られし陶器となり。次には光滑なる釉薬が施され、或は水分を吸収せぬ炻器となり。途には堅牢美麗なる磁器にまで進歩せしものである。なほ此上には近來日本陶器會社に試みられ超硬質磁器が、普及的に製作さるゝ時代が来らねばならぬ。
而して磁器の焼成火度は、ゼーゲル三角錐熟度計八番より拾六番、即ち攝氏千二百五十度より千四百六十度の範圍と稱せらるゝも、最硬質なる有田焼に於て千三百七十度乃至四百度以内といはれてゐる。要するに日用の器具としては出来得る丈け高火度の磁器が必要である。蓋しそれは原料の耐火性と、燃料の低價方法が經濟的に研究された後であらう。
尤も装飾用器に至つては、或程度の陶質にて足りる而已ならず、製作上に於いても軟陶の方が彩色や彫刻等凡て意の儘に焼成し得る便利がある。硬磁を焼くには無論高火度を要する丈け破損物の生すること多く、且釉下の發色が稀薄となり或は全く失色する彩料がある。故に磁器は青花(染附といふ)を主彩とするも、陶器に比して釉色の單調なるを以て、一度焼成されし器に何彩色を補ふ可く、―上繪附―茲に上繪附(赤繪附又錦附或は繪附)なるものが發達せしものであらう。
凡べて社會の進歩が單純より複雑となるが如く往古の焼物は全く單調の無釉土器であつた。故に此時代酒盃の如きも甚だしく水分を吸収するを以て、手早く之を飲み干されしものと謂はれ。又大内の御器や神社の祭器などは、毎にうち棄てらしものにて全くの清器に相違ない。而して印度に於いても、食物の腐敗し易き氣節の關係より素焼物の一度使用を習慣とせしを以て、此地の製陶人類と焼物製作はに進歩を見ざりしといはれてゐる。
全世界の製陶
此焼物製作は、全世界人類の棲息せしところ、何れの國も古くより行はれしと見る可く。古代アッシリヤ(亞細亞の古代王國)の涙の壺を始め、埃及や希臘に於ける古蹟より、可成り精巧なる土器が發掘さるゝこと珍らしくない。支那は燧人氏(我神武紀元前二千百二十年頃則ち神農氏也)の時始て火食を行ひしと傳へらるゝは、此時代既に土器を用ひし事を立證すべきであらう。
焼物と人類
佛人ルーイ・ギュエーの「焼物は人と共に生れたる物なり」と謂ひし如く、各國其製技の進歩に就いては遅速巧拙ありとするも、何れの種族も其生活の必要に駆られて焼物を造りしことは疑ふの地なく。而して此製陶の進歩及作風によりて有史以前の人類が生活程度を考証し。又後代に於いても發掘されし殘缺を観て、其時代の文化を考察するに重大な役目を持つてゐるのである。
【現代語訳】
人類と焼物の歴史
■ 原始人と土器
人類が青銅器時代より前に土器を作り始めたのは非常に古いことのようです。考えてみると、初期旧石器時代に長い原始生活を送ったネアンデルタール人の時代が終わり、クロマニョン人やグリマルディ人が現れた後期旧石器時代になると、絵画や彫刻の優れた遺物は見つかっています。しかし土器に関しては、粘土をこねて像を作り、天日に乾かしただけの、いわゆる古代のアルセンウェア以外に、焼成されたものは発見されていません。
■ 新石器時代
その後、オーリニャシアン時代・ソリュトリアン時代・マグダレニアン時代を経て、アズィリアン、すなわち地中海イベリア人の新石器時代になると、ようやく土器を焼くことが始まったと考えられています。これは今から約2万5千年から1万2千年前のことだといわれています。
■ 原始人と火
火打石を使ったのはハイデルベルク人から始まるという説に従えば、土器作りの始まりはさらに古くさかのぼる可能性があります。原始人が摩擦によって火を生み出したのは大発見で、彼らにとって大きな驚きと喜びだったに違いありません。その後、火を使って食べ物を調理することを覚え、飲食器の必要性に迫られる中で、粘土を焼いて器を作るようになったのは自然な流れです。
■ 原始人の土器焼成
必要は発明の母であり、最初は水で練った土を手で形作り、天日で乾燥させていました。あるとき偶然火に当たり堅くなることを発見しました。さらに好奇心から改良が進み、当初は野焼きのように薪の熱で焼き固めたと考えられています。我が国の弥生式土器も、器を地上に置き、砂をかぶせて隠し、その周囲に燃料を積んで焼いたといわれています。やがて地面を掘り下げて囲い石を設けて焼く方法も考えられました。しかし、まだ窯を築くことを知らなかったため、火力は弱く壊れやすく、また釉薬がなかったため、水分がしみ込み、食物の味を変えてしまうことも避けられませんでした。
■ 窯の発明
その後、斜面に細長い穴を掘り、粘土で天井をアーチ状にした「窖窯(あながま)」が工夫されました。これが焼物窯の起源といえるでしょう。大窯や鉄砲窯と呼ばれるものもこの型に属し、鎌倉・足利時代の名陶の多くはこの窯で焼かれました。さらに内部を区切った長窯、丸窯を連ねた登窯、のちには竪窯や徳利窯、トンネル窯など様々な様式が発展しました。
■ 成形法
初期の成形法としては、縄を棒に巻き、その上に粘土を押しつけて壺や甕を作る朝鮮式の方法や、粘土を紐状に伸ばして螺旋状に重ねる「紐作り」がありました。後には轆轤(ろくろ)が発明され、手回しと蹴ろくろに分かれ、さらに押型や石膏型、動力機械も使われるようになりました。
■ 釉薬の始まり
器に水が染み込まないようにし、光沢を与える釉薬の使用が始まるまでには長い年月がかかりました。中国でも六朝時代に始まったと伝えられています。きっかけは窯の中で灰が器に付着し、高温で焼かれてガラス状の層ができたことでした。そこから灰を混ぜて釉薬を作る方法が発見され、アルカリ性の溶媒を加えると熱で溶けやすいことが理解されるようになりました。
■ 焼物の進歩
こうして赤褐色の軟質土器から、焼き締められた陶器、釉薬をかけた器、さらに吸水しない炻器、やがて堅牢で美しい磁器へと発展しました。近代には日本陶器会社で超硬質磁器の製作も試みられました。磁器の焼成温度は摂氏1250度から1460度とされ、有田焼は1370~1400度ほどです。日常器具には高火度の磁器が望まれますが、それには原料の耐火性と燃料の経済性が研究される必要があります。装飾用には軟陶のほうが彩色や彫刻がしやすく便利です。磁器は高温のため失敗も多く、彩料が発色しにくいので、青花(染付)が主流となり、さらに赤絵や錦手などの上絵付が発達しました。古代の焼物は無釉の単調な土器で、水を吸いやすいため、盃などは一気に飲み干したと伝えられます。神社の祭器も毎回使い捨てで清浄を保ちました。インドでも気候のため素焼の器を一度だけ使う習慣があり、焼物の発展は見られませんでした。
■ 世界各地の製陶
焼物は世界中で古くから作られており、古代アッシリアの「涙の壺」、エジプトやギリシャの遺跡からも精巧な土器が出土します。中国でも燧人氏(神武紀元前2120年頃、神農氏の時代)が火を使い始めたと伝えられ、当時すでに土器が用いられていた証拠といえるでしょう。
■ 焼物と人類
フランス人ルーイ・ギュエーは「焼物は人と共に生まれた」と述べました。各国で進歩の速さや技術の巧拙に違いはあれど、どの民族も生活の必要から焼物を作ったことは疑いありません。製陶の発展や作風から、先史時代の人類の生活水準を考察することができ、また後世の発掘品から当時の文化を知る大きな手がかりとなっています。
【英語訳】
The History of Pottery and Humanity
■ Primitive Humans and Pottery
Humanity began making pottery long before the Bronze Age. During the late Paleolithic era, when Cro-Magnons and Grimaldians thrived after the Neanderthals, remarkable cave paintings and sculptures were created. However, no fired pottery has been found from this period, only clay figurines dried in the sun, known as ancient Arsenware.
■ The Neolithic Era
Through the Aurignacian, Solutrean, and Magdalenian periods, pottery-making truly began during the Azilian (Mediterranean Iberian) Neolithic era, around 25,000 to 12,000 years ago.
■ Fire and Early Potters
If the use of flint dates back to Heidelberg Man, pottery making may have started even earlier. The discovery of fire by friction was revolutionary, allowing humans to cook food. This in turn created the need for vessels, leading naturally to the invention of fired pottery.
■ Firing Techniques
At first, clay was shaped by hand and dried in the sun. Accidentally, pieces hardened when exposed to fire. Curiosity led to controlled firing, initially with open bonfires. In Japan, Yayoi pottery was fired by placing vessels on the ground, covering them with sand, and surrounding them with fuel. Later, pits with stone linings were used, though weak fires and the absence of glaze made these wares fragile and porous.
■ Kiln Development
Eventually, long pit kilns with arched clay roofs were devised. These were the ancestors of true kilns. Large kilns and “teppō-gama” (cannon kilns) followed, producing famous wares of the Kamakura and Ashikaga periods. Further developments included long kilns, linked round climbing kilns, and later vertical, bottle-shaped, and tunnel kilns.
■ Shaping Methods
Early shaping methods included wrapping clay around cords to form jars, or coiling clay strips. Later, the potter’s wheel appeared, with hand-turned and kick-wheels, followed by molds, plaster casting, and mechanical wheels.
■ The Invention of Glaze
Glazes, which prevent water absorption and give a glossy finish, appeared much later. In China, glazing began around the Six Dynasties. It likely originated when ash fell onto vessels in the kiln and melted into a glassy surface. This discovery led to mixing ash with clay, realizing that alkaline fluxes allowed easier melting.
■ Progress of Pottery
Thus, pottery evolved from porous reddish earthenware, to ceramic stoneware, glazed ware, and finally durable porcelain. Modern Japanese companies have even attempted ultra-hard porcelains. Porcelain requires firing between 1250°C and 1460°C, with Arita ware typically fired at 1370–1400°C. High-fired wares are preferable for daily use, though softer ceramics are easier for decoration. Because porcelain is fired at high temperatures, many pigments fade, making blue-and-white underglaze (sometsuke) dominant, with overglaze enamels (akae, kinrande) developing later. Ancient unglazed wares absorbed water quickly, so drinking cups were drained at once, and ritual vessels were discarded after use to maintain purity. In India, climate led to single-use earthenware, limiting ceramic development.
■ Pottery Worldwide
Pottery was made wherever humans lived. Finds include Assyrian “tear vases,” Egyptian and Greek artifacts, and Chinese traditions tracing fire use to Suiren-shi (c. 2120 BCE). These attest to the universality of pottery.
■ Pottery and Humanity
As French scholar Louis Guey said, “Pottery was born with mankind.” Though the pace and refinement varied, all peoples made pottery out of necessity. The evolution of pottery reveals much about prehistoric life and later cultural levels through excavated remains.
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】
人类与烧物的历史
■ 原始人与土器
在人类进入青铜器时代之前,就已经开始制作土器。这可以追溯到很久以前。到了旧石器时代晚期,尼安德特人的生活逐渐结束,出现了克罗马农人和格里马尔迪人。他们留下了绘画和雕刻的遗物,但土器方面,仅发现用粘土捏成并在阳光下晒干的像,即所谓古代“阿尔森器”,并没有发现真正烧成的陶器。
■ 新石器时代
经过奥里尼亚文化、索吕特文化、马格达林文化,进入阿兹利文化(地中海伊比利亚人)的新石器时代,人类才开始真正烧制土器。据说距今约2万5千年至1万2千年前。
■ 火与原始人
如果火打石的使用始于海德堡人,那么土器的制作可能还要更早。原始人通过摩擦生火,这是划时代的大发现,让他们学会了烹饪。这种需求促使他们制作饮食器皿,用火烧制粘土成为必然结果。
■ 烧制方法
最初,人们只是将粘土手工捏成形,放在阳光下晾干。偶然之间,器物在火中被烧硬。后来人们有意用木柴加热,逐渐发展出烧制方法。在日本,弥生式土器是将器物放在地上,用砂覆盖,然后在四周堆放燃料烧制的。再后来,人们在地上挖坑,用石块围起来进行烧制。但因为没有窑,火力不足,器物容易破裂,而且没有釉药,水分渗入后会影响食物的味道。
■ 窑的出现
后来,人们在斜坡上挖长坑,用粘土拱成顶,这就是最早的“穴窑”。这可以说是陶窑的鼻祖。之后出现了大窑、铁炮窑,镰仓和足利时代的名陶多用此类窑烧制。再后来,有分隔室的长窑、串联的圆窑“登窑”,以及竖窑、德利窑和隧道窑等多种样式。
■ 成型方法
最早的成型方法包括将绳子绕在棒上,再贴上粘土制成壶罐,或将粘土搓成长条,螺旋状盘绕堆叠,称为“盘筑法”。后来出现了陶轮,包括手工轮和脚踏轮,之后又有模具、石膏模和动力机。
■ 釉药的起源
为了防止水分渗入,并使器物表面光滑,釉药的出现经历了漫长时间。在中国,据说始于六朝时期。当时窑灰落在器物上,高温烧成后在表面形成玻璃状层,由此启发了釉药的发现。后来人们加入草木灰,逐渐理解到加入碱性助熔剂能使其更易熔化。
■ 烧物的发展
于是,陶器从红褐色的软质土器,发展为致密的陶器,继而出现施釉器、吸水性低的炻器,最终发展成坚硬美丽的瓷器。近代日本还尝试制造超硬质瓷器。瓷器的烧成温度在1250℃至1460℃之间,有田烧一般在1370~1400℃。日用品最好采用高温烧成的瓷器,但这需要耐火原料与经济燃料。装饰品则软陶更便于彩绘和雕刻。瓷器因高温烧制,失败率高,部分釉下彩料褪色,因此以青花为主,后来发展出赤绘、锦手等上彩。古代的无釉土器会大量吸水,酒杯需一口饮尽。祭祀器皿则多为一次性使用。印度因气候炎热,也习惯使用一次性素烧器,因此烧物未有大发展。
■ 世界的制陶
世界各地都自古制作陶器。古代亚述的“眼泪瓶”、埃及和希腊遗迹中都有精巧的陶器出土。中国相传燧人氏在神农时代开始用火,这也证明当时已有土器使用。
■ 烧物与人类
法国人路易·吉埃说过:“烧物与人类一同诞生。”各国的发展速度和水平不同,但出于生活需要,各民族都制作陶器。通过制陶的进步和风格,可以推测史前人类的生活水平,而后世的出土器物则成为研究当时文化的重要依据。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】
人類與燒物的歷史
■ 原始人與土器
在人類進入青銅器時代之前,就已經開始製作土器。這可以追溯到很久以前。到了舊石器時代晚期,尼安德特人的生活逐漸結束,出現了克羅馬農人和格里馬爾迪人。他們留下了繪畫和雕刻的遺物,但土器方面,僅發現用黏土捏成並在陽光下曬乾的像,即所謂古代「阿爾森器」,並沒有發現真正燒成的陶器。
■ 新石器時代
經過奧里尼亞文化、索呂特文化、馬格達林文化,進入阿茲利文化(地中海伊比利亞人)的新石器時代,人類才開始真正燒製土器。據說距今約2萬5千年至1萬2千年前。
■ 火與原始人
如果火打石的使用始於海德堡人,那麼土器的製作可能還要更早。原始人通過摩擦生火,這是劃時代的大发現,讓他們學會了烹飪。這種需求促使他們製作飲食器皿,用火燒製黏土成為必然結果。
■ 燒製方法
最初,人們只是將黏土手工捏成
形,放在陽光下晾乾。偶然之間,器物在火中被燒硬。後來人們有意用木柴加熱,逐漸發展出燒製方法。在日本,彌生式土器是將器物放在地上,用砂覆蓋,然後在四周堆放燃料燒製的。再後來,人們在地上挖坑,用石塊圍起來進行燒製。但因為沒有窯,火力不足,器物容易破裂,而且沒有釉藥,水分滲入後會影響食物的味道。
■ 窯的出現
後來,人們在斜坡上挖長坑,用黏土拱成頂,這就是最早的「穴窯」。這可以說是陶窯的鼻祖。之後出現了大窯、鐵炮窯,鎌倉和足利時代的名陶多用此類窯燒製。再後來,有分隔室的長窯、串聯的圓窯「登窯」,以及豎窯、德利窯和隧道窯等多種樣式。
■ 成型方法
最早的成型方法包括將繩子繞在棒上,再貼上黏土製成壺罐,或將黏土搓成長條,螺旋狀盤繞堆疊,稱為「盤築法」。後來出現了陶輪,包括手工輪和腳踏輪,之後又有模具、石膏模和動力機。
■ 釉藥的起源
為了防止水分滲入,並使器物表面光滑,釉藥的出現經歷了漫長時間。在中國,據說始於六朝時期。當時窯灰落在器物上,高溫燒成後在表面形成玻璃狀層,由此啟發了釉藥的發現。後來人們加入草木灰,逐漸理解到加入鹼性助熔劑能使其更易熔化。
■ 燒物的發展
於是,陶器從紅褐色的軟質土器,發展為致密的陶器,繼而出現施釉器、吸水性低的炻器,最終發展成堅硬美麗的瓷器。近代日本還嘗試製造超硬質瓷器。瓷器的燒成溫度在1250℃至1460℃之間,有田燒一般在1370~1400℃。日用品最好採用高溫燒成的瓷器,但這需要耐火原料與經濟燃料。裝飾品則軟陶更便於彩繪和雕刻。瓷器因高溫燒製,失敗率高,部分釉下彩料褪色,因此以青花為主,後來發展出赤繪、錦手等上彩。古代的無釉土器會大量吸水,酒杯需一口飲盡。祭祀器皿則多為一次性使用。印度因氣候炎熱,也習慣使用一次性素燒器,因此燒物未有大发展。
■ 世界的製陶
世界各地都自古製作陶器。古代亞述的「眼淚瓶」、埃及和希臘遺跡中都有精巧的陶器出土。中國相傳燧人氏在神農時代開始用火,這也證明當時已有土器使用。
■ 燒物與人類
法國人路易·吉埃說過:「燒物與人類一同誕生。」各國的發展速度和水平不同,但出於生活需要,各民族都製作陶器。通過製陶的進步和風格,可以推測史前人類的生活水平,而後世的出土器物則成為研究當時文化的重要依據。
【中国語訳(英語から簡体字)】
陶器与人类的历史
■ 原始人和陶器
在人类进入青铜器时代之前,就已经开始制作陶器。在旧石器时代晚期,克罗马农人和格里马尔迪人出现,他们留下了绘画和雕刻,但未发现真正烧制的陶器,只发现了晒干的粘土像。
■ 新石器时代
陶器制作在阿兹利安新石器时代开始,大约在距今2.5万至1.2万年前。
■ 火与陶器
火的发现使烹饪成为可能,推动了陶器的产生。
■ 烧制方法
起初是手工成型和日晒干燥,偶然被火烧硬。后发展为野烧和坑烧。由于没有釉药,器物易破裂且渗水。
■ 窑的发展
出现了“穴窑”,后发展为大窑、长窑、登窑等。
■ 成型方法
早期有盘筑法,后有陶轮、模具和机械。
■ 釉药
起源于灰在器物上熔化,逐渐发展为人工施釉。
■ 陶器的发展
从软陶到陶器、炻器,再到瓷器。
■ 世界制陶
亚述、埃及、希腊和中国都有早期陶器。
■ 陶器与人类
正如法国学者所说:“陶器与人类一同诞生。”陶器反映了人类文化的发展。
【中国語訳(英語から繁體字)】
陶器與人類的歷史
■ 原始人和陶器
在人類進入青銅器時代之前,就已經開始製作陶器。在舊石器時代晚期,克羅馬農人和格里馬爾迪人出現,他們留下了繪畫和雕刻,但未發現真正燒製的陶器,只發現了曬乾的黏土像。
■ 新石器時代
陶器製作在阿茲利安新石器時代開始,大約在距今2.5萬至1.2萬年前。
■ 火與陶器
火的發現使烹飪成為可能,推動了陶器的產生。
■ 燒製方法
起初是手工成型和日曬乾燥,偶然被火燒硬。後發展為野燒和坑燒。由於沒有釉藥,器物易破裂且滲水。
■ 窯的發展
出現了「穴窯」,後發展為大窯、長窯、登窯等。
■ 成型方法
早期有盤築法,後有陶輪、模具和機械。
■ 釉藥
起源於灰在器物上熔化,逐漸發展為人工施釉。
■ 陶器的發展
從軟陶到陶器、炻器,再到瓷器。
■ 世界製陶
亞述、埃及、希臘和中國都有早期陶器。
■ 陶器與人類
正如法國學者所說:「陶器與人類一同誕生。」陶器反映了人類文化的發展。