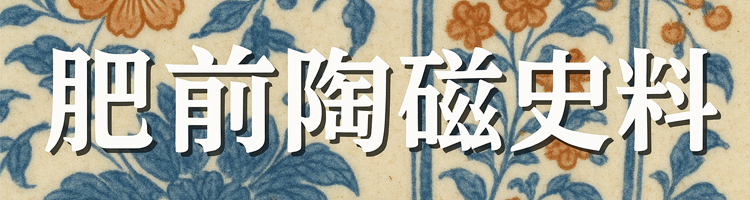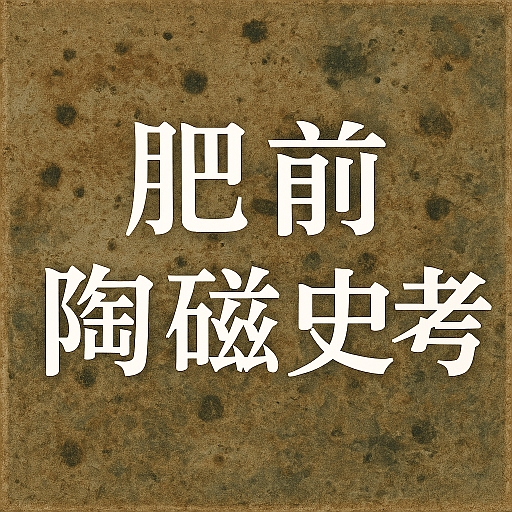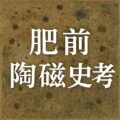【原文】
吉備津の開窯
同天平七年三月十日、入唐大使多治比廣成、留學生吉備真備、僭玄昉等歸朝するや、彼地より伴ひ來りし陶工菜、備中國吉備津に於いて開窯し施釉の陶器を作りし傳へらる。
行基焼
大僧正行基は又山背國清閑寺村字丸山(愛宕郡)に於いて、鄕人を指揮して土器を焼かしめたとの口碑がある。(法相宗の高僧大菩薩行基は俗姓高志氏和泉國大鳥郡の人にて天平元年二月二日卒去した行年八十二才であつた)
瑠璃瓦を葺く
稱徳天皇の神護景雲元年四月十四日、東院玉殿成るにあたり、瑠璃瓦を用ひて屋根を葺かしめたとある。(此時代の瑠璃とは碧釉でなく、玻璃の意味ならんとの説があり、今玉殿の古なる物あるも、果して當時の遺物なりや、或は後代改作の際に葺替へしにあらざるか詳でない)
陶器を日用の雑器に充つ
箕亀元年八月四日、稱徳帝西宮殿に於いて崩じ玉ふや宮廷は大膳職、大炊寮、造酒司、陶工司の監物等各一人に命じて役夫を養ふ司と為し、以て山陵(大和國漆上郡高野)を起さしめ、當時製陶の器を以て役夫の食器及日用の雑器に充てられことを記載されてある。
平安朝時代=佛具と青瓷
桓武天皇が延暦十三年十月二十二日、山背國乙訓郡長岡より、更に同國平安(京都)に御遷都あるや、佛具に用ふる陶器を凡て支那の青瓷に仰ぎ給うた。此頃より彼國の該器を齎らすこと頗る多きを加へしさ稱せらる。
碧瓦を葺く
薄いで平安城を築き、同十五年大極殿(大内裏入省院の中央にて即ち朝堂院の正殿おほやすみごのといふ、即位朝賀の國儀大禮所)の建立にあたり、洛北鷹ヶ峰に於いて焼きし碧瓦を以つて屋根を葺かしめられた。蓋し當時民屋に於いて瓦を葺くことは未だ許されざる時代である。
筥陶司合併さる
同朝の延暦二十四年十二月十日(或は大同三年とも)制して諸司の穴員を省き筥陶司を以つて大膳職に合併し、爾来陶器は此職の掌るところとなり、又土工司(瓦工)を木工に合併さるに至った。
酒甕の封鎖
平城天皇の大同元年、詔して酒甕の封鎖を行はれしが、一面陶業の發展に一頓挫を来たすの止を得なかった。
中興陶祖乙麿
嵯峨天皇の弘仁六年正月、嚮に造瓷生となりて入唐し、彼の瓷器傳習を終へて准雜生に出身せし三人のうち、尾張國山田郡(今春日井郡地方)の人三家人部乙麿、彼地より原料の陶砂を齎らして郷里主惠郷に来り、我邦に於いて始めて硬度の瓷器(青瓷)を製作した。之が尾濃陶業の元祖であり、そして又本邦中興の陶昶であらう。
平安朝藤原時代=青瓷の輸入を制す
光孝天皇の仁和元年十月二十日、太宰府にして私に唐物を買ふことを禁ぜられた。蓋し儒佛の傳來以後其祭具として支那青瓷の我邦人に愛さること甚だしく、上士太夫より下冨格の庶民に至るまで、花瓶、香壇の類を購入し以て賓客を待つのとした。當時より如何に多くの青瓷が輸入されしかは破損物を唐船より投棄せし博多海岸の夥しき残缺が、彼の元寇役に於ける元軍破船の遺物とのみは断定されぬのにしても明である。
陶器を輪となす
醍醐天皇の延喜五年、陶器を朝廷に奉り之を輪となす制度が發布され、大和、河内、攝津、和泉、美濃、近江、三河、淡路、播磨、筑前、讃岐、備前等十二ヶ國を調貢國と定め別に尾張と長門より瓷器若干を民部省に納貸せしむることゝなった。(輪とは其製する陶器を役に充費をするの法にて、其價は國の正税を以てしめたのである)
焼物の朝廷儀式階級
又弘仁式の瓷器即ち青瓷は、當時朝貢品中の上位であり、普通の陶器は中に位し、土器は下位であつた。故に其頃朝廷儀式の節は土器は黒漆器に相當され、陶器は朱漆器に相當されしが、瓷器に至つては銀器に代用されたのである。
土師左エ門
同延喜年間尾張國常滑村(知多郡)に於いて、土師左衛門なる者ありて稍勝し陶器を作りも。降つて天慶二年十一月二十一日平將門下にを起し、いで此月藤原純友伊豫に叛せ戰め、―陶輸絶ゆ―交通全く絶ゆるに及んで輸送の道なく、此頃より朝廷への陶楡こゝに斷絕せしといはれてゐる。
平安朝院政時代=猿頭の硯を献ず
堀河天皇の長治二年、尾張國瀨戸村(山田郡後の春日井郡)の陶工にて、朝廷へ猿頭の硯二十口(無釉陶)を奉献する者があつた。
後鳥羽天皇の元暦年間、山城國深草村(紀伊郡)に於いて陶器を製する者ありしが、それは釉薬なきものにて俗に焼締といふのであつた。
鎌倉源氏時代
保元治の頃より源平の兵権争奪屢行はれ、引き兵亂の影響は陶業の衰退を招くの止むを得なかつた。斯くて源頼朝天下を一統し、建久三年七月十二日府を鎌倉に開きしも、彼の武斷政治は工藝獎勵の如き敢て願みざりしもの如く、従つて何等出色の陶工も現出するに至らなかったのである。
【現代語訳】
天平七年三月十日、入唐大使の多治比広成、留学生の吉備真備や玄昉らが帰国した際、彼らに伴ってきた陶工が備中国吉備津で窯を開き、釉薬を施した陶器を作ったと伝えられている。
大僧正行基は山城国清閑寺村丸山において村人を指揮し、土器を焼かせたという伝承がある。行基(俗姓高志氏、和泉国大鳥郡の出身)は法相宗の高僧で、大菩薩と称され、天平元年二月二日に八十二歳で没した。
称徳天皇神護景雲元年四月十四日、東院玉殿の建立にあたり「瑠璃瓦」で屋根を葺かせたと記録にある。当時の瑠璃は青釉ではなくガラスの意味であったとの説もあり、現存する瓦が本当に当時のものか、後代の改作なのかは明らかでない。
称徳天皇崩御後の箕亀元年八月四日、山陵造営のため宮廷は大膳職や陶工司などの役人を任じ、製陶された器を労役の食器や日用雑器として充てたと記録される。
桓武天皇は延暦十三年に平安京へ遷都し、仏具として用いる陶器はすべて中国の青磁に仰いだ。この頃より青磁の輸入が盛んになったとされる。
延暦十五年、大極殿の屋根を葺くため、洛北鷹ヶ峰で焼かれた碧瓦が用いられた。当時、一般の民家には瓦葺きは許されていなかった。
延暦二十四年(または大同三年)、筥陶司は大膳職に合併され、陶器はその管轄となった。同時に土工司は木工に合併された。
平城天皇大同元年には酒甕の封鎖が命じられ、陶業発展は一時停滞した。
嵯峨天皇弘仁六年、尾張国山田郡の陶工・乙麿が唐から陶砂を持ち帰り、郷里で日本初の硬質磁器(青磁)を製作した。これが尾濃地方の陶業の始祖であり、日本陶業の中興とされる。
光孝天皇仁和元年、太宰府で私的に唐物を購入することが禁じられた。当時、中国青磁は祭具や接客具として貴族から庶民に至るまで広く愛用され、大量に輸入された。その証拠に、博多海岸からは廃棄された青磁片が夥しく出土している。
醍醐天皇延喜五年、陶器を朝廷に奉納し、租税に代える「輪」の制度が制定された。大和・河内など十二か国が調貢国とされ、尾張・長門からは磁器も納められた。
弘仁式では青磁が最上位の貢納品とされ、陶器は中位、土器は下位とされた。儀式では土器は黒漆器、陶器は朱漆器に相当し、青磁は銀器の代用品とされた。
延喜年間、尾張国常滑村の土師左衛門が優れた陶器を作ったが、平将門や藤原純友の乱で流通が絶え、朝廷への陶器供給は断絶した。
堀河天皇長治二年、尾張国瀬戸村の陶工が猿頭の硯二十口(無釉陶)を献じた。後鳥羽天皇の時代には山城国深草村で釉薬を用いない焼締陶が作られた。
鎌倉時代、源平の戦乱で陶業は衰退し、源頼朝が鎌倉幕府を開いた後も武断政治のもとで工芸は奨励されず、優れた陶工は現れなかった。
【英語訳】
In 735 (Tenpyō 7), when Ambassador Tajihi no Hirotsugu, scholar-official Kibi no Makibi, and Genbō returned from Tang China, they brought back potters who established kilns in Kibi, Bitchū Province, producing glazed ceramics.
The great monk Gyōki is also said to have directed villagers in Maruyama, Seikanji Village, Yamashiro Province, to fire earthenware. Gyōki (secular name Takashi of the Koshi clan, from Ōtori District, Izumi Province) was a high priest of the Hossō sect and passed away in 729 at age 82.
In 767 (Jingō Keiun 1), when the Tōin Gyokuden was built, roofs were covered with “ruri tiles.” It is debated whether “ruri” meant blue glaze or glass, and whether surviving examples are originals or later replacements.
After the death of Empress Shōtoku in 770, records show that pottery vessels were used as tableware and daily utensils for laborers working on her mausoleum.
When Emperor Kanmu moved the capital to Heian (Kyoto) in 794, he relied entirely on imported Chinese celadon for Buddhist ritual wares. Imports of celadon increased significantly from this time.
In 796, celadon tiles fired at Takagamine in northern Kyoto were used to roof the Daigokuden, the main hall of the imperial palace. At that time, commoners were not permitted to use roof tiles.
In 805, the Office of Pottery was merged into the Imperial Kitchen Bureau, while the Office of Tilework was merged with woodworking.
In 806, Emperor Heizei decreed the sealing of sake jars, causing a setback for the ceramic industry.
In 815, potter Otsumaro of Yamada District, Owari Province, returned from Tang China with ceramic raw materials and produced Japan’s first hard porcelain (celadon). He is regarded as the founder of the Ono ceramic tradition and a restorer of Japanese ceramics.
In 885, Emperor Kōkō prohibited the private purchase of Chinese imports at Dazaifu. Celadon was highly prized as ritual and hospitality ware by nobles and commoners alike, evidenced by the vast quantities of discarded shards found on Hakata’s coast.
In 905, Emperor Daigo established the rin system, in which ceramics were submitted to the court as tribute, replacing part of the tax. Twelve provinces were designated as tribute regions, and porcelain was collected from Owari and Nagato.
In the Engi era, celadon ranked as the highest-class tribute ware, pottery was middle-class, and earthenware the lowest. Ritual use assigned earthenware to correspond with black lacquerware, pottery with red lacquerware, and celadon as a substitute for silver.
In Owari’s Tokoname Village, Haji Saemon produced fine pottery during this era, but following the rebellions of Taira no Masakado and Fujiwara no Sumitomo, ceramic transport collapsed, cutting off supply to the court.
In 1105, under Emperor Horikawa, potters in Seto presented twenty monkey-head inkstones (unglazed) to the court. During Emperor Go-Toba’s reign, potters in Fushimi, Yamashiro, produced unglazed yakishime stoneware.
During the Kamakura era, civil wars weakened pottery production. Even after Minamoto no Yoritomo unified the nation in 1192, his militaristic government did not promote crafts, and no outstanding potters emerged.
【中国語訳(現代語訳から簡体字)】
天平七年三月十日,多治比广成、吉备真备、玄昉等自唐归国,随行陶工在备中国吉备津开窑,制作施釉陶器。
大僧正行基据传在山城国清闲寺村丸山指挥村人烧制土器。行基俗姓高志氏,和泉国大鸟郡人,法相宗高僧,天平元年以八十二岁卒。
称德天皇神护景云元年,东院玉殿建成,用“琉璃瓦”覆盖屋顶。据说当时的琉璃或指玻璃而非青釉。
称德天皇崩御后,陵墓营造中,陶器被用作役夫的食器与日用杂器。
桓武天皇延历十三年迁都平安京,佛具一律依赖中国青瓷,自此青瓷进口大增。
延历十五年,大极殿屋顶用洛北鹰峰烧制的碧瓦覆盖,民居仍不得用瓦。
延历二十四年,筥陶司并入大膳职,陶器归其掌管;土工司并入木工。
平城天皇大同元年,诏令封禁酒甕,陶业发展受阻。
嵯峨天皇弘仁六年,尾张国山田郡陶工乙麿自唐携陶砂归乡,始制日本首批硬质青瓷,被视为尾濃陶业之祖,也是日本陶业中兴的重要人物。
光孝天皇仁和元年,禁止在太宰府私购唐物。因中国青瓷盛行,自贵族至庶民皆用花瓶、香坛等接待宾客,导致大量进口。博多海岸出土的大量破碎青瓷,正是当时抛弃之物。
醍醐天皇延喜五年,制定“轮”制,以陶器代税,十二国被定为调贡国,并命尾张、长门贡瓷器。
弘仁式中,青瓷居贡品上位,陶器次之,土器最下。朝仪上,土器相当黑漆器,陶器相当朱漆器,青瓷则代银器。
延喜年间,尾张常滑村陶工土师左卫门烧制优良陶器,然平将门与藤原纯友之乱使交通断绝,朝廷陶贡中绝。
堀河天皇长治二年,尾张濑户村陶工献猿头硯二十口(无釉陶)。后鸟羽天皇时,山城深草村陶工制烧締陶。
镰仓时代,源平纷争使陶业衰落。源赖朝开幕府后,武断政治不振工艺,未见杰出陶工。
【中国語訳(現代語訳から繁體字)】
天平七年三月十日,多治比廣成、吉備真備、玄昉等自唐歸國,隨行陶工在備中國吉備津開窯,製作施釉陶器。
大僧正行基據傳在山城國清閑寺村丸山指揮村人燒製土器。行基俗姓高志氏,和泉國大鳥郡人,法相宗高僧,天平元年以八十二歲卒。
稱德天皇神護景雲元年,東院玉殿建成,用「琉璃瓦」覆蓋屋頂。據說當時的琉璃或指玻璃而非青釉。
稱德天皇崩御後,陵墓營造中,陶器被用作役夫的食器與日用雜器。
桓武天皇延曆十三年遷都平安京,佛具一律依賴中國青瓷,自此青瓷進口大增。
延曆十五年,大極殿屋頂用洛北鷹峰燒製的碧瓦覆蓋,民居仍不得用瓦。
延曆二十四年,筥陶司併入大膳職,陶器歸其掌管;土工司併入木工。
平城天皇大同元年,詔令封禁酒甕,陶業發展受阻。
嵯峨天皇弘仁六年,尾張國山田郡陶工乙麿自唐攜陶砂歸鄉,始製日本首批硬質青瓷,被視為尾濃陶業之祖,也是日本陶業中興的重要人物。
光孝天皇仁和元年,禁止在太宰府私購唐物。因中國青瓷盛行,自貴族至庶民皆用花瓶、香壇等接待賓客,導致大量進口。博多海岸出土的大量破碎青瓷,正是當時拋棄之物。
醍醐天皇延喜五年,制定「輪」制,以陶器代稅,十二國被定為調貢國,並命尾張、長門貢瓷器。
弘仁式中,青瓷居貢品上位,陶器次之,土器最下。朝儀上,土器相當黑漆器,陶器相當朱漆器,青瓷則代銀器。
延喜年間,尾張常滑村陶工土師左衛門燒製優良陶器,然平將門與藤原純友之亂使交通斷絕,朝廷陶貢中絕。
堀河天皇長治二年,尾張瀨戶村陶工獻猿頭硯二十口(無釉陶)。後鳥羽天皇時,山城深草村陶工製燒締陶。
鎌倉時代,源平紛爭使陶業衰落。源賴朝開幕府後,武斷政治不振工藝,未見傑出陶工。
【中国語訳(英語から簡体字)】
公元735年,多治比广成、吉备真备、玄昉等自唐归国,带回陶工在备中国吉备津建窑,制釉陶。
僧行基曾在山城国清闲寺村组织村人制土器。行基高志氏出身,和泉国人,法相宗高僧,729年卒,享年82岁。
767年,东院玉殿建成,屋顶覆以“琉璃瓦”。学界认为此时琉璃或指玻璃。
770年,称德天皇驾崩后,陶器用于陵墓工役者食器与杂器。
794年,桓武天皇迁都平安京,佛具全赖中国青瓷。
796年,大极殿以鷹峰窑碧瓦覆顶。民居尚禁用瓦。
805年,筥陶司并入大膳职,土工司并入木工。
806年,酒甕封禁,陶业受挫。
815年,尾张陶工乙麿自唐携陶砂归乡,制日本首批硬瓷(青瓷),为尾濃陶业之祖。
885年,禁私购唐物。青瓷流行,贵贱皆用,博多遗有残片。
905年,设“轮”制,以陶器代税,十二国贡陶,尾张长门贡瓷。
当时青瓷最尊,陶器次之,土器最卑。仪式上,土器=黑漆器,陶器=朱漆器,青瓷=银器。
延喜年间,常滑陶工土师左卫门制优陶,但因战乱陶贡绝。
1105年,濑户陶工贡猿头硯二十口。后鸟羽时,深草陶工制烧締陶。
镰仓时,兵乱衰陶。源赖朝政武断,不振工艺。
【中国語訳(英語から繁體字)】
公元735年,多治比廣成、吉備真備、玄昉等自唐歸國,帶回陶工在備中國吉備津建窯,製釉陶。
僧行基曾在山城國清閑寺村組織村人製土器。行基高志氏出身,和泉國人,法相宗高僧,729年卒,享年82歲。
767年,東院玉殿建成,屋頂覆以「琉璃瓦」。學界認為此時琉璃或指玻璃。
770年,稱德天皇駕崩後,陶器用於陵墓工役者食器與雜器。
794年,桓武天皇遷都平安京,佛具全賴中國青瓷。
796年,大極殿以鷹峰窯碧瓦覆頂。民居尚禁用瓦。
805年,筥陶司併入大膳職,土工司併入木工。
806年,酒甕封禁,陶業受挫。
815年,尾張陶工乙麿自唐攜陶砂歸鄉,製日本首批硬瓷(青瓷),為尾濃陶業之祖。
885年,禁私購唐物。青瓷流行,貴賤皆用,博多遺有殘片。
905年,設「輪」制,以陶器代稅,十二國貢陶,尾張長門貢瓷。
當時青瓷最尊,陶器次之,土器最卑。儀式上,土器=黑漆器,陶器=朱漆器,青瓷=銀器。
延喜年間,常滑陶工土師左衛門製優陶,但因戰亂陶貢絕。
1105年,瀨戶陶工貢猿頭硯二十口。後鳥羽時,深草陶工製燒締陶。
鎌倉時,兵亂衰陶。源賴朝政武斷,不振工藝。