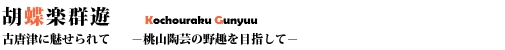古唐津及び唐津焼並びに陶芸に関する用語集 さ行
さ
彩陶(さいとう)
中国の新石器時代に現れた彩色文様を施した土器。
「釉薬(ゆうやく)」(うわぐすり)のかかったものは含めません。
砂まじりの、または良質の粘土でつくった土器に、鉄分を多量に含んだ紅土(焼成後黒くなる)や、赭(しゃ)石(焼成後赤くなる)をといて種々の文様を描き、つぎに約1,000℃で焼成します。
この場合の彩色は落ちにくいが、焼成後に彩色したものは落ちやくなります。
彩陶は、黄河流域の仰韶文化に発達し、文様は幾何学文や動物文など多様であり、彩色は黒・赤から、しだいに多彩になります。
特に黄河上流域の甘粛・青海地方では、多様な彩陶が大量につくられ、渦巻文・連孤文・蛙文・鳥文などの複雑精緻な文様が施されており、中国の彩陶芸術の宝庫といわれています。
鮫肌釉(さめはだゆう)
薩摩焼(さつまやき)などにみられる粒状の、いわゆる鮫肌を表す釉(うわぐすり)。
酒井田柿右衛門(さかいだかきえもん)
伊万里焼(いまりやき)の窯元で初代は赤絵(あかえ)の創始者。当代は14代目。国の重要無形文化財にも指定されています。独特の乳白の素地(きじ)である濁し手(にごして)は4代目に完成。
薩摩焼(さつまやき)
朝鮮半島の陶工によって薩摩に開かれた窯。明治以降、錦手(にしきで)が多く欧米諸国に輸出。
猿投(さなげ)
愛知県瀬戸市と豊岡市、日進市、藤岡町周辺で焼かれた焼締陶。
五世紀前半から須恵器がつくられ、八世紀前半には、日本で最初の灰釉陶がつくられ始められました。
愛知県の猿投窯では、9世紀には猿投窯独特の白色の陶胎に高火度の灰釉を掛けた、灰釉陶器を焼くようになる。
奈良朝に原形を持つこの壷は、その優美な造形から10世紀前半の作と考えられ、蓋・身にかけられた淡緑色の灰釉の流れも美しい。
共蓋を伴うのも貴重であり、猿投灰釉陶を代表する作例です。
銹絵(さびえ)
鉄絵(てつえ)ともいい、絵付けの一種。釉薬(ゆうやく)の下に描く下絵、上に描く色絵の上絵とあり、茶色から黒褐色の色合い。
銹釉(さびゆう)鉄砂(てっしゃ)
茶色に発色した鉄釉(てつぐすり)の一種。
柿右衛門様式(かきえもんようしき)では口縁に塗られる。
皿山(さらやま)
焼物が造られている地域のことをいう。
皿屋ともいい九州地方の磁器製造地など。南九州では壺屋ともいいます。
匣(さや)・匣鉢(さやばち)
窯詰道具のひとつで、窯の焼成時に焼物を保護し、効率よく窯に積み上げて積むための容器で、ボシとも呼ばれる。
紗綾形文(さやがたもん)
卍を斜めに連ねた連続文様。綾の絹織物に用いられる文様。
酸化炎焼成(さんかえんしょうせい)
酸素を多くして完全燃焼させる焼成法。土や釉に含まれる鉱物が酸化され固有の発色をする。
三彩(さんさい)
褐・緑・黄・藍といった色釉を、直接素地に施して低火度焼成(800度)された陶磁器の加彩法。
漢代におこり、唐三彩によって完成されました。
その影響は渤海三彩・奈良三彩を生み出し、遼三彩や宋三彩へと転化していき、西方ではペルシア陶器・マジョリカ陶器にまで至っています。
明末には景徳鎮にて磁器に三彩釉を施す、素三彩が登場し康熙年間のものが名高い。
唐三彩(とうさんさい)
中国の唐時代につくられた軟陶三彩を呼びます。
緑・白・褐の三色が多いが、緑なり、白なりの一色のものもあります。
たまに青色を加えたものもあり、これは藍彩と呼ばれています。
殆ど副葬品として用いられました。
し
信楽(しがらき)
滋賀県甲賀郡信楽町を中心として焼かれる陶磁器の通称。
天平14年(742)聖武天皇が紫香楽宮を造営したとき、造営用布目瓦を焼いたのがその始まりとされています。
本来は種壷、茶壷、甕、擂鉢などの雑器が中心であったが、室町時代後期に「侘茶」が流行しはじめると、いち早く茶道具として注目を集め、これらの逸品は古信楽といわれる。
天文18年(1549)の津田宗達の『天王寺屋茶会記』に「しからきそヘテ茶碗也」とあるのが茶陶としての信楽の初出。
武野紹鴎も信楽焼を愛好し茶器を焼かせ、また千利休は自らの意匠による茶器を作り、紹鴎信楽・利休信楽・新兵衛信楽・宗旦信楽・遠州信楽・空中信楽などと茶人の名前を冠した茶器が現れるほど名声を博した。
長石を含んだ白色の信楽胎土は良質で、鉄分の少ない素地のため、高火度の酸化炎により焦げて赤褐色の堅い焼締め肌の明るい雰囲気が特徴となっています。
本来は無釉だが、焼成中に薪の灰がかかる自然釉が淡黄、緑、暗褐色などを呈し器物の「景色」をつくっています。
薪の灰に埋まって黒褐色になった「焦げ」、窯のなかで炎の勢いにより作品に灰がかかり自然釉(ビードロ釉)が付着した「灰被り」、「縄目」赤く発色した「火色」、胎土に含まれたケイ石や長石が炎に反応し、やきものの表面に現れる)」、「蜻蛉の目(やきものの表面に窯を焚く灰が掛かり、それが溶けて釉薬と同等の働きをしたもの)」また、水簸をおこなわないため、胎土中の粗い長石粒が溶けて乳白色のツブツブになる「石はぜ」も信楽焼の一つの特徴となっています。
磁器(じき)
陶石(とうせき)を主原料とし、透光性があり、吸収性はなく、主な産地としては有田・瀬戸・九谷・砥部など。
磁石(じせき)
日本では有田の泉山の磁石の発見が最初。
世界中でも、泉山と熊本の天草の石だけが単身で磁器が造れる珍しい磁石です。
四耳壺(しじこ)
肩の部分の四方に、つまみや紐の留め具など耳がつけられた壺で、葉茶壺に用いられることが多くあります。
天平6年(734)に光明皇后が法隆寺に献納された「丁子」と呼ばれる香料の容器が世界最古の伝世陶磁として残っています。
中国南部の浙江省を中心とした地域で生産された青磁で、盤口をもつ器形や灰緑色のなめらかな釉調などから判断して製作年代は南朝末頃とみらています。
磁州窯(じしゅうよう)
中国河北省の陶窯であり、中国の白化粧の磁器のことでもある。
中国の華北地方一帯には、灰色の胎土に白土を化粧がけした白色の陶器を焼いた民窯が散在し、代表的な窯場の名をとって磁州窯と総称されている。
磁州窯では、白化粧を施した器面を彫る掻落しの技法により、独特の文様装飾が発達しました。
浮彫風の力強い文様表現は、北宋時代前期の作風を示しています。
自然釉(しぜんゆう)
窯内で素地の表面に燃料の薪の灰が付着して熔けて釉となったもの。
自然にかかった状態なのでそう呼びます。
この発見によって木灰が使われるようになったと考えられています。
下絵付け(したえつけ)
釉薬を施す前の釉下の仕事で、素地に染付や銹絵などで文様を描く技法のこと。
染付(そめつけ)・銹絵(さびえ)・辰砂(しんしゃ)などのように、釉薬(ゆうやく)を掛ける前に素地(きじ)に直接模様を描くこと。
七宝(しっぽう)
金属で作られた器物の表面に凹部を作り、そこに鉱物質の色剤を入れ、熱して溶着させたもの。
色と色との間を針金で区切って模様を表す有線七宝といわれるものが一般的だが、その他にも金属線を省いた無線七宝、透明な色剤を用いた透胎七宝などの種類があります。
七宝繋文(しっぽうつなぎもん)
鍋島の裏文様の中で最も代表的な文様。七宝文をつないで結んだ文様。
七宝文(しっぽうもん)
七種の宝をあらわす四方に孤をもつ丸文。これを数個繋いだものは七宝繋文となる。
志野(しの)
桃山時代に美濃(岐阜県)で焼かれた白釉の陶器。
日本で最初に下絵付けが行なわれた白色の焼き物で、茶陶の優品が多くあります。
素地は「もぐさ土」という鉄分の少ない白土で、長石質の半透明の白釉が厚めにかかり、釉肌には細かな貫入や「柚肌」と呼ばれる小さな孔があり、釉の薄い口縁や釉際には、「火色」(緋色)と呼ばれる赤みの景色が出ます。
絵模様のない「無地志野」、釉の下に鬼板で絵付けした「絵志野」、鬼板を化粧がけし文様を箆彫りして白く表し志野釉をかけた「鼠志野」、鼠志野と同じ手法で赤く焼き上がった「赤志野」、赤ラク(黄土)を掛けた上に志野釉をかけた「紅志野」、白土と赤土を練り混ぜ成形し志野釉をかけた「練り上げ志野」があります。
さらに近年、大窯で焼かれた志野(古志野)と区別し登り窯で焼かれたものを「志野織部」と呼びます。
天明5年(1785)の『志野焼由来書』に「伝言、文明大永年中、志野宗心と云う人ありて茶道を好む故に、其の頃加藤宗右衛門春永に命じて古瀬戸窯にて茶器を焼出す、是を志野焼と称す。」とあり長く瀬戸で焼かれたとされていましたが、昭和5年(1930)の荒川豊蔵(1894~1985)の古窯跡調査以降、美濃の可児・土岐などの窯で黄瀬戸・瀬戸黒・織部とともに焼かれたとされ、志野宗心についても、貞享元年(1684)刊の『堺鑑』に「志野茶碗 志野宗波風流名匠にて所持せし茶碗也 但し唐物茶碗の由申伝。」とあるように今云うところの志野焼とは異なるとされています。
元禄頃までは志野焼は織部焼と目され、千宗旦の弟子の城宗真が、織部好みの焼物に「篠焼」と名付けてから織部焼と区別されたとされています。
志野織部(しのおりべ)
志野と同じ技法で大窯で焼かれたもので、火色は出ず、鉄絵の部分も黒みの強いものが多く見られます。
次世代の連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま)の作品にも同種のものがあって、大窯作品との区別は難しいですが、大窯のものは志野、連房式登窯のものは志野織部とされています。
鎬(しのぎ)
本来は、刀剣の刃と峰の間に貫いて走る稜線のことだが、やきものでは、上下に削られた筋のこと。鎬文といいます。
仕服(しふく)
茶入を入れる袋のことで、「仕覆」とも書きます。
名物裂・古代裂が多く使用されています。
茶入によっては、名物裂の替袋(かえぶくろ)を何枚も持つものもあります。
仕服は、茶入、茶杓とともに客の拝見に供されます。
もと、茶入に付属する「袋」「挽家(ひきや)」(仕服に入れた茶入を保存する木の器)「箱」「包裂(つつみぎれ)」その他の補装を「修覆(しゅうふく)」といい、修覆が仕覆となり、茶入袋の呼び名になったといわれています。
蛇窯(じゃがま)
丹波焼(たんばやき)で用いられた窯。窖窯(あながま)が地上化、長大化して蛇のように登るところが名前の由来。
蛇蝎唐津 (ジャカツカラツ)
黒釉の上に失透性釉や長石釉をかけて焼成したもので、長石釉の下から鉄釉が出て溶け合い、釉肌が蛇やトカゲの肌に似ているところからの名称です。
朱泥(しゅでい)
朱色の粘土を使った石器(せっき)質の焼き物。急須などの煎茶器が多く、常滑(とこなめ)・万古(ばんこ)などが名高い。
常滑といえば、ただちに赤褐色の急須が思い浮かぶほど、朱泥の急須は常滑焼の代表的な製品になっています。
しかし、朱泥焼の技法が取り入れられたのは、常滑焼の歴史の中でも比較的新しく、江戸時代末期(1861年~1864年)のこととされています。
江戸時代後期から盛んになった煎茶の風習にあわせて、19世紀初頭から常滑でも急須の生産は始まっていました。
この時代の代表的な煎茶器は、中国で生産された朱泥焼でした。
この朱泥焼に取り組んだのが、常滑の杉江寿門(すぎえじゅもん)と片岡ニ光(かたおか にこう)でした。
常滑の朱泥焼は、鉄分の多く含まれた土を酸化炎焼成することによって赤褐色の色を得ることができました。
このことによって、常滑の窯業は一変し、従来の壷・甕類の大型製品ばかりでなく、朱泥煎茶器類を専門に生産する陶工達も現れてきます。
特に、明治11年(1878年)に中国人金士恒(きんしこう)を招き、中国の急須制作技法を受けたことにより、常滑の朱泥急須は一層発展するのです。
朱泥急須の表面に細字を彫る技法も、金士恒の時から始まります。
金士恒の刺激は、単に技術的な面ばかりでなく、常滑窯に欠けていた工芸に対しても大きな影響を与えたのです。
大正名器鑑(たいしょうめいきかん)より
小岱焼(しょうだいやき)
熊本県南関町宮尾で焼かれた陶器。一時、有田や瀬戸の磁器に押され衰退したが、現在は荒尾市、熊本市で再興。
縄文土器(じょうもんどき)
日本の新石器時代(縄文時代) 1万2000年前より、約1万年の間つくられ使われた土器。
縄目の文様がついたものが多く、黒褐色でもろく、形や文様はさまざまで、芸術的にもすぐれています。
各地の貝塚や住居跡から出土しますが、関東・東北地方に特に多くみられます。
初期伊万里(しょきいまり)
最も古い時期の伊万里焼(いまりやき)。
17世紀初頭、有田の泉山で磁器原料となる陶石が発見され、日本の磁器の創業期を迎えました。
天神森窯、山辺田窯、天狗谷窯、百間窯などそこで焼成された白磁、染付、青磁を「初期伊万里」と呼んでいます。
皿の器形は高台が口径に比べて非常に小さく、底の中央をえぐるように削り出しています。
また底には砂の付着したものが多いようです。
染付の文様は自由奔放な筆致で力強く、しかも雅味に富んでいます。
当時すでに中国から日本に輸入されていた古染付や祥端文などの影響が考えられます。
祥瑞(しょんずい)
中国明時代、景徳鎮(けいとくちん)の民窯で焼かれた染付磁器(そめつけじき)。独特な幾何学的な文様が特徴。
白薩摩(しろさつま)
薩摩焼(さつまやき)の中で、白土に透明釉(とうめいゆう)を掛けたもの。表面に細かな貫入(かんにゅう)が入るのが特徴の一つ。
沈香壺(じんこうつぼ)
蓋付で口縁が高く、肩が張って、長い胴が裾に向かってすぼまっている壺。
辰砂(しんしゃ)
還元炎焼成(かんげんえんしょうせい)により、銅化合物が辰砂(しんしゃ)のような朱色になったもの。
す
吸出し(すいだし)
湯のみが筒形なのに比べ、口に向かって開いている茶碗。もともとは茶会で白湯を出す際に用いる器。
水簸(すいひ)
水に入れて攪拌(かくはん)し、土の場合は精粗を分別し、灰の場合はアクを取り除く作業。
水中に土を入れよくかき混ぜると砂などの粒子の粗いものが沈んで、細かい粒は泥状になります。
この泥土の水分を蒸発させると細かい粒子のみの素地土が得られます。
最近の研究で、古唐津は粘土ではなく、砕いた石を 原料にしているのではないかと考えられてます。
唐津市周辺に大量にある砂岩をから質の良い土を取り出すことができる方法が簸(すいひ)です。
まずは細かく砕いた石を水にいれます。
焼き物の原料となる目の細かい良質な土は沈殿せずに水にとけています。
この水を何度もこして、粒子のそろった土を取り出します。
堅く焼き締まる秘密はこの土の成分にあります。
実はガラスの原料となる長石が大量に含まれているのです。
「唐津焼 (NHK美の壺)」 NHK「美の壺」制作班より
須恵器(すえき)
須恵器(すえき)とは、青く硬く焼き締まった土器で、古墳時代の中頃(5世紀前半)に朝鮮半島から伝わった焼成技術をもって焼いた焼き物のことをいいます。
それまでの日本には、野焼きで焼いた縄文土器や弥生土器、土師器など赤っぽい素焼きの土器しかありませんでした。
それまでの焼き物と須恵器が大きく異なっているのは、その焼成技術にあります。
野焼きでも1,000度近くまで温度は上がりますが、周りが覆われていないので、すぐに熱が逃げて温度が安定しません。
窯を使うことにより高温状態を保つことができるようになりました。
須恵器はまたたくまに全国に広がり焼かれるようになりました。
当時の人々にとって、重要な食器として使われたことでしょう。
その後15世紀にいたるまで須恵器の伝統は続きました。
珠洲焼がその一つの例です。
須恵器は今日にも続く焼き物に重要な役割をもっていたといえるでしょう。
砂目跡(すなめあと)
器を重ねて焼くときに、器どうしがくっついてしまうのを防ぐため間に砂をまきます。
その時に残った跡を砂目跡といいます。
墨弾き(すみはじき)
墨で文様を描き、上から絵具で施して焼くと、墨上の絵具が剥がれて白く抜ける下絵付けの技法。
墨流し(すみながし)
墨で文様を描き、上から絵具を施すと、墨に入っている膠分で絵具をはじき、その後、焼くと墨も焼き飛び、白い文様が出てくる白抜きの下絵付けの技法で、白釉に鉄釉を垂らして竿で撫ぜ、マーブル状で焼成すると、水面に墨を流したようになります。
スタンパー(すたんぱー)
石や土などを粉砕するための装置。
スタンパーで突いた石類はポットミルで細かくしたものに比べ粒子に角があり、天然材料を使用する場合は味が出てきます。ポットミルで細かくしたものは、均一になるので用途に合わせて使用することが作品の出来を少しだけ変化させることができます。
素焼(すやき)
成形した器を乾燥させ、釉(うわぐすり)をかけずに比較的低い温度で焼成すること。
温度は、土にぎりぎり戻ることができる400度から800度の間で焼成します。
素焼きの効果としては、作品を扱いやすくなりますが、釉薬を浸けるときに吸水が大きくなるので釉薬の濃度管理が必要となります。
せ
青花(せいか)
青花とは、白磁の素地にコバルトを含んだ顔料で文様を描き、透明釉をかけて焼成する技法で、わが国では染付とも呼ばれます。
青花の技術と様式は、元時代後期の景徳鎮窯において完成されました。
青海波(せいがいは)青海波状文(せいかいはじょうもん)
同心円の半円形を重ね併せて、波文様を表現した文様。
叩き技法で作る壺・水指等の内側によく見られます。
内側には丸太外側は板で、同時に叩き合わせて土を締めながら作る叩き技法により、規則正しいリズムでたたくのでこのような輪状の文様ができます。
輪状の文様は丸太(杉や松や桜の木を焼いて作ったもの)の年輪の叩き跡の文様です。
青磁(せいじ)
磁器の一種で、釉薬の中に少量(2%前後)含まれる鉄分が、還元炎焼成されて酸化第一鉄となり青緑色に発色した磁器。
鉄分が少ないと青白磁となり、さらに少なければ白磁となります。
また釉薬中の鉄分が多いと黄色から褐色、さらに黒色となります。
古く中国の殷・周時代に始まり、戦国から前漢時代に一般に使用されるようになった灰釉陶が青磁の始源と考えられています。
三国・六朝時代になると、古越磁(こえつじ)といわれる青磁が越州窯でつくられた。
北宋になると華北の汝窯や官憲でつくられたが、南宋になると修内司官窯・郊壇官憲や民窯では龍泉窯で優れた青磁がつくられました。
中国の龍泉窯・汝窯・磁州窯などに優品がみられます。
日本ではその時代と色によって、南宋代の粉青色を呼ばれる鮮やかな青緑色の砧手(きぬたで)、元代から明代にかけてのやや黄色味を帶びた緑色の天龍寺手(てんりゅうじで)、明代後期の透明性のある淡い翠青色で貫入があるのが特徴とされる七官手(しちかんで)と呼び分けてきました。
高麗時代の初期になると朝鮮に伝えられ、いわゆる高麗青磁がつくられるようになりました。
10~13世紀にはヴェトナムに、13世紀にはタイにも伝えられ、日本では江戸時代になってから青磁がつくられるようになりました。
佐賀県有田の伊万里青磁・鍋島青磁などが有名です。
青瓷(せいじ)
青磁のなかでも、器胎が陶器質の場合にこの文字を使う場合があります。
「青磁」は磁器質を表しています。
青白磁(せいはくじ)
中国景徳鎮(けいとくちん)窯で宋代に焼かれた、白磁(はくじ)と青磁(せいじ)の中間のような薄青い磁器。室町時代に日本へ多く輸出。
石炭窯(せきたんがま)
石炭を燃料とした窯で、日本では19世紀末から半ばまで、重油窯や電気窯に移行する50年程の間に使用。
ゼーゲルコーン(ぜーげるこーん)
窯のなかの温度を測るための、配合土でできた三角錐の温度計です。
ある熱量を受けると、曲がるように調合してあります。
焼成程度あるいは耐火度を測定するために使用する標準の三角錐。
わが国やヨーロッパ各国で使用されています。
標準のコーンとして、ISOではISOコーン、アメリカではオルトンコーンが用いられます。
石灰釉(せっかいゆう)
下絵がにじまないため、絵付けをした器に掛けるのに適する釉。
1号釉から3号釉まであります。それぞれ融ける温度が違いますので用途に合わせて使用します。
非常に便利な釉薬ですが、唐津ではあまり使用しません。
せっ器・石器(せっき)
備前(びぜん)・信楽(しがらき)・常滑(とこなめ)などのように、素地(きじ)が白色でない、石のように固く焼き締められた陶器の総称。
石膏型鋳込み(せっこうがたいこみ)
轆轤(ろくろ)では不可能な形を、石膏の吸収性を利用し、石膏型をつくりそこに泥漿を流し込んで作る方法。
瀬戸(せと)
愛知県瀬戸市並びにその周辺で作られる陶磁器の総称。
六古窯(ろっこよう)の一つで成立は古く平安中期の灰釉陶器にまで遡ります。
鎌倉時代の初めから室町時代の中頃瀬戸窯では、中国や朝鮮から輸入された陶磁器を模倣し、釉薬を器面全体に施したやきものが製作され、この日本の中世唯一の施釉陶器を「古瀬戸」と呼んでいます。
加藤四郎左衛門景正(かとうしろうざえもんかげまさ)が貞応2年(1223)に僧道元(どうげん)に従って入宋し、陶法を修業して帰国し、仁治3年(1242)瀬戸において窯を築いたのが瀬戸焼の始まりとする陶祖藤四郎(とうそとうしろう)伝説が古くから伝えられています。
灰釉のみが使用された前期(12世紀末~13世紀後葉)、鉄釉が開発され印花(いんか)・画花(かっか)・貼花(ちょうか)など文様の最盛期である中期(13世紀末~14世紀中葉)、文様がすたれ日用品の量産期となる後期(14世紀後葉~15世紀後葉)の三時期の区分がされています。
戦国時代になると、大窯により天目茶碗、中国明代の青磁や染付を模倣した供膳具が生産されました。
桃山期になると美濃地方を含めた地域で「黄瀬戸」「瀬戸黒(せとぐろ)」「志野(しの)」、さらに17世紀初頭には連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま)の導入とともに「織部(おりべ)」といった桃山茶陶(ちゃとう)の生産が全盛期を迎えます。
江戸時代中期になると名工達による一品物の制作が盛んに行われ、瀬戸村の春琳(しゅんりん)・春暁(しゅんぎょう)・春宇(しゅんう)・春丹(しゅんたん)・善治(ぜんじ)、赤津村(あかづむら)では春岱(しゅんたい)・寿斎(じゅさい)・春悦(しゅんえつ)、下品野村では定蔵(ていぞう)・品吉(しなきち)・春花(しゅんか)らの名工が幕末期にかけて活躍します。
江戸後期になって、文化4年(1807)加藤民吉(かとうたみきち)により有田から染付磁器の製法が伝えられてからは、染付磁器が主流となる。
現在、加藤民吉は瀬戸の磁祖(じそ)として窯神神社(かまがみじんじゃ)に祀られ9月の第2土・日曜日には「せともの祭り」が開催されています。
瀬戸焼(せとやき)
愛知県瀬戸市の陶磁器。鎌倉時代に加藤四郎右衛門景正(かとうしろううえもんかげまさ)が、中国の陶法を伝え天目茶碗(てんもくぢゃわん)や茶入を焼いたのがはじまりといわれています。
瀬戸唐津(せとがらつ)
茶碗の一種で、唐津の漉土を使い、瀬戸の上薬を用いて焼成したゆえにこの名があるという。
砂気の多い白土で、白色釉が施され、釉ひびがある朝顔形の平茶碗で、高台は低く、口縁に鉄釉の口紅が施され、俗に皮鯨と称される。
中国定窯・磁州窯などの天目茶碗にヒントを得たものであろう。
また本手瀬戸唐津といわれる深手の碗形茶碗もあり、唐津鬼子嶽飯洞甕下窯・同上窯・帆柱窯・道谷窯などから類似の破片が発見されています。
(茶道辞典淡交社より)
瀬戸唐津は尾張瀬戸の釉薬を用いるためにこの名があるといい、また瀬戸に類似している唐津であるためにこの名があるといわれます。
瀬戸唐津には本手と皮鯨手の二種があります。
本手瀬戸唐津:
本手瀬戸唐津は、砂気の多い白い土で、縮緬皺がよく出ていて、釉薬は長石単味に近く、色は灰白、白、琵琶色で梅花皮がよく出ています。
形は、柿の蔕、青井戸、蕎麦、呉器などを写していて、見込みの鏡に目跡があります
皮鯨手瀬戸唐津:
平茶碗の口縁に鉄釉が施され、鯨の皮に似た色に発色していることからこの名があります。
瀬戸黒(せとぐろ)
美濃(みので桃山時代に焼かれた黒色の茶碗。かつて瀬戸の産と考えられたのが名前の由来。
扇形(せんめん)
向付(むこうづけ)などに用いられる扇の形をした器。
半面開いたものは、半間扇と呼ばれる。
施釉(せゆう)
やきものに釉薬(ゆうやく)を施すこと。刷毛塗り、漬け掛けなどの方法もある。
千利休(せんのりきゅう)
安土桃山あづちももやま期の茶道の完成者で千家流茶道の開祖。
茶湯を武野紹鴎などに学び、16歳のとき京都で茶会を開いて茶湯の世界に登場しました。
のち大徳寺で参禅、宗易の号で茶会を主催、織田信長の茶頭、次いで豊臣秀吉に重用されました。
佗び茶を完成し草庵風の茶室様式を築き、多くの弟子を育てて茶道の発展に尽力を尽くしたが、秀吉の怒りを受け、切腹しました。
現在の茶道千家の始祖であり、茶聖と称せられています。
そ
象嵌(ぞうがん)
生乾きの素地(きじ)に文様を付けたり、素地(きじ)と異なる色の土で埋めて、はみだし部分を削り文様を表す装飾法。
青磁象嵌は高麗時代の朝鮮で独自の発達をとげた技法。
胎土に文様を彫り込んで白土、赤土を埋め、いったん素焼きをしたのち青磁釉をかけて焼成すると、白土は白く、赤土は黒く発色する。
胴の一面に柳と葦、一面に竹と梅樹、さらにもう一面に葦の図がいずれも器面いっぱいにのびやかにあらわされおり、高麗独特の繊細な情感がもりこまれています。
染付(そめつけ)
呉須(ごす)やコバルトを主原料とした絵具を用いて下絵付けし、その上に透明釉(とうめいゆう)を掛け焼いたもの。
白素地に藍色の顔料である酸化コバルト(呉須)を含む顔料で絵付けをし、さらに透明な上釉を掛けて還元焼成をした磁器の総称で、中国では、青花(せいか)・釉裏青(ゆうりせい)と呼ばれています。
また下絵付けを施したものに対する広義の名称として用いられる場合もある。
「染付」とは、もともとは染織用語から派生した言葉で、室町時代にはじめて中国から輸入されたときに、見かけが藍色の麻布(染付)に似ているので日本ではその名で呼ばれるようになった。
中国では青花(華)・釉裏青と呼び、英語ではブルー・アンド・ホワイトという。
文献的には室町時代の『君台観左右帳記』には染付の語は見えず、1603年(慶長8)刊行の『日葡辞書』に掲載されています。
染付は1,300度といった高火度の還元焼成を必要とするため、相当の築窯技術の発達を背景としていなければなりません。
中国における染付は宋時代に創設されたましたが、完成を見るのは明の宣徳期(1426~1435)です。
朝鮮の染付は李朝期(16世紀末)に始まるといわれ、日本の染付は、元和・寛永期(1615~1644)李朝染付けの流れをくむ肥前有田の金ケ江三兵衛(李参平)を創始者とされています。
文化・文政期(1804~1830)には日本の染付は全盛期を迎えました。
染錦(そめにしき)
色絵(いろえ)と染付(そめつけ)を組み合わせたもので、とくに伊万里(有田)ものが言われる。色絵だけは錦手(にしきで)ともいう。