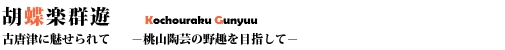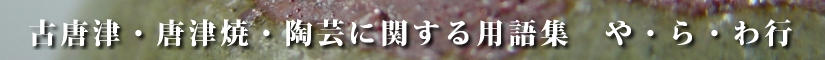古唐津・唐津焼・陶芸に関する用語集 や・ら・わ行
や
やきもの戦争(やきものせんそう)
文録・慶長の役(1592~93、97~98)をさし、日本の諸大名が戦後多くの朝鮮人陶工を連れ帰り、唐津、上野、高取、八代、伊万里、萩で茶陶をつくらせ九州諸窯発展の基礎となりました。
歴史的にみると、文禄・慶長の役は失敗とおもわれますが、文化史的角度からの評価は、西九州の窯業にはかり知れない恩恵をもたらし、後には世界の窯業に大きな影響を与えることなったことを考える焼き物の発展には貢献したと思われます。
矢筈口(やはずぐち)
口の下がくびれ、口の内側に蓋の受けがあり、水指しに多い形。志野(しの)・唐津(からつ)・備前(びぜん)などにみられます。
焼き締め(やきしめ)
成形した器を釉(うわぐすり)にかける前に乾燥させ、無釉で素地(きじ)を強く焼き締めること。
もしくは常滑や備前・信楽など、焼き締まったやきもののこと。
山疵(やまきず)
窯の中で、焼成中に生じたひび割れなどの疵。
山茶碗(やまぢゃわん)
瀬戸・美濃地方で特に使われており、須恵器(すえき)風の茶碗や杯のこと。
弥生土器(やよいどき)
約2300年前から1700年前までの間の弥生時代につくられた土器。
600~700度の低火度焼成のやきもので、壺、甕、鉢、高坏などがあります。
農耕生活の進展は土器の上にも反映され、貯蔵用の壷、煮沸用の甕、盛りつけ用の鉢・高坏といった用途別の器種を生み出しました。
特徴として、縄文土器のような複雑な文様は消え去り、機能性を求めた簡素な弥生の美の胎動がみられます。
.
ゆ
釉下彩(ゆうかさい)
低下度釉である、透明釉(とうめいゆう)の下に赤・緑・黄・紺青・紫・白などの顔料で絵付けしたもの。
釉薬(ゆうやく)
陶磁器の表面に施したガラス質の被膜。吸水性をなくし、表面を保護し、装飾性を与え、それ自体が装飾ともなる。「うわぐすり」とも呼ぶ。
唐津焼における釉薬
使用原料としての「主材」としては長石質で釉石、や耐火性が低い軟質の石類や陶土類および藁灰類で「溶剤」として土灰、松灰、樫灰、石灰石や貝灰などがあり「骨材」としては粘土類や共土などが主流で、「顔料」としては産地近郊の含鉄鉱物である黒錆、鬼板、黄土や赤土です。
一部特殊な例として後期においては磁器用の呉須や胆磐、緑青の酸化銅系があります。
これらの原料で得られた釉薬の種類として
「灰釉」「土灰軸」「透明釉」「長石釉」「斑釉」「藁灰釉」「飴釉」「黄釉」「黒飴釉」「天日釉」「鉄砂」「伊羅保」
その他に、二種の重ね掛け、または掛け分けなどの技法による「朝鮮唐津」などがあります。
いずれも身近にある入手しやすい原材料を用いて調整した2~3成分系が主流であり、原料の選択として「主材」「骨材」と更に「顔料」まで兼ねた材料に「溶剤」の添加で各種の独特な組み合わせで釉薬調整がなされたと考えられます。
「主材」に対して「溶剤」の添加量次第で釉性状は連続的に変化し長石質主材の透明系では、白濁質の「長石釉」から透明性の「土灰釉」高光沢の「灰釉」へと順次移行していきます。
これらの釉調をみても唐津焼は民陶として雑器を作っていたのが伺い知れますね。
釉下彩(ゆうかさい)
釉の下に、絵付けを行うことで、鉄絵、染付、釉裏紅がこれに当たります。
釉裏紅(ゆうりこう)
鮮紅釉ともいい、釉下の紅色の文様のある磁器。
酸化銅によって還元炎焼成し、釉薬の下に紅色の発色を施す技法
中国・元時代に始まった、銅釉を還元焼成により鮮紅色に発色させるやきもので、日本では「辰砂」と呼ばれています。
釉裏紅も釉下彩の一種で、青花よりも焼成温度の管理が難しい高度な技法として知られ呈色剤の銅が、火度が低すぎると黒みを帯び、高すぎると揮発して文様が飛散してしまう性質があります。
16世紀前期、西有田の広瀬窯で多く造られています。
釉裏青(ゆうりせい)
中国での染付(そめつけ)の呼称。呉須(ごす)で模様を下絵付けして、その上に透明釉(とうめいゆう)を掛け焼いたもの。
油滴(ゆてき)
黒釉の表面に、銀色の斑文が現れた窯変(ようへん)の一種。水面に油の滴をたらしたような様が、名前の由来。
よ
陽刻(ようこく)
陰刻(いんこく)に対して浮き彫りにした文様のこと。
耀州窯(ようしゅうかま)
中国陜西省耀県銅川市附近に分布し、中国陶磁史において有名な窯場です。
唐から元・明に至るまでの長期間活動し、その作風は華北・華南に影響を与え、隆盛を極めました。
初唐には黒釉磁、盛唐には三彩や素胎黒花をつくり、中唐には青磁が登場します。
宋代に入って片刃彫りや型押しによって文様をあらわしたオリーブ・グリーンの青磁を作り上げたことで、その技術の高さを知らしめました。
金代以降は、次第に黄褐色の釉に変化し、その作風を変えながら明代以後まで続いていきます。
窯変(ようへん)
焼成の際に、窯のなかで予期せぬ火焔の変化や灰が降り、思わぬ釉色や釉相が現れること。
または、素地(きじ)や釉薬(ゆうやく)の成分が化学変化をおこし、予測しない釉色や釉相が現れること。
景色として見所の一つになります。
曜変(ようへん)
建盞天目茶碗(けんさんてんもくぢゃわん)の一種。瑠璃色の美しい光彩を放ち、神秘的な魅力がある窯変(ようへん)。
寄せ向(よせむこう)
一組揃いの向付ではなく、形や種類の違った向付を寄せ集めて一組とし、客の一人ずつに別々のものを出したりすることをいいます。
交ぜ向(まぜむこう)ともいいます。
名残りの茶事などで用いられます。
米量(よねばかり)
古唐津奥高麗の一種で、米の斗量に用いたとのいい伝えによりこの名があります。
米を掬うのに用いたらしく、口造りがひどく摩減りしたり欠けたりしているものがあります。
焼損じの歪みのある、青黄色の釉を施した茶碗・皿などです。
呼継ぎ(よびつぎ)
欠けた部分の陶片がなくなっている場合、似たような陶磁片をカケ部分の形に整えて補う方法。
よろけ縞文(よろけしまもん)
不規則に蛇行する縦縞のこと。
ら
楽家(らくけ)
初代長次郎に始まり、楽焼本窯の家系。
楽焼(らくやき)
京都の楽家代々の作と、脇窯の作品。手捏ねで成形し、低火度(ていかど)で焼いた軟質陶器。茶碗が多く黒楽と赤楽が主。
り
李参平(りさんぺい)
鍋島藩により朝鮮から連れてこられた陶工で、1610年代有田町の泉山で陶石を発見し、日本で最初の磁器を造ったと言われている。
李朝(りちょう)
朝鮮・李朝時代(1392~1910)の陶磁器の総称。
竜泉窯(りゅうせんよう)
宋代から始まり、青磁の中でも第一とされる砧(きぬた)青磁を焼いた、中国の浙江(せっこう)省にあった窯。
竜門司焼(りゅうもんじやき)
薩摩焼(さつまやき)の系統の一つ。
鹿児島県姶良郡加治木町産の陶磁器。
俗に黒薩摩(くろさつま)と称され、鮫肌焼などが知られる。
緑地(りょくじ)
12代今右衛門が中国・明期の緑地金襴手に範を得、上絵の緑を塗り込む技法。
鍋島的技法として、13代・14代も作品に取り込んでいます。
緑釉(りょくゆう)
酸化焼成により発色剤の銅が酸化し、鮮やかな緑を発色する鉛釉(なまりゆう)の一種。
輪花(りんか)
口縁に刻みを入れ、花形にした鉢や皿。
る
瑠璃(るり)
酸化コバルトを長石に混ぜた高火度釉で、鮮やかな藍色に発色します。
ろ
ロウ抜き(ろうぬき)
釉(うわぐすり)をかけ残したい部分にロウを塗り、その上から釉(うわぐすり)をかけて焼くとロウの部分が抜ける装飾法。
轆轤(ろくろ)
回転台で、上に粘土を乗せ回転の際の遠心力を利用して、粘土を引き伸ばして成形する道具。
ロストル
窯の中にある、薪などの燃料の下にある火格子。
露胎(ろたい)
釉薬がかかっておらず、素地が見えている状態のこと。
六古窯(ろっこよう)
中世を代表する窯場として、瀬戸(せと)・常滑(とこなめ)・越前(えちぜん)・信楽(しがらき・丹波(たんば)・備前(びぜん)の六つの窯場を指す。
わ
藁灰釉(わらばいゆう)
稲稲藁を焼いた藁灰を主原料とする釉薬(ゆうやく)。
珪酸分を多く含有するので、焼くと遊離した珪酸粒子が不熔融で焼成器物表面に白濁現象をおこす。
唐津の斑唐津や朝鮮唐津の白い釉薬として使います。
割高台(わりこうだい)
輪状ではなく、1~数カ所をV字形に欠き割ったようにした高台。大名物、朝鮮茶碗が名高い。
割山椒(わりざんしょ)
山椒の実が開いたような形で、3~5弁の鉢で向付に多くあります。
割竹式登り窯(わりだけしきのぼりがま)
朝鮮半島から伝わった登窯の一種。
連房式で竹を割って伏せたような登り窯で、竹の節のように壁で房が区切られています。
炎が一房ごとに回る連房式とは異なり、窖窯のように真っ直ぐ走ります。