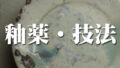古瀬戸(こせと)は、美濃(みの)と並んで中世で唯一の施釉陶器〔注:器面に釉薬をかけて仕上げる陶器〕として知られ、名古屋市の東北東約20kmに位置する瀬戸(せと)市街地を取り巻く標高100〜200mの低い丘陵帯で焼かれました。狭義の瀬戸窯(せとがま)は尾張旭市東端から瀬戸市のほぼ全域に広がり、東西約11km・南北約10kmの範囲で六百基近い古窯跡が確認されていますが、実際の数はこれを大きく上回ったと考えられます。これらの窯跡は平安後期の灰釉(はいゆう)陶窯〔注:木灰を溶剤とする透明系の釉薬を用いた窯〕から中世全期にわたりますが、各時期の分布は一様ではありません。
赤塚幹也(あかつか みきや)氏の長年の調査をまとめた『瀬戸市史陶磁史篇』に記録される分布図によれば、猿投窯(さなげがま)系の外延に属する平安後期の灰釉陶窯は南部の矢田川(やだがわ・山口川)以南に偏在し、山茶碗(やまぢゃわん)窯〔注:中世の無釉の碗を主に焼く窯〕は瀬戸市街地の西半に多く、中世の施釉陶は市街地東部から猿投山(さなげやま)西北麓へかけて集中します。これは瀬戸窯の中心が時代とともに西から東へ移り展開したことを示すもので、年代が確定する四百四十八基の内訳は平安期灰釉陶窯九基・中世施釉陶窯二百一基・山茶碗窯二百三十八基となりますが、とりわけ山茶碗窯は実数がさらに多かったと推測されます。
古瀬戸の起源については「藤四郎伝説」がよく知られます。陶祖とされる加藤四郎左衛門景正(かとう しろうざえもん かげまさ)が貞応二年(1223)に道元(どうげん)と入宋して陶法を学び、安貞二年(1228)に帰国後、各地で試作を重ね、仁治三年(1242)に瀬戸で良土を得て開窯したという筋立てです。しかし伝承を離れて遺跡・遺物に基づくと、学説は大きく二つに分かれます。第一は、輪積み成形による灰釉四耳壺(よつみみつぼ)〔注:肩や胴に四つの耳状把手を付す壺〕や瓶子(へいし)〔注:細頸の供献用瓶〕の出現を指標とし、伴出する山茶碗の編年から古瀬戸の確立を鎌倉中期に求める見解で、赤塚氏は、11世紀初頭に瀬戸市山口の広久手窯で始まった灰釉陶が12世紀に衰え山茶碗窯へ転化し、のち鎌倉中期に市街地南部丘陵で四耳壺・瓶子を大量生産する灰釉陶窯として復活した時期こそ古瀬戸の成立段階だと位置づけます。
第二は、古瀬戸特有の四耳壺の萌芽を平安末期の東山(ひがしやま)古窯跡群に求め、猿投窯の平安灰釉陶生産の延長線上に広域的に把握する立場です。平安末期に古代的生産体制が崩れて猿投窯が分解し、南方では壺・甕・擂鉢(すりばち)を主とする常滑(とこなめ)窯が成立しましたが、その分極の一つとして同じ圏域の一部に上手物の施釉陶器生産地が生まれたとみる考えです。近年の研究では、猿投窯発祥の地でありながら長い空白ののち11世紀に灰釉陶で復活した東山窯が、12世紀に他の地区が無釉雑器(山茶碗・小皿)へ移行するのに対し、院政期の中央権力や在地新興寺院の需要を背景に、屋瓦や仏器などの高級品製作に携わったことが明らかになりました。
その生産の中には四耳壺や仏器に加え、広口壺の胴に二重の沈線を巡らし、その間に牡丹文を繞(めぐ)らすといった新しい未磁(みじ)系の模倣も含まれ、古瀬戸の母胎となる技術・意匠がすでに芽生えていたことが注目されます。常滑窯が猿投窯西南部から遠く知多半島中央へ飛地的に成立した事実にならえば、高級施釉陶器の供給地としての瀬戸が東山窯の移動・継承によって形成されたと考えるのは、製品構成から見ても自然な推論といえるでしょう。
古瀬戸の製品は、美濃と並ぶ中世唯一の施釉陶であるがゆえに、山茶碗窯を除く二百基余の施釉陶窯では、比較的小型の高級日常具や仏器の生産が中心でした。大型の壺・甕(かめ)は常滑・渥美(あつみ)窯が担い、器形による分業が成立していました。需要層は社寺・貴族・武士に富裕農民まで広く及び、とくに中国陶磁の模倣——たとえば青磁(せいじ)や天目(てんもく)系の意匠——を主題とした点に特色があります。
器種は多岐にわたり、飲食具の碗・皿・鉢・水瓶・土瓶、調理具のおろし皿・擂鉢・片口・坩堝(るつぼ)・釜、貯蔵の壺・瓶・甕、日常具の薬壺・水滴・合子(ごうす)・燭台・筒形容器・洗(せん)・折縁深皿、仏具の瓶子・花瓶・仏供・燈明皿・香炉・仏塔、さらに茶陶の天目茶碗・茶入・茶壺、入子・沈子・陶丸・狛犬(こまいぬ)など、五十種を超える多様さに達します。ただし、すべてが鎌倉〜室町期を通じて一様に作られたわけではなく、時代により栄枯盛衰があります。
とりわけ鎌倉から室町初頭までの前半期は、四耳壺・瓶子・仏花瓶・香炉など、蔵骨器や社寺の祭祀具が顕著でした。これに対して室町期には、天目茶碗・茶入・灰釉平碗・小皿など消費都市を対象にした日常具——とりわけ茶陶——が前面に出ます。装飾傾向にも差があり、前者は印花文・画花文・貼花文〔注:型押し・筆描き・貼付成形による花文様〕で豊かに飾るのに対し、後者は無文が増え、むしろ釉薬表現に重心が移りました。
要約(300〜500字)
古瀬戸は瀬戸市周辺の丘陵地で焼かれ、美濃と並ぶ中世唯一の施釉陶器として展開した。窯跡は平安後期から中世全期に及ぶが、期ごとに分布が偏り、西から東へ中心が移動したことが『瀬戸市史陶磁史篇』の分布図に示される。成立論は二説あり、①鎌倉中期に四耳壺・瓶子を大量生産した段階を確立期とする見解、②平安末期の東山古窯を源流とし猿投窯の系譜上に広域的に捉える見解である。後者は院政期の高級需要に応じた東山窯の動向や未磁模倣の出現を根拠に、瀬戸への移動・継承を想定する。製品は小型高級具と仏器が中心で、大型容器は常滑・渥美が担う分業が成立。鎌倉期は祭祀具、室町期は茶陶・日常具へと主役が交替し、装飾は文様重視から釉調重視へ転じた。
【関連用語】
- 瀬戸(せと):尾張の陶磁産地。中世以降「せともの」の語源となった産地。
- 美濃(みの):岐阜県東濃の産地。のちに志野・織部・黄瀬戸など茶陶を生んだ地域。
- 常滑・渥美・猿投(とこなめ・あつみ・さなげ):中世の主要古窯群。大甕や施釉陶で知られ、瀬戸と器形分業を行った。
- 灰釉(はいゆう):木灰を溶剤に用いた透明系の釉薬。日本では飛鳥〜奈良期に登場し、中世施釉陶の基盤となった。
- 天目(てんもく):中国宋代に成立した黒釉碗の系統。日本では室町〜桃山期に茶の湯で珍重され、瀬戸でも和製天目が作られた。