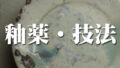【総説】
瀬戸焼(せとやき)〔注:愛知県瀬戸市を中心に産する陶磁器の総称〕は、わが国の製陶業における最大級の集積地として長い歴史と旺盛な生産を誇り、「瀬戸物(せともの)〔注:陶磁器の通称〕=陶磁器」を意味するほど名が広く定着しましたが、その背景には原料面での恵まれた自然条件と、きわめて古い技法の伝統、さらに当時の政治的中枢に近い地理的優位が相まって、茶の湯に用いる器の製作と日常雑器の大量生産が並行し、全国の窯業地に対し中核的役割を担った事実があります。
本項は概説として沿革の大要のみを述べ、坏土(はいど)〔注:成形に用いる調製粘土〕・釉料(ゆうりょう)〔注:釉薬の原料〕・成形・装飾・窯・焼成などの技術的細目には立ち入りませんので、関連事項は末尾付記の項目を参照されたいという従来の叙述方針に従い、ここでは瀬戸と美濃(みの)との歴史的関係にも触れておきますが、もともと美濃国の土岐(とき)・可児(かに)・恵那(えな)の三郡は瀬戸に隣接し、産業史的にも文化史的にも広義の瀬戸焼圏に含めて理解すべき点に留意が必要です。
【地域】
瀬戸(せと)は旧東春日井郡(ひがしかすがいぐん)に属しますが、平安時代には山田郡(やまだぐん)の一部で、のち山田荘瀬戸村と称し、その後山田郡が廃止されて春日部(はるべ、のち春日井)・愛知の二郡に分割されると瀬戸地方は春日部に編入され、さらに呼称が改められて春日井郡となり、1878年(明治11)には東西に分けられて瀬戸は東春日井郡に属し、名古屋(なごや)市の東北約20kmという位置関係が現在の地域性を規定しました。
行政の進展としては、1892年(明治25)に町制を施行し、1925年(大正14)には隣接する赤津(あかづ)村および旭(あさひ)村の一部(字今・字美濃之池)を編入、1929年(昭和4)に市制を布いて我が国唯一の“窯業都市”としての性格を明確にし、その地質環境は花崗岩・花崗岩質砂岩・砂質粘土・粘土・褐炭・礫層から成る第三紀新層(あるいは第四紀洪積層)に属し、花崗岩の風化変質による木節粘土(きぶしねんど)〔注:耐火性の高い良質粘土〕や、霧爛=濾蝕変質で生じた蛙目粘土(がいもくねんど)〔注:珪砂分を多く含む耐火粘土〕を産するなど、原料面での優位が顕著でした。
さらに本地砂(ほんじすな)・房州砂(ぼうしゅうずな)・千倉石(ちくらいし)・鬼板(おにいた)〔注:鉄釉原料となる板状酸化鉄塊〕・水打(みずうち、別称水垂)〔注:鉄分系の釉原料〕・黒浜(くろはま)〔注:鉄釉用原料の一種〕・砂絵(すなえ)〔注:装飾・耐火用の砂原料〕など特殊窯業原料も産出し、燃料面でも近隣に黒松が豊富であったため、総合的に見て陶業立地としてきわめて恵まれていました。
周辺地域として、品野(しなの)町は瀬戸市の東北に接し、1906年(明治39)に下品野村・上品野村・掛川町を合併して1924年(大正13)に町制を施行、1959年(昭和34)に瀬戸市へ編入され、水野(みずの)村は瀬戸の西隣で江戸時代の代官所所在地として機能し、1885年(明治18)に上・中・下の各水野を合併して水野村と称し、1889年(明治22)に村制施行ののち瀬戸市へ合併するなど、広域の窯業圏を形成して行政的にも一体化が進みました。
要約(300〜500字)
瀬戸焼は愛知県瀬戸市を中心とする陶磁器の総称で、原料・技術・立地の三要素が揃ったことにより、茶の湯の器から日常雑器までを大量かつ継続的に供給し、日本の窯業史で中核的地位を占めました。叙述は沿革の骨子に限り、技術詳細は扱いませんが、地理・行政の推移としては、山田郡から春日部(のち春日井)郡を経て東春日井郡に属し、1892年町制、1929年市制を施行して「窯業都市」として確立します。地質は第三紀新層(第四紀洪積層を含む)で、木節粘土・蛙目粘土などの耐火原料に恵まれ、鬼板・水打・黒浜等の特殊原料や燃料資源も周辺で確保できました。品野・水野など周辺町村の編入により窯業圏は行政的にも統合され、歴史的に隣接する美濃(土岐・可児・恵那)三郡は広義の瀬戸焼圏として理解されます。
【関連用語】
- 瀬戸焼(せとやき):瀬戸市周辺で産する陶磁器の総称。
- 瀬戸物(せともの):日本で陶磁器一般を指す通称。瀬戸焼に由来。
- 木節粘土(きぶしねんど):花崗岩の風化で生じる耐火性の高い良質粘土。
- 蛙目粘土(がいもくねんど):珪砂分が多く耐火度が高い粘土。ろくろ適性に優れる。
- 鬼板(おにいた):地層上部に沈積した板状の酸化鉄。鉄釉の主要原料。
- 水打/水垂(みずうち/みずたれ):鉄分系の釉原料として用いられた鉱物資源。
- 黒浜(くろはま):鉄釉原料の一種。黒褐色系釉の発色に寄与。
- 釉料(ゆうりょう):釉薬を構成する原料の総称。長石・灰・粘土など。
- 窯業(ようぎょう):陶磁器などを窯で焼成する産業。
- 春日井郡(かすがいぐん):瀬戸地域が属した旧郡名。のち東西に分割。
- 品野(しなの)・水野(みずの):瀬戸周辺の窯業集落で、のちに瀬戸市へ編入。